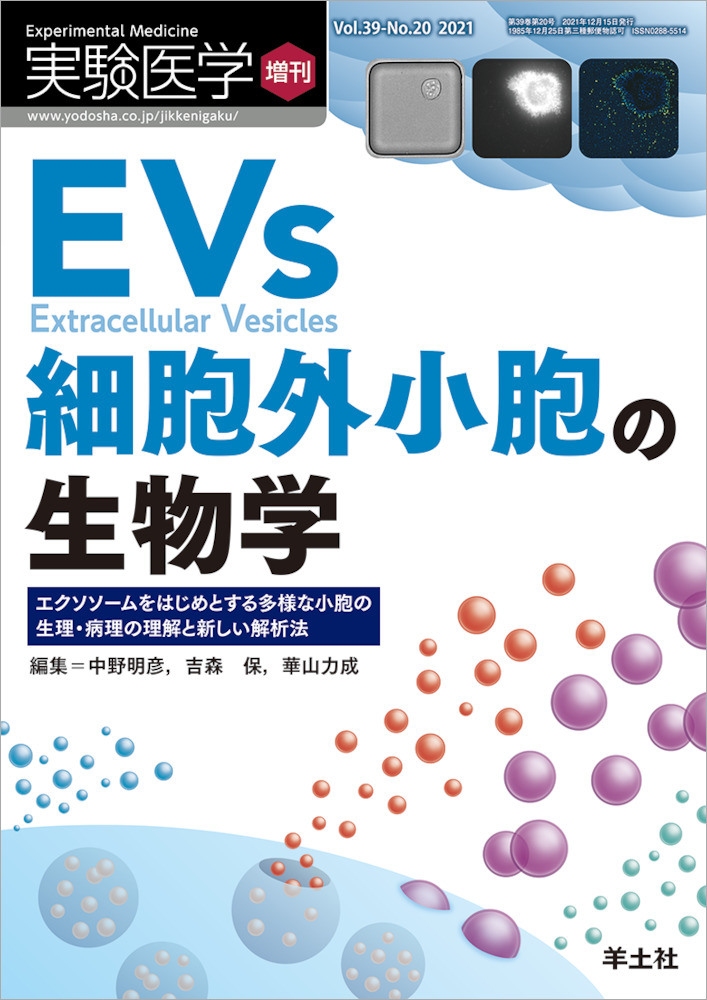概 論
過熱する細胞外小胞研究
華山力成
(金沢大学ナノ生命科学研究所)
[略語]
- DDS:
- drug delivery system
- EP:
- extracellular particle(細胞外粒子)
- EV:
- extracellular vesicle(細胞外小胞)
- ISEV:
- International Society For Extracellular Vesicles(国際細胞外小胞学会)
- MISEV:
- minimal information for studies of extracellular vesicles
- PDL1:
- programmed death ligand 1
- PS:
- phosphatidylserine
はじめに
近年,エクソソームに代表される細胞外小胞の研究が加速度的に進展し,さまざまな生理機能や病態発症との関連が示唆されている.細胞外小胞の発見自体は古く,1960年代には細胞による不要物の排出機構として存在が知られていたが1),その後ほとんど注目されることはなかった.しかし,2007年にスウェーデンのJan Lötvallらによって,細胞外小胞の内側に分泌細胞由来のmRNAやmiRNAが含まれ,それらが他細胞へと受け渡されることで遺伝子発現情報の交換に関与することが発見されて以降2),新たな細胞間情報伝達機構として,細胞外小胞の新規機能解析や疾患との関連が世界中で活発に研究されている.特に医療応用への期待は高く,2013年頃より欧米で大型研究プロジェクトが開始され,細胞外小胞を標的または応用した診断・治療法の開発が進められており3),数多くのベンチャー企業が誕生している.このような状況のもと,日本においても2017年の文部科学省の研究開発戦略目標として,細胞外小胞研究を主要な柱とする「細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御」が選定され,科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST/さきがけ)において細胞外小胞に関連する基礎研究課題が30件ほど採択された.これらの研究には,以前からの細胞外小胞の研究者のみならず,ナノテクノロジー,イメージング技術,バイオインフォマティクスなどさまざまな分野に強みをもつ研究者が多数参入しており,新たなアプローチによる融合的研究が進められている.そこで本書では,これらの事業などによりさらに加速中の細胞外小胞研究の動向と最新の成果について,以下の項目に大別して,記載していただいた.
1.細胞外小胞の多様性


細胞外小胞とは,「細胞から自然に分泌され,脂質二重層で囲まれ,複製できない,つまり機能的な核をもたない粒子の総称」であり,主としてその形成過程の違いにより,エンドソーム膜由来の「エクソソーム」や形質膜由来の「マイクロベシクル(エクトソーム)」,死細胞の膜由来である「アポトーシス小胞(小体)」などが知られている(図).しかし,これらの細胞外小胞のサブタイプは,その性質や大きさにおいてオーバーラップすることが多いうえに,その検出・単離の難しさや,精製法・解析法の違いなどでコンセンサスが得られておらず混乱を招いてきた.そこで,2012年よりISEVという会員数2,000人を超える国際的研究者コミュニティーが形成され,その機関誌Journal of Extracellular Vesiclesにおいていくつかのポジションペーパーを発信している.特に重要視されているのが,細胞外小胞研究における最低限の指標としてまとめられたMISEVガイドラインである.現時点での最新版であるMISEV20184)では,細胞外小胞のサブタイプを明確に区別する特定マーカーについてはいまだコンセンサスが得られておらず,どの形成過程によってできたものかを確定するのは困難であるため,細胞外小胞のサブタイプの表記にはエクソソームやマイクロベシクルなどの従来の用語は使用せず,表1で示すような運用的な用語を使用することが強く勧められている(一方,筆者を含めて長年研究している者にとっては,これらの用語がどの細胞外小胞を指しているのかが漠然としており,学術論文以外ではあえてエクソソームやマイクロベシクルとよんでいる者も多い).また,MISEV2018にはその他にもさまざまな指標がチェックリスト(表2)として掲載されており,従わなかった場合には論文の査読において厳しく指摘されることもあるため,本研究領域に参入される場合には必読である.なお,細胞外小胞の単離には,現在最も利用されている超遠心法/密度勾配超遠心法のほか,ポリマー沈殿法,サイズ排除/イオン交換クロマトグラフィー法,抗体/PSアフィニティー法など原理の異なる方法が利用可能であり,上記指標が満たされていれば,どの方法を用いてもよいとされている.ただし,多量に取れる方法は純度が低く,純度が高い方法は少量しか取れないなど一長一短であり,研究目的に応じた選択が必要となる.

このような細胞外小胞の定義のあいまいさを解決するためには,まずどのような種類の細胞外小胞が実際に存在するのかを,しっかりと同定する必要がある.上記のサブタイプの違いのみならず,エクソソーム1つとってみても,その古典的なマーカーとして知られるテトラスパニン(CD9,CD63,CD81など)の発現様式は個々のエクソソームや細胞種によりバラバラであり,他のマーカーや内容物の違いまでを考慮に入れると無数の種類が存在する5).このような多様性が細胞外小胞の形成過程や放出部位の違いによりどのように生み出されるのか,プロテオミクス解析を用いた研究が進められている(第1章-1,2).また,がん細胞や老化細胞では細胞外小胞の分泌量や内容物・性質が変化することが知られているが,これらの他シグナルから細胞外小胞の形成過程へのクロストークがどのように制御されているのかも重要な課題である(第1章-3,4).さらにクロストークにおいては,細胞外小胞とオートファジーは「不要な細胞内容物の除去」という共通の生理的意義を有しており,相補的な関係を担っていると考えられる(第1章-5).
加えて本書では,従来の定義には収まらない細胞外小胞にも焦点を当てた(第3章).形質膜由来の細胞外小胞は一般的にマイクロベシクルとよばれているが,その形成過程は多様であり,一次繊毛の先端が切り離されてできるものや,細胞移動に伴って形成されるものなどが新たに報告されている(第3章-1,2).また,色素細胞内でメラニン色素を含有するメラノソームは細胞外小胞として分泌され,毛母細胞や表皮細胞などへと受け渡される(第3章-3).植物由来の細胞外小胞の機能はよくわかっていないが,動物由来のものと同様の機能が示されれば,その生産性の高さからバイオ創薬への応用も考えられる(第3章-4).さらに,さまざまな細菌が特にその集合体であるバイオフィルムの状態において多くの細胞外小胞を分泌し,互いに情報を伝達していることが判明している8)(第3章-5,6).今後宿主との相互作用の解析により,常在細菌による生体制御や病原細菌による感染における新たな役割が明らかになるであろう.
2.細胞外小胞の機能
細胞外小胞の機能は,中に含まれるタンパク質やRNAなどの分子に依存するが,その発現様式は分泌細胞の種類や状態により大きく変化する.現在,治療用としてその機能が最も期待されているのが,間葉系幹細胞由来の細胞外小胞である.この細胞外小胞には,血管新生促進性やコラーゲン沈着促進性,抗炎症性のmiRNAなどが含まれており,組織修復や炎症抑制への医療応用が検討されている9).また,多能性幹細胞から分化途上にある細胞が,互いに細胞外小胞を交換することにより,それぞれの分化段階・速度を同調させる現象も見出されている(第2章-1).
免疫系において細胞外小胞は,免疫細胞間での抗原情報の交換や,免疫細胞の分化・選別など,さまざまな免疫機能の制御に関与することが示されている10)(第2章-2,3).また,がん細胞から分泌される細胞外小胞には,血管新生や転移を促進する分子が含まれており,がんの進展に適した微小環境の構築に重要な役割を担うとともに11)(第2章-4),がん細胞を攻撃するT細胞の活性化を強力に抑制するPDL1の発現が見出され,がんの免疫逃避における役割が注目されている12).一方,がん患者の樹状細胞から分泌された細胞外小胞にはさまざまながん細胞由来の抗原が含まれており,がん細胞特異的なT細胞の強い活性化を引き起こすことが知られているが,近年では,細胞ストレス下のがん細胞由来細胞外小胞にも免疫活性化能をもつものがあることが判明し,細胞外小胞を利用したがん免疫療法の開発が進められている13)(第2章-5).また同様に,細胞ストレス下の障害肝細胞から分泌される細胞外小胞は,マクロファージや肝星細胞・内皮細胞などを活性化し,肝の線維化や炎症の促進に関与することが明らかになっている(第2章-6).さらにウイルスは,感染細胞内において細胞外小胞の産生経路を乗っ取り,その分泌量や性質を変化させることで,ウイルスの増殖や免疫逃避など非感染細胞へのシグナル伝達を制御している可能性が示唆されている14)(第2章-7).
神経系においては,神経細胞が分泌する細胞外小胞に,アミロイドβやタウ,αシヌクレイン,TDP-43など,神経細胞内で凝集することでアルツハイマー病やパーキンソン病,筋萎縮性側索硬化症などの神経変性疾患の発症原因となるタンパク質が含まれており,各疾患発症との関連性が注目されている15).加えて,細胞外小胞が血液脳関門をトランスサイトーシスにより通過することで,脳由来細胞外小胞が末梢血にも検出されることが示されており16),中枢-末梢臓器間連関における新たな役割の発見や末梢血を用いた脳疾患の診断法の開発が期待されている.
3.細胞外小胞の解析法
細胞外小胞は生体液中で非常に安定であるとともに,小胞内に含まれるタンパク質やRNAは脂質二重膜に守られており分解を受けにくい.また,間葉系幹細胞由来などの天然の細胞外小胞にはさまざまな薬効分子が含まれていること,さらには,合成生物学的手法を用いて作製した人工の細胞外小胞には目的の薬効分子や接着分子などを自在に搭載させられることから17)(第4章-1),細胞外小胞を新たなモダリティとして用いる創薬開発が活発に行われている18).しかし,特に標的精度の高いDDSとして用いるためには,どの細胞外小胞がどこへ行くのかの理解と制御が必須であり,細胞外小胞の分泌から取り込みまでの細胞・生体内における動態を一細胞/一粒子レベルで超高感度に可視化する技術の開発と,それらを制御する分子機序・性状の解析が進められている(第4章-2,3).
また,採取後長期間保存された生体液中においても細胞外小胞は比較的安定であるため,細胞外小胞は臨床検査における新たな疾患バイオマーカーのソースとして有望視されている.さまざまな疾患との相関が調べられているが,特に血中に分泌されたがん細胞由来細胞外小胞のmiRNAは,健常細胞由来細胞外小胞と構成の違いが注目されており,さまざまながんの発症との相関関係が調べられている19).さらに,尿中の細胞外小胞は腎臓・前立腺・膀胱疾患の新たな診断マーカーとして,髄液中の細胞外小胞は脳内の腫瘍・神経変性疾患のマーカーとして,羊水中の細胞外小胞は胎児の状態を反映するマーカーとして期待されるなど,細胞外小胞を用いたリキッドバイオプシーの開発が活発に進められている.しかし,現在の技術で解析される細胞外小胞は,さまざまな細胞が分泌した細胞外小胞の総和であり,それらが平均化されたものしか解析することができない.例えば,末梢血から細胞外小胞を単離し,病的細胞由来の細胞外小胞の解析を行う場合,圧倒的多数を占める健常細胞由来の細胞外小胞の影響により,バイオマーカーの検出感度が劇的に低くなってしまう.よって,各種ナノデバイス技術を応用して一粒子レベルで細胞外小胞を解析する技術(第4章-4,5,6)や,細胞外小胞内のRNAを一分子レベルで検出する技術(第4章-7)の開発が重要であるとともに,由来細胞の種類や状態などの情報を細胞外小胞表面のタンパク質や脂質二重膜構造・糖鎖などで識別する方法の開発が必要となっている(第4章-8,9).
おわりに
細胞外小胞の研究は,その検出や単離の難しさ,さらには種々の分類方法があったため,実験データの解釈・再現性の確認が困難な状況が続いてきた.国際基準のMISEV2018ガイドラインに従った研究手法の共通化は有用であるが,それと同時に,このガイドラインに基づく新たな研究手法の開発も非常に重要である.特に,現在の主流である超遠心法を用いた細胞外小胞の単離法では,細胞外粒子など多くのコンタミが混入しているため,これらの細胞外小胞を用いた実験結果が,真に細胞外小胞の機能を反映しているとは厳密には言い難く,革新的な細胞外小胞の単離・解析技術の確立と普及が早急に求められている.また,現在行われている細胞外小胞の機能解析研究の多くでは,高度に濃縮された細胞外小胞が過剰に投与されており,それによって引き起こされる生命現象が生理的な条件下で本当に起きているのかは不明である.細胞外小胞の機能解明のためには,その形成・放出・機能分子の内包化機構の解明が不可欠であり,このことによってはじめて,特定の細胞や臓器特異的に細胞外小胞の分泌を亢進または阻害させ,その生理機能を解明することが可能となる.細胞外小胞の研究は世界的な広がりを見せているが,しっかりとした基礎的研究による基盤整備がなされなければ,多くの混乱を招き一時的なブームで終わる危険性も孕んでいる.そのためには,有用な情報や技術を共有する体制の構築が今後ますます重要となっていく.本書がその一助となり,日本発のブレイクスルーの創出に貢献することを期待する.
文献
- van Niel G, et al:Nat Rev Mol Cell Biol, 19:213-228, doi:10.1038/nrm.2017.125(2018)
- Valadi H, et al:Nat Cell Biol, 9:654-659, doi:10.1038/ncb1596(2007)
- Das S, et al:Cell, 177:231-242, doi:10.1016/j.cell.2019.03.023(2019)
- Théry C, et al:J Extracell Vesicles, 7:1535750, doi:10.1080/20013078.2018.1535750(2018)
- Kalluri R & LeBleu VS:Science, 367:doi:10.1126/science.aau6977(2020)
- Yamauchi T & Moroishi T:J Biochem, 169:155-161, doi:10.1093/jb/mvaa132(2021)
- Teng F & Fussenegger M:Adv Sci (Weinh), 8:2003505, doi:10.1002/advs.202003505(2020)
- Toyofuku M, et al:Nat Rev Microbiol, 17:13-24, doi:10.1038/s41579-018-0112-2(2019)
- Phinney DG & Pittenger MF:Stem Cells, 35:851-858, doi:10.1002/stem.2575(2017)
- Veerman RE, et al:Trends Mol Med, 25:382-394, doi:10.1016/j.molmed.2019.02.003(2019)
- Xu R, et al:Nat Rev Clin Oncol, 15:617-638, doi:10.1038/s41571-018-0036-9(2018)
- Daassi D, et al:Nat Rev Immunol, 20:209-215, doi:10.1038/s41577-019-0264-y(2020)
- Lindenbergh MFS & Stoorvogel W:Annu Rev Immunol, 36:435-459, doi:10.1146/annurev- immunol-041015-055700(2018)
- Raab-Traub N & Dittmer DP:Nat Rev Microbiol, 15:559-572, doi:10.1038/nrmicro.2017.60(2017)
- Hill AF:J Neurosci, 39:9269-9273, doi:10.1523/JNEUROSCI.0147-18.2019(2019)
- Mustapic M, et al:Front Neurosci, 11:278, doi:10.3389/fnins.2017.00278(2017)
- Jafari D, et al:BioDrugs, 34:567-586, doi:10.1007/s40259-020-00434-x(2020)
- Wiklander OPB, et al:Sci Transl Med, 11:doi:10.1126/scitranslmed.aav8521(2019)
- Shah R, et al:N Engl J Med, 379:958-966, doi:10.1056/NEJMra1704286(2018)
著者プロフィール
華山力成:1999年大阪大学医学部卒業後,長田重一教授のもとでアポトーシス細胞の除去機構を研究.米国ハーバード大学医学部(Michael Greenberg研究室)HFSPフェロー,京都大学大学院医学研究科助教を経て,2011年に大阪大学免疫学フロンティア研究センターにて独立准教授として研究室を立ち上げ,細胞外小胞の研究を開始.’15年より金沢大学医学系教授,’17年より同ナノ生命科学研究所教授.免疫・がん・神経変性における細胞外小胞の機能解明と細胞外小胞を用いた創薬開発をめざしている.