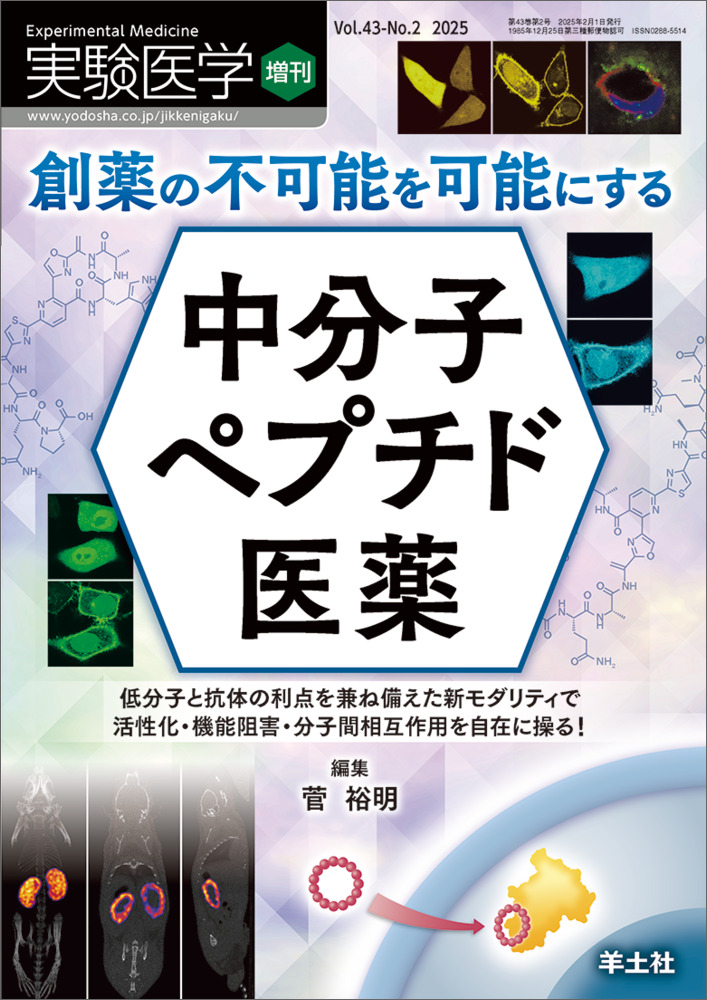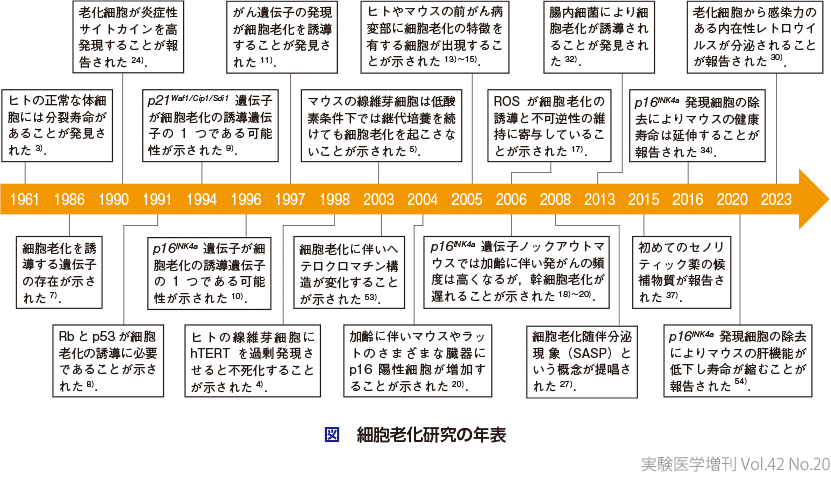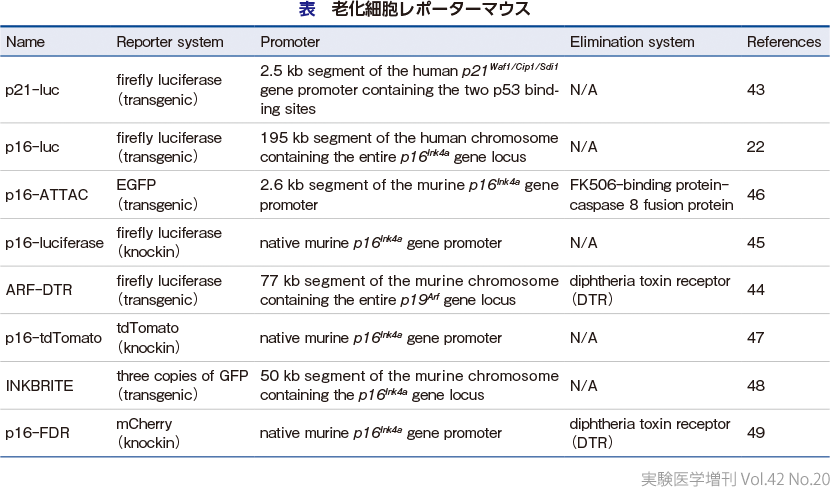序にかえて
ペプチド創薬と治療薬開発のさらなる進展に期待する!
菅 裕明
(東京大学大学院理学系研究科化学専攻生物有機化学教室)
はじめに
ペプチド分子が疾患治療を目的に研究されてきた歴史は長い.ペプチド領域のノーベル賞というと,日本では1984年にノーベル化学賞で受けた「ペプチド固相合成の先駆者」であるMerrifield博士のことを称えることが多いが,歴史的にみると1955年に「硫黄を含んだペプチドホルモンの合成と生化学の先駆者」であるdu Vigneaud博士がノーベル化学賞を受賞,さらに「神経ペプチドの発見」を果たしたGuillemin・Schally両博士,「神経ペプチドの放射線検出法の開発」したYalow博士(女性)が1977年にノーベル生理学・医学賞を共同受賞している.インスリンをペプチドと捉えれば,さらに遡ること1923年に「インスリンの発見」に貢献したBanting・Macleod両博士がノーベル生理学・医学賞を受賞している.日本のペプチドホルモン研究の発展に大きな貢献をした松尾壽之博士は,Schally博士のもとでノーベル賞受賞に至る研究に大きく寄与したことも忘れてはならない.また,化学分野では赤堀四郎・榊原俊平両博士のペプチド解析や合成研究も世界に先駆けた研究成果で,その後の国内外のペプチド研究の進展に大きく貢献したことは,ペプチド研究者ならば誰もが知っていることである.
ペプチド研究からペプチド医薬品開発へ
日本のペプチド研究も,前述の先駆者のもと1980年以降大きな発展を成し遂げてきた.その一方で,国内の製薬企業の多くはペプチド医薬品開発から徐々に後退・撤退していった.2003年にアメリカから日本に帰国した私は,新たな方法論と技術でペプチド医薬品を開発すると意気込んでいた.しかし,現実は厳しく,ほとんどの国内製薬企業からは「ペプチドを医薬品にするのは難しい」と言われたのも事実だ.しかし,糖尿病治療薬としてインスリンを開発していた製薬企業は,新しい治療薬としてGLP-1受容体作動薬の開発に挑み,その成功が目の前に迫っていた.ついに,2005年にはエキセナチドが糖尿病の新たな治療薬としてアメリカで認可される.その後のGLP-1受容体作動薬の開発競争や近年の治療展開は今や誰もが知るところだが,その当時ここまでの成功を多くのペプチド研究者が予測していたわけではなかっただろう.
ペプチド探索から特殊環状ペプチド探索へ
先に言及しなかったが,2018年に「ペプチド・ファージディスプレイの先駆者」であるSmith博士がノーベル化学賞を受賞している.彼のペプチドディスプレイ技術は,同時にノーベル賞を受賞したWinter博士によりscFv(single chain fragment variable region:一本鎖可変領域)へと展開され,抗体医薬品開発において大きな貢献を残した.scFvのCDR(complementarity- determining region:相補性決定領域)は抗原結合を主として担う3つのループ構造からなり,三次元立体空間をあらかじめもつランダム・ライブラリーからscFv活性種を探索することができた.したがって,ファージディスプレイで達成可能な10億種類の多様性ライブラリーからでも標的タンパク質への高い結合力をもつ活性種が得られていた.一方で,ファージディスプレイでペプチド活性種を探索する場合,三次元構造の多様性と適度な硬さを兼ね備えることが難しい短鎖ペプチドでは,発見される活性種の結合活性がそれほど高くなく(しばしば解離定数がμMレンジ),医薬品開発への展開に限界があった.
2005年頃,菅研ではフレキシザイム技術によって非タンパク質性アミノ酸を遺伝暗号に複数アサインし,特殊環状ペプチドを試験管内でリボソーム翻訳合成をする技術を完成,2006年前後にはこの技術とmRNAディスプレイと組合わせて1兆種類を超える特殊環状ペプチドをディスプレイするRaPIDシステムを完成させた.この技術を応用した薬剤候補探索を菅研ではじめた時期に,社会実装を目的としてペプチドリーム社は立ち上がったのである.菅研では,基盤技術の研磨と技術検証のための薬剤候補探索に注力し,獲得された特殊環状ペプチドリガンドが標的タンパク質に対して「解離定数がnMレンジ」という画期的な成果を発表した.同時に,ペプチドリーム社はその技術を用いた「特殊環状ペプチド薬剤の探索」を進めるため海外製薬企業と交渉をはじめ,技術の信頼度と他技術では達成できない技術の高度さを武器に2010年から海外製薬企業を中心とした協業がはじまった.さらに,設定されたマイルストーンを確実に達成したことで協業製薬企業から技術ライセンスの要望が増え,それに応える形で技術ライセンス契約も結んだ.「創薬プラットフォーム技術のビジネス展開」の先駆者としてペプチドリーム社は高い評価を受けたわけである.
経⼝吸収性ペプチドやPDCの開発へ
現在では,mRNAディスプレイを用いたペプチド薬剤候補探索は大手海外企業のスタンダードになったとさえ言える.しかし,それらの企業がめざしているのは,抗体の代替品としての注射剤でなく,経口吸収性のペプチド薬剤である.それには環状化や非タンパク質性アミノ酸の含有化はもちろんのこと,経口化を達成しうる分子の最適化である.その達成例として近年公表されたのがMSD社の開発したPCSK9経口阻害剤と中外製薬社の開発したKRAS経口阻害剤である.前者薬剤は,臨床試験が順調に進み,好成績が得られている.両企業ともペプチドリーム社から技術ライセンスを受けており,両薬剤ともmRNAディスプレイ技術から発見された特殊環状ペプチドをもとに最適化されて開発された事実は注目に値する.この技術を用いることで,さまざまな疾患にかかわるタンパク質を標的として薬剤探索ができることをかんがみれば,さまざまな経口性特殊環状ペプチド薬剤の開発が今後さらに進むことは容易に推察できる.
ペプチドリーム社が製薬企業と協業し,事業展開をした2010年前後が「特殊環状ペプチド探索ブーム」のはじまりとすれば,その果実が採れはじめた2023年に「経口性特殊環状ペプチド開発ブーム」が到来したといえる.いや,GLP-1受容体作動薬の経口剤化がすでに進んできたことを考えると,経口性ペプチド開発のブームはエキセナチドが認可されて10年後の2015年にははじまっていたのかもしれない.しかし,経口性ペプチド創薬の課題もまだ多く残されている.より高い経口吸収性や薬物動態の向上,フォーミュレーションを含めた吸収補助技術の開発等,経口性ペプチド薬剤の開発を確固たるものにする基盤はいまだ十分とはいえない.一方で,ペプチド・ドラッグ・コンジュゲート(PDC:peptide-drug conjugate),特に放射性同位体を薬剤として用いたセラノスティクスPDCは,体外排出の早いペプチドの方が抗体を用いたデリバリーよりも優れており,ペプチドリームだけでなく,世界中のスタートアップ企業や製薬企業で開発が進んでいることも見逃せない方向性だろう.
おわりに
今や誰も「ペプチドを医薬品にするのは難しい」とは言わない.ただ,低分子や抗体と比較すれば,まだ十分な研究開発がされておらず,そのポテンシャルを最大限引き出すにはまだ時間もかかるだろう.しかし,冒頭に述べた先駆者たちは,きっとその可能性を見抜き,研究をしていたに違いない.その意志は,現在もペプチド創薬研究に生きているはずだ.
本誌では,日本を代表するペプチド研究者に筆を振るっていただいた.これらの研究のほとんどは,アカデミア基礎研究である.しかし,RaPIDシステムにしても膨大なアカデミア基礎研究の背景があってこそ成立した技術であり,本誌で取り上げた基礎研究がいつ大きな応用に進展するかはわからない.それに大きな期待を寄せている一人として,本誌の編集にかかわった.これまでのペプチド創薬研究はもちろんのこと,未来のペプチド創薬を考える若い研究者たちの参考になれば,幸いである.
<著者プロフィール>
菅 裕明:東京大学大学院理学系研究科化学専攻生物有機化学教室教授.1994年,マサチューセッツ工科大学にてPh.D.取得.マサチューセッツ総合病院・ハーバード医学部博⼠研究員,ニューヨーク州立バッファロー大学助教授・准教授,東京大学先端科学技術研究センター准教授・教授を経て,2010年より現職.’06年にペプチドリーム社を設立,’18年社外取締役退任.’17年ミラバイオロジクス社を設⽴,現取締役.主な受賞は2023年ウルフ賞,2024年⽇本学⼠院賞,他.特殊ペプチド創薬,擬天然物創薬,ネオバイオロジクス創薬が専⾨.趣味はギター演奏(Jazz,Blues等).