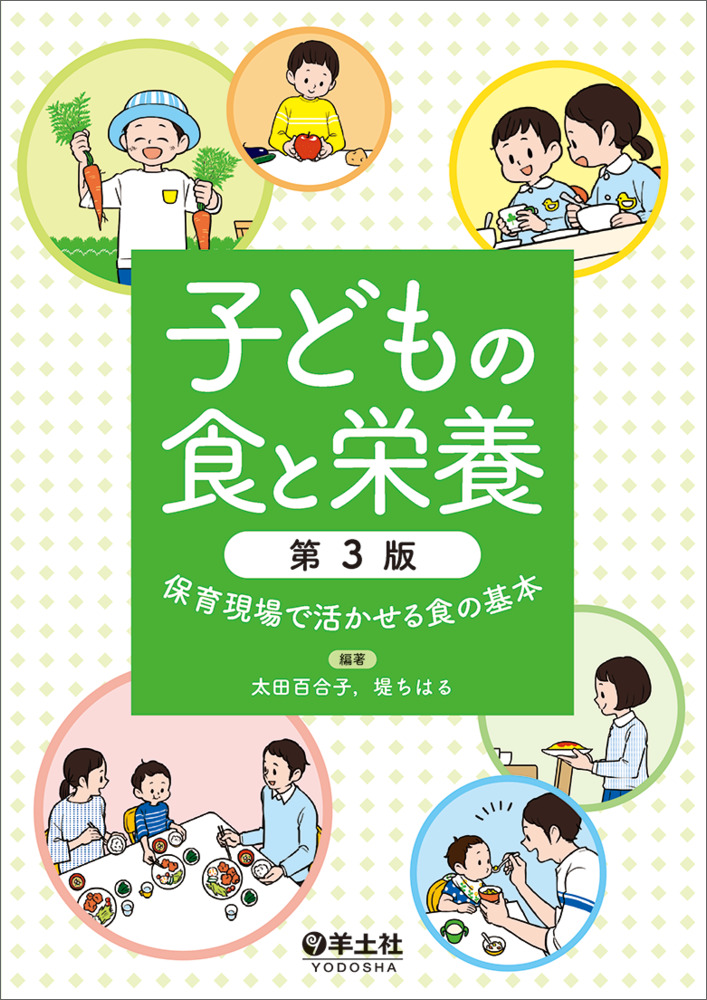第5章 乳児期の食生活
1 乳児期の食生活
A.授乳・離乳の意義
乳児期の食は,生命の維持と生活活動,発育のために必要なエネルギーや栄養素の補給を目的とする。十分な保護のもとで未熟な食機能や精神発達に対応することが,食生活の基礎づくりに大切である。
5〜6カ月までは乳汁のみで必要な栄養素等を獲得できるが,それ以降になると乳汁だけでは不足すること,また,口腔機能や消化機能は離乳食★1を通して徐々に獲得されることから,成長に合わせて離乳食を開始する(図1)。
安心と安らぎのなかで食欲や味覚,食嗜好の基礎が培われ,自分で食べたい気持ちが芽生えてくる。健康長寿の基礎となるような食習慣を身につけるには,適切な時期に適切な栄養素等を,好ましい環境のもとに提供する必要がある。
厚生労働省は「授乳・離乳の支援ガイド★2」を2019年に改定し公表した。妊産婦や子どもにかかわる支援者が,望ましい支援のあり方の基本事項を共有することを目的につくられたものである。保育者は,基本を抑えつつ,子どもの発達に合わせて栄養士,調理員,保護者と一緒に授乳・離乳を進めることが大切である。
★1 離乳食
WHO(世界保健機関)では「Complementary Feeding」といい,いわゆる「補完食」と訳されることがある。
★2 授乳・離乳の支援ガイド
「乳幼児栄養調査結果」をもとに,約10年ごとに見直されて公表されている。保護者の不安が高いことなどから,授乳期,離乳期の理解と支援などが詳しくまとめられている。
1)乳汁栄養
●授乳回数
出生後数日は,母乳の分泌量が少なく,与え方や飲み方も母子ともに不慣れなため,回数にはこだわらず頻回に授乳する。個人差はあるが,1〜2カ月経つと回数や間隔が定まってくる。3カ月頃には母乳の分泌もよくなり,授乳のリズムが備わってくる。基本的に,子どもが欲しがるときに欲しがるまま与える自律授乳★3とする。母乳は人工栄養(育児用ミルク★4)に比べて消化・吸収しやすい組成のため,人工栄養児に比べて授乳回数は多い。

●授乳方法
落ち着いた環境のなかで,子どもを横抱きにして目を見ながら行う。人工栄養の場合は,乳首にミルクが満たされた状態になるよう,ほ乳瓶を傾けて口に含ませる。乳首に空気が入っているとたくさん空気を吸い込んでしまい,余分なげっぷや吐き戻しの原因になる。
授乳後は縦抱きにして背中をさすり,排気(げっぷ)をさせる。胃の括約筋が未熟なため,飲み込んだ空気とともに乳をもどすことがある。これをいつ乳という。排気がうまくいかないときは,しばらく縦抱きで抱っこをするか,寝かせる場合は窒息予防として横向きに寝かせ,目を離さずに見ている必要がある。

★3 自律授乳
授乳は子どもに栄養素等を与えるとともに,母子・親子のきずなを深める。子どもの欲しがる欲求に応えて与えることは,心身の健やかな発育・発達を促す。
★4 育児用ミルク
乳児用調製粉乳および乳児用調製液状乳のこと。フォローアップミルクは含まれない。
B.母乳栄養,冷凍母乳
1)母乳について
母乳の成分は,子どもが効率的に消化・吸収や代謝ができる最も自然な栄養素である。母乳の組成には変化がある。例えば正期産と早産の違い,飲みはじめと飲み終わりの変化,母親の食事内容によっても影響がある。分娩後,数日間は初乳が分泌される。初乳は黄白色で,成乳に比べるとたんぱく質,ミネラルが多く,脂質,ラクトース(乳糖)が少ない。感染症を防御する免疫グロブリンやラクトフェリンが含まれているので,飲ませるように指導している。移行乳を経て14日以降には成乳となる。
成乳は,乳清たんぱく質が高く,カゼイン★5の割合が少ないため消化しやすく,アミノ酸組成は乳児の発育に適している。脂質はリノール酸,リノレン酸が多く,消化しやすい。糖質の多くはラクトースであり,カルシウムの吸収を促進する。オリゴ糖が含まれており,ビフィズス菌を増殖し,感染から身を守る。ミネラルは少なく腎臓に負担をかけず,吸収率は高い。ビタミンはほとんど含まれている。乳児に適した消化・吸収しやすい栄養成分を含むので,完全栄養といえる。母乳育児の利点と留意点は表1,表2にまとめた。
母乳栄養を続けたい保護者には,園での授乳の環境★6を整備する必要がある。


★5 カゼイン
牛乳に酸を加えると固まる成分。一般に乳固形分とよばれる成分で,消化・吸収しにくい。
★6 授乳の環境
仕事の合間などに保育所で授乳を希望する場合は,授乳室やコーナーをつくり,落ち着いて授乳ができるように環境を整える。
★7 乳幼児突然死症候群(SIDS)
元気だった子が寝ている間に突然なくなる病気である。2〜6カ月に多く,入園初期が特に危険である。0歳児クラスは睡眠時に気をつけて観察する。発症の危険を回避するためには,①うつぶせ寝にしない,②たばこは吸わない,③母乳で育てる,の3つが推奨されている。
2)母乳不足
授乳間隔が短い,1回の授乳に30分以上かかる,尿,便の回数や量が少ない,体重増加が少ない(20 g/日以下),不機嫌,元気がないなどの場合,母乳不足が考えられる。実際には足りているにもかかわらず,母親に心理的な不安が強く,母乳不足感に悩んでいることがある。母親の気持ちや状況をよく聴いて,不安にさせないようにかかわったり医療機関と連携をしたりする。

3)冷凍母乳
母親が母乳育児を継続したい場合は,園で冷凍母乳を預かり,飲ませることができる。母親は,清潔な手,もしくは搾乳ポンプを使用して母乳を搾乳し,母乳バッグに移し,空気を抜き,封をして付属のテープで固定し,冷凍する。
園で受け取るときは,名前,搾取日や時間,量,冷凍状態などの記載を確認し,すぐに冷凍庫で保管する。冷凍母乳の解凍は,成分が失われるので50℃以上の湯や電子レンジを使用しない。約40℃の湯もしくは水に浸して解凍し,母乳バッグの角を清潔なはさみで切り取り,清潔なほ乳瓶に移す。湯につけて人肌くらいに温める。
4)卒乳・断乳
母乳をやめる時期は個人差がある。母子が自然にやめることを卒乳という。仕事の都合や考え方などから母乳をやめることを断乳という。子どもの成長に影響がなく,母親の情緒が満たされるなら,どちらのやり方でもかまわない。母親の気持ちをよく聴いて,母親自身が判断できるように情報提供を心がける。
ご覧ください