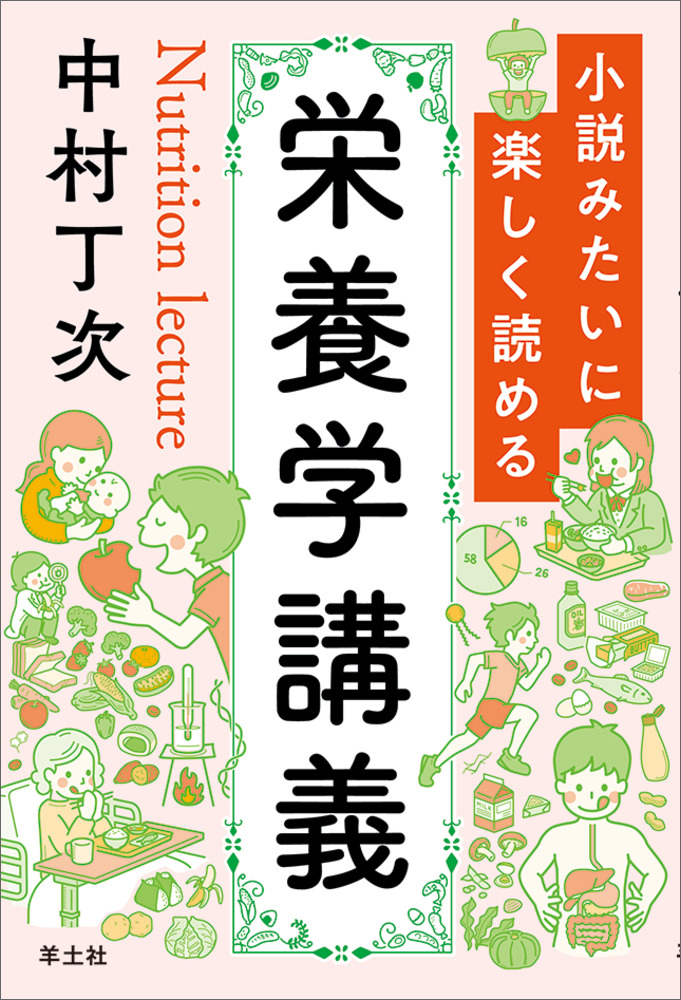本書を一部お読みいただけます
第2章 栄養素の種類と働き
人間は、日々の食事からエネルギーと生命に必要な成分である栄養素を摂取しています。栄養素には、タンパク質、脂質、炭水化物(糖質、食物繊維)、ビタミン、ミネラルがあると説明しました。また、栄養素ではないですが水も生体にとって重要です。各栄養素は、それぞれに構造的特徴があり、役割も異なります。この章では、まず栄養素の種類やその栄養素を含有する食品について説明します。そのあと、生体での働きやそのバランスが乱れたときに起こる欠乏症や過剰症について学んでみましょう。
タンパク質―人体を構成する主成分
タンパク質(protein)は、ギリシャ語で「第一の物、重要なもの」という意味をもちます。タンパク質はアミノ酸から構成され、アミノ酸は、炭素、水素、酸素以外に窒素を含有しており、内臓、筋肉、皮膚、毛、ホルモン、酵素、さらに免疫体などの主成分となります(図1)。いわば、人体を構成する主成分はタンパク質だといえます。タンパク質は、同じようにエネルギー源となる炭水化物や脂質とは異なり、約16%の窒素を含んでいるため、糖質や脂質によって代替することはできません。また、約20種類のアミノ酸から構成され(表1)、これらのうち、9種類が人体で合成できない、あるいは、合成されても必要量が満たされないために、必須アミノ酸(不可欠アミノ酸)とよばれます(※)。タンパク質は、主として肉類、魚介類、卵類、牛乳・乳製品、大豆・大豆製品から摂取できますが、炭水化物の多い穀類、いも類、果物類、野菜類などにも広く含有されています。


続きは書籍にて
ご覧ください
ご覧ください