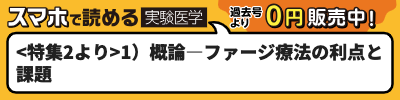概論
特集1 概論
細胞集団のふるまい・機能を創出する合成生物学
Synthetic biology of multicellular systems to create tissue-level dynamics and functions
戸田 聡
Satoshi Toda:大阪大学蛋白質研究所
近年,細胞操作技術の発展に伴って合成生物学の考え方を多細胞レベルへ拡張することが可能となり,組織形成プロセスの再構成や組織構築のデザインが実現されつつある.そこで本特集では,細胞間相互作用を操作して多細胞構造・動態を新たに創出した事例を紹介し,つくるアプローチによってどのように組織形成原理の理解が深まるか議論したい.また,多細胞体を合成するうえで重要な解析手法,光遺伝学的手法,材料工学的手法などの最新技術を紹介する.さらに,独自に進化した単細胞生物の多細胞化機構を紹介し,発生過程の再現を超えて多細胞体のデザインを考えたい.
はじめに
生体分子や細胞を使って人工的に生命機能をつくり出すアプローチは合成生物学とよばれ,生命機能が生み出される原理を理解し,生成物を直接医療・産業へ応用することが試みられている.合成生物学分野は近年目覚ましく発展しており,その代表例の1つは人工遺伝子回路であり,遺伝子発現のオン・オフを切り替えるトグルスイッチや遺伝子発現を振動させるリプレシレーターなどで,転写ネットワークの動作原理の理解と遺伝子発現操作に貢献してきた1).また,リン脂質二重膜からなるリポソームに遺伝子の転写・翻訳系や代謝経路,細胞骨格などを封入し,細胞機能の再構成を試みる人工細胞の開発もさかんに行われている2).このように,合成生物学分野では「分子のネットワーク」を設計することで細胞のふるまいを操作する技術開発や細胞自体の創成をめざす研究が進められてきた.

細胞は生命の最小単位である一方で,私たちの身体は単なる細胞の集合体ではなく,細胞どうしが相互作用しあうことによってさまざまな高次機能や複雑なダイナミクスを生み出している.例えば,生体組織内では,多種多様に分化した細胞が適切に配置され,多層構造や管腔構造などへ機能的に組織化されている.さらに,生体組織は環境変化への適応力や損傷時の自己修復能ももち合わせている.また驚くべきことに,生体組織は元をたどれば1つの受精卵を始まりとして,組織のパーツである細胞が相互作用しながら複雑な構造を自律的に形成する.このような生体組織がもつ生きものらしい特徴を理解して,それを模倣した生体材料や望み通りの構造をもった人工組織をつくれるようになることは研究者やエンジニアの大きな目標である.しかし現在の技術では,パーツが勝手に組み上がり,損傷を受けても自分で修復して何十年間も動作し続けるような人工物をつくるには至っておらず,私たちは生きものがもつ能力をまだまだ理解できていない.このような現状を打ち破るべく,合成生物学の考え方を一細胞レベルから多細胞レベルへと拡張し,さらに最新の細胞操作技術および解析技術を利用することで,「細胞のネットワーク」を設計・構築することが可能となってきた(概念図1).本特集では,「細胞のネットワーク」を設計してどのような条件がそろえば生体でみられるような組織形成過程や細胞集団動態を生成できるか検証した複数の事例を紹介する.
1細胞間コミュニケーションの操作による多細胞構造・動態の再構成
「分子のネットワーク」は,どの分子とどの分子が結合するか,結合時にどのような化学反応を起こすかを設計することで,人工的に構築することができる.同様に「細胞のネットワーク」も,どの細胞がどの細胞を認識するか,認識後に細胞がどのように変化するかを設計することで人工的な細胞間コミュニケーションネットワークを構築することができる.このとき,細胞がもともともっている細胞間シグナル分子と受容体を用いて細胞間コミュニケーションを構築すると,内在的なシグナル経路を介して多数の細胞内分子や転写因子が活性化し,細胞のふるまいを思うように制御できなくなってしまう.しかし近年,内在的なシグナル経路とは独立した新たな細胞間コミュニケーションを構築する人工受容体技術が開発され,「細胞のネットワーク」の設計の幅が一気に拡がった(概念図2)3).

2016年に開発されたsynthetic Notch receptor(synNotch)は,細胞が「認識するリガンド分子」と「分子認識時に誘導する標的遺伝子」を指定することを実現し,細胞間コミュニケーションを自在に設計することができる4).最近,synNotchを使ってシグナル分子の分泌を介した細胞間コミュニケーションを再構成することで,拡散する分子が多細胞パターンをつくり出すのに必要な条件が解明された(水野・戸田の稿).また,遺伝子発現振動の細胞間同期現象を人工的な細胞間コミュニケーションにより再構成することで,分節時計の同期を導く最小設計が見えてきた(磯村の稿).さらに,2023年にはsynthetic cell adhesion molecule(synCAM)が開発され,人工的なリガンド-受容体の相互作用を介して強固な細胞接着を誘導することで細胞配置の操作を実現した5).実際にsynCAMを用いて細胞分化を指揮する人工オーガナイザーをさまざまな位置に配置し,未分化細胞塊の細胞分化を時空間的に制御する手法が開発された(山田の稿).より最近では,前述の人工受容体以外にもSNIPR(synthetic intramembrane proteolysis receptor,膜内領域切断により活性化する人工受容体),PAGER(programmable antigen-gated G-protein-coupled engineered receptor,リガンドや応答をプログラム可能なGタンパク質共役人工受容体),リン酸化シグナル回路を制御する人工受容体などさまざまな受容体ツールが開発されている6)〜10).これらのツールを使ってより自由度の高い設計が可能になれば,「細胞のネットワーク」が組織機能を生み出す原理を解明し,細胞分化の空間操作や生体内での細胞間相互作用の操作などさまざまな応用が期待される.
2細胞集団のふるまいを操作・解析・評価する技術
細胞集団が組織構造・機能を生み出す過程でみられる細胞のふるまいは多岐にわたるため,多細胞体を合成するにあたってはさまざまな細胞操作技術が有用である(概念図2).例えば,多細胞構造が形成される過程で,細胞間コミュニケーションに加え,細胞の足場となる細胞外マトリクスとの相互作用や細胞の増殖・分化に影響するニッチなどの組織形成環境の制御が重要である11).また,ある程度大きなサイズの多細胞構造を形成するためには多細胞構造内へ酸素・栄養を輸送する脈管構造が必要となる.そこで,足場材料やマイクロ流路系を応用して脈管構造を形成する組織工学技術について紹介する(松永の稿).
組織形成過程において,細胞の遺伝子発現は単純なオン・オフではなく時空間的にダイナミックに制御されているが,薬剤などで遺伝子発現をダイナミックに操作することは容易ではない.近年開発された光遺伝学は,このような分子の活性を時空間的に操作するための強力なツールである.光の照射場所と時間を制御することで,細胞集団内の狙った領域において高い時間分解能で遺伝子発現変化を誘導することが可能となり,遺伝子発現ダイナミクスの変化と細胞集団動態の関係性を解析できる12).本特集では,周期的な光刺激を利用して培養細胞間で遺伝子発現リズムの同期現象を再構成した事例を紹介する(磯村の稿).
「細胞のネットワーク」を設計して多細胞体を形成する場合,①机上で設計した細胞のネットワークを②実際に細胞上に構築し,③細胞集団のふるまいを解析してそこで何が不足しているかを検証し,④システムの再設計および再度検証を行う,いわゆるDBTL(design,build,test,learn)サイクルを回すことが必須であり,その過程でさまざまな学びがある.しかし,このサイクルを回すためには,多細胞体の中の細胞がどのような状態にあり,設計通りの構造や機能を生成できているか正確に評価する解析技術が必要である.これには細胞集団内の多細胞動態を網羅的に解析する蛍光イメージング技術とオミクス解析が重要であり,今後多細胞体の合成に求められる全細胞解析について紹介する(洲﨑の稿).
3多細胞体制の進化vs合成
細胞が相互作用しながら多細胞体を形成する現象は,動物の発生過程だけでみられる現象ではなく,単細胞生物のなかにはユニークな多細胞構造を形成するものが存在する13).細胞性粘菌は生活環のなかで,アメーバのふるまいをする単細胞期と集合して子実体を形成する多細胞期を行き来し,化学走性,移動体の形成,柄の形成など独自の多細胞構造構築システムを進化させている.そこで,動物の神経細胞間のシナプス接続形成と細胞性粘菌の多細胞体形成における細胞間認識分子の分子構造を紹介し,進化の観点から両しくみの共通性を議論する(澤井の稿)(概念図3).

自然界では長い時間をかけた変異の蓄積や環境変動に伴って種の進化・多様化が進んできたと考えられる.一方で,合成生物学の場合はシステムをデザインすることが可能で,細胞のネットワークを高い自由度でつくりこむことができる.この「つくりこみ」によって,現存する生物がもつしくみを再構成することに加えて,長年の進化の過程で登場しなかった,あるいは過去に登場したが絶滅してしまった機能的な細胞ネットワークを見つけられる可能性がある.また,デザインベースではないが,近年,単細胞生物が多細胞生物へと進化する過程をリアルタイムで観察すべく,試験管内での人工進化実験が行われている.例えば,酵母では沈降速度を選択圧とすることで巨大な凝集体を形成する株が登場する14).単細胞が凝集するのは多細胞化の第一歩であるが,そこから選択圧をうまくデザインすることで,細胞の分化や自己複製能,恒常性などの生きものらしい特徴が人工進化によって生じうるのかたいへん興味深い.
おわりに
「細胞のネットワーク」を設計・構築して機能的な多細胞体をつくり出すことは簡単な実験ではなく,本特集で紹介する事例も,粘り強く条件検討や再設計をくり返した結果である.だが,簡単につくれないときこそ,何がわかっていないのかを突き詰めるチャンスであり,それが新たな発見・発明につながる可能性がある.また,合成したシステムはあくまでin vitroのモデルシステムであり,合成系で成り立つ現象がモデル生物でも実際に成り立つのか,現象のコアとなる原理を記述した数理モデルと比較して生きた細胞ならではの特性を見出せないか,など,異なるアプローチと連携することにより,生きものらしさの理解にぐっと近づくことができるだろう.さらに,合成した多細胞システムやマテリアルは,新たな組織構築技術としての応用利用が期待される(column参照).一方で,エンジニア指向で「つくる」ことに“全集中”して,生命らしい多細胞体を人工的にどこまでつくれるかとことん突き詰めるのもロマンがある.偶然本特集に目が留まった研究者の方に,本特集が自分の興味のある生命現象を人工的につくれないかと一考するきっかけになれば幸甚である.
多細胞の合成生物学の応用可能性
合成生物学の重要な目的の1つは,つくったものを実際に医療や産業に応用することによる社会貢献である.生命システムを設計してつくること自体おもしろいし,つくる過程でさまざまな検証を行うことで生命現象のしくみの一端でも理解できれば嬉しいが,さらにつくったものが医療・産業に応用されて多くの人の役に立つことができれば研究者冥利につきる.近年,血液がんを認識して排除するようにデザインしたCAR-T細胞療法の効果が実証され,より高機能で固形がん治療などにも応用できるような次世代細胞医薬の開発が世界的に行われている15).そのなかで,細胞間コミュニケーションを操作する技術は,がん細胞認識の特異性向上やがん組織環境改変のための技術として利用されている.がん細胞は排除する対象であるが,逆に,難治性疾患などにより失われた組織および組織機能を回復させたい場合に,人工受容体を導入した細胞の移植や遺伝子治療の方法で生体内に新たな細胞間コミュニケーションを構築することが,再生医療の実現に役立つかもしれない.(戸田 聡)
文献
- Cameron DE, et al:Nat Rev Microbiol, 12:381-390, doi:10.1038/nrmicro3239(2014)
- Ivanov I, et al:Annu Rev Chem Biomol Eng, 12:287-308, doi:10.1146/annurev-chembioeng-092220-085918(2021)
- Toda S, et al:Science, 361:156-162, doi:10.1126/science.aat0271(2018)
- Morsut L, et al:Cell, 164:780-791, doi:10.1016/j.cell.2016.01.012(2016)
- Stevens AJ, et al:Nature, 614:144-152, doi:10.1038/s41586-022-05622-z(2023)
- Yang X, et al:Science, 387:74-81, doi:10.1126/science.adm8485(2025)
- Kalogriopoulos NA, et al:Nature, 637:230-239, doi:10.1038/s41586-024-08282-3(2025)
- Piraner DI, et al:Nature:Online ahead of print, doi:10.1038/s41586-024-08366-0(2024)
- Zhu I, et al:Cell, 185:1431-1443.e16, doi:10.1016/j.cell.2022.03.023(2022)
- Chao G, et al:Cell, 185:3551-3567.e39, doi:10.1016/j.cell.2022.08.012(2022)
- Hofer M & Lutolf MP:Nat Rev Mater, 6:402-420, doi:10.1038/s41578-021-00279-y(2021)
- Krueger D, et al:Development, 146:dev175067, doi:10.1242/dev.175067(2019)
- Kawabe Y, et al:Int J Dev Biol, 63:359-369, doi:10.1387/ijdb.190108ps(2019)
- Bozdag GO, et al:Nature, 617:747-754, doi:10.1038/s41586-023-06052-1(2023)
- Baker DJ, et al:Nature, 619:707-715, doi:10.1038/s41586-023-06243-w(2023)
本記事のDOI:10.18958/7691-00001-0001876-00
著者プロフィール
戸田 聡:2009年京都大学工学部物理工学科卒業,’14年京都大学大学院医学研究科修了(長田重一研究室),’15年カリフォルニア大学サンフランシスコ校博士研究員(Wendell Lim研究室),’19年10月金沢大学ナノ生命科学研究所にて独立,’24年4月より現職(大阪大学蛋白質研究所准教授).分子の集合,細胞の集合がどうやって生きものになるのかに興味があり,培養細胞の塊を「生きもの」にすべく,細胞間相互作用のデザインや細胞の挙動を操作するツールの開発を行っている.細胞や生体分子を使ったものづくりやその医療応用に興味のある学生・研究員を募集中.