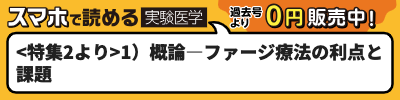概論
ポストビッグデータ時代の精神疾患研究
病態生理の学際的な理解に向けて
Psychiatric research in the post-big data era
友田利文
Toshifumi Tomoda:Centre for Addiction and Mental Health, University of Toronto(トロント大学薬物依存精神研究センター)
ポストゲノム時代の精神疾患研究はゲノム情報の網羅的解析とビッグデータ解析ツールの進歩で様変わりした.これらは貴重な情報であるが,それをどのように生物学的な理解に結びつけ,臨床応用するかについてはまだ明らかでない.その結果をふまえて,今後の精神疾患研究はどう進むのか? 本特集ではその方向性の一例をご紹介する.具体的には,精神疾患は神経回路機能異常が重要な病態生理の一つではあるが,そのさらに根本に全身にわたる器質異常がかかわることが各種ビッグデータ解析からも裏付けられてきた.特に,代謝疾患,炎症あるいは免疫異常,微生物学,基礎細胞生物学的変化が今後さらに追求されるべき課題だと考える.精神疾患の病態生理の研究が,脳神経科学だけでなく他分野も参画する学際的な研究分野に発展することを期待したい.
はじめに―精神障害の基礎知識
精神障害は,古くから知られるうつ病,統合失調症,双極性障害,自閉症などの狭義の精神疾患に加えて,発達障害,知的障害,パーソナリティー障害,心的外傷後ストレス障害,睡眠障害,摂食障害など,こころの不調を背景にもつ広義の病態を含めると,現代ではじつに4人に1人が生涯の間にいずれかに罹患すると言われるほど非常に一般的な病態である.増える老年人口とともに増加が指摘される神経変性疾患に伴う認知症,および老年期うつ病の予想される増加も含めて,精神障害が,個人・社会・経済レベルに及ぼす影響が今後も増大していくことは間違いない.21世紀は“脳の時代”あるいは“心の世紀”と言われて以来,精力的な脳研究・精神病態研究が進められ,特に2003年のヒトゲノムプロジェクトの完了とその後のバイオインフォマティクス関連技術の進歩に裏打ちされ,過去10年間に遺伝学分野での発見が精神疾患の病態の解明に大きく貢献してきた.他の多くの身体疾患と異なり,生きた脳を対象とした研究が大きく制約を受ける精神・神経疾患は,遺伝学,および死後脳を用いてよりダイナミックな遺伝子発現変化のプロファイルを探索し,疾患病態生理の理解をめざすような研究手法との親和性が特に高く,ビッグデータの解析を中核としたデータドリブンな研究が世界的な潮流である.
このような精神疾患研究の進歩は,どのように病因の解明,診断や治療に役立てられているのだろうか? まず病因については,代謝疾患,生活習慣病,あるいは心臓血管障害と同様,精神疾患の多くは多因子性であり,複数の遺伝的危険因子と環境要因の相互作用が発症や増悪にかかわることが明らかである.例えば,統合失調症とうつ病の場合,ゲノムワイド関連解析(GWAS)の結果,多数の遺伝的危険因子が近年報告されており1)2),個々の遺伝的多型の病態生理への貢献度は小さいものの,ライフイベントの変化や心理社会的あるいは生物学的ストレスに対する不適応状態を介して発症に至ると考えられる(ストレス仮説).次に,診断に関しては驚くべきことに,疾患としての認識・記載がされて以来1世紀以上にわたる研究の歴史があるにもかかわらず,精神疾患には特異的な器質異常も,診断に有用なバイオマーカーも存在しない.精神疾患の診断は,症候学にもとづき,一連の主観的,客観的症状の組合わせに応じてカテゴリーとして分類され診断されるものであり,一つの診断名に対して複数の異なる病因が含まれる可能性が高く,このことは前述の遺伝的多型の存在と矛盾しない.最近,うつ病の診断に関して,機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)による画像をもとに脳神経回路の結合状態を予測し,うつ病を4つのサブタイプに分類できること,それにより経頭蓋磁気刺激法(TMS)が治療に有効なうつ病のサブタイプを予測できる可能性が示唆された3).ビッグデータ解析を活用した臨床応用の一例として,この診断ツールがさらに多くの精神疾患に一般化できるアプローチとなるか,今後の展開が期待される.
一方,精神疾患の治療に目を向けると,現状は深刻である.例えば,うつ病の治療の場合,60年以上前に偶然に見つかった三環系抗うつ薬にはじまり,現在主流の選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)に至るまで,神経伝達物質である脳内モノアミンの不足が原因とするモノアミン仮説にもとづき,類似の機序の薬剤が開発され使用されてきた4).しかし,患者の約50%には十分な効果が認められないこと,効果の発現までに数週間を要すること,長期使用で治療抵抗性となる場合があること,自殺念慮・企図などの深刻な副作用が存在すること,など多くの問題があり,モノアミン仮説はうつ病の病態の一部の側面しか説明しないと考えられる.統合失調症についても同様に,脳内モノアミンであるドパミンの脳内バランス不全が原因であるとするドパミン仮説にもとづき5),ドパミン受容体遮断薬が治療に使用されるが,重篤な副作用があり,また,興奮性のグルタミン酸や抑制性のGABAなど他の神経伝達物質の機能不全を示唆する仮説も提唱され6)7),ドパミン仮説は統合失調症の病態の一部の側面しか説明しないと考えられる.最大の問題は,モノアミン神経伝達を標的とした薬物治療はおのおのの疾患の症候の改善を指標に開発されたものであり,その背景にある病態生理メカニズムの理解にもとづいた治療ではないことにある.これは他の身体部位の器質疾患の薬物療法では考えられない状況であり,精神障害全般に対する社会的偏見や精神疾患治療に対する懐疑的な見方を助長する原因の一つでもある.より効果の高い治療法の開発のためには病態生理メカニズムの解明が喫緊の課題であるといえる.
精神疾患研究の最新動向

では,近年の遺伝学とビッグデータ解析の進歩は精神疾患の病態生理メカニズムの理解にどのように貢献しているだろうか? まず,当然のことながら,精神疾患のGWASからは神経回路機能異常の原因となる神経伝達物質とその制御に関与する分子の異常が確認されてきた.同時に,多因子性の身体疾患にも共通する多くの器質的な異常を示唆する知見が見出され,これらが,精神疾患にみられる神経回路機能異常とともに疾患病態にかかわるらしいこと,あるいは,神経回路機能異常はむしろエピフェノメノン(付帯現象)であり,その背景にある根本の原因として脳以外の全身にわたる器質異常がかかわるらしいことが示唆されてきている.しかしこれらの興味深いデータはそのままではヒト遺伝学上の相関関係を示すにとどまる.病態生理として確立し診断や治療へ向けた意義づけを行うには,因果関係を証明する機能解析によって支持される必要がある.ヒトゲノムプロジェクトが完了したのち,2005年以降,精神疾患に限らず全体として数千を超えるGWASが行われ,各種疾患に関与する遺伝的背景が明らかにされつつある一方,機能解析により因果関係の証明に至った研究は二桁少ないことが最近の論文で指摘されている(図)8).つまり,多くの報告されている遺伝学的知見は機能解析による検証と意義づけがされないまま,データとして誰かに利用される日を待ち続けている.精神疾患の遺伝学研究もこのなかに若干数含まれるが,これらが今後放置されることなくフォローアップされ病態の解明と診断・治療開発へと応用される必要がある.
本特集では,ポストビッグデータ時代にどのような精神疾患研究が可能になっていくか,その例として,最近の話題を6稿にわたって紹介する.いずれも,精神疾患の神経回路機能異常の背景にある病態生理に迫るべく,あえて脳機能からいったん離れた立場でさまざまな角度から機能解析に取り組んだものである.
① 田口・石塚らは最近,統合失調症と代表的な代謝障害である糖尿病との間に双方向性の関係があり,これらに共通する分子基盤としてインスリンシグナルの異常を報告している9).これまで臨床的な見地からは,統合失調症に対する薬物療法の副作用として高血糖,肥満,糖尿病等のメタボリックシンドロームが生じることが問題とされてきたが,今回はじめて代謝障害と共通のメカニズムが統合失調症の病因の一つとして発症に直接関与し,これが精神疾患の主要症状である認知機能異常の原因となることが示唆された(田口・石塚の稿).
② 住友・友田らは,全身のすべての細胞の恒常性維持のメカニズムであるオートファジーが,神経細胞においてシナプス関連タンパク質の品質管理(プロテオスタシス)にかかわり,神経伝達と認知機能の制御を行うメカニズムの一端を明らかにした10).特に,興奮性神経細胞表面への抑制性GABA受容体の提示がオートファジー調節により制御されることを示し,古くから知られる統合失調症における皮質の脱抑制現象を分子レベルで説明する新しいメカニズムを示唆している(住友・友田の稿).
③ 田中・遠藤らは,神経変性疾患に合併した精神疾患様症状や自閉症スペクトラム症において,特定のタンパク質の凝集化が精神障害の原因となる可能性を呈示している.神経変性疾患の場合と異なり,精神疾患にみられるタンパク質凝集は神経細胞の生存に影響するものではないが,神経細胞機能を低下させ情動や社会性行動異常を引き起こすらしい.②の神経細胞におけるオートファジー低下でも特定のタンパク質の凝集化がみられ11),これら細胞生物学的基盤が精神疾患に共通の概念として一般化できるか興味深い(田中・遠藤の稿).
④ 長谷らは,腸内常在細菌叢(マイクロバイオータ)が腸-脳相関を介して神経細胞機能・回路機能,および行動や情動を制御するしくみを紹介している.マイクロバイオータの異常は他の多くの身体疾患(免疫疾患・代謝疾患)とともに神経変性疾患や精神疾患の素因・増悪因子となる12).GABA等の神経伝達物質が,進化の過程で細菌により産生され,ヒトの神経系の制御にも関与している事実は,精神疾患病態の全体像の解明において脳回路だけでなく全身の生理機能の理解が必要であることを想起させる(長谷の稿).
⑤ 長谷川・酒本・神谷らは,統合失調症や自閉症スペクトラム障害などの発達障害における病態生理メカニズムとして脳内免疫システムと炎症が関与することを示している13).免疫異常や炎症は,外因性の環境要因が発達障害患者の脳内で引き起こすストレス応答として捉えることができ,精神疾患のストレス仮説を支持するメカニズムと言える.また,発達期に胸腺の萎縮退行が起こる時期が統合失調症の好発年齢と重なることは,個人的には内在性の免疫機能変化が病因に影響する可能性が想起され,興味が尽きない(長谷川らの稿).
⑥ 北岡・古屋敷らは,慢性ストレスマウスモデルを用いたうつ病の病態生理解析から,脳内および末梢で炎症様反応が起き,それが中枢において,ストレス感受性が選択的に高いことが知られる前頭前皮質の一部分のミクログリアを介した炎症シグナル伝達経路を活性化することにより,うつ症状に関連した行動異常を引き起こすことを示した14).末梢を循環する免疫担当細胞や物質が脳機能を調節するメカニズムは,前述の腸-脳相関とあいまって精神疾患病態生理における全身性の機序の理解の重要性を示している(北岡・古屋敷の稿).
おわりに

以上,さまざまなアプローチによる精神疾患病態生理の解析の試みの例を簡単に列挙したが,詳細は続く各論でそれぞれの筆者の先生方の稿を読んでみていただきたい.最後に,本特集で取り上げた話題と脳機能制御の関係を概念図にまとめた.領域としては代謝疾患,炎症あるいは免疫異常,微生物学,基礎細胞生物学的変化と多岐にわたるメカニズムが精神疾患の病態生理に関与しているわけだが,統括的なキーワードは,『全身』の病態に着目することであり,精神疾患を,外因性・内因性のサイコジェニックな(心因性の)ストレスに対する神経系の『ストレス応答反応』と定義することに尽きると思う.このアプローチが今後さらに関連領域を巻き込んで学際的な研究分野として発展し,新たな診断・治療戦略の構築につながることを期待したい.
文献
- Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium:Nature, 511:421-427, 2014
- Howard DM, et al:Nat Neurosci, 22:343-352, 2019
- Drysdale AT, et al:Nat Med, 23:28-38, 2017
- Hirschfeld RM:J Clin Psychiatry, 61 Suppl 6:4-6, 2000
- McCutcheon RA, et al:Trends Neurosci, 42:205-220, 2019
- Coyle JT:Harv Rev Psychiatry, 3:241-253, 1996
- Gonzalez-Burgos G, et al:Curr Psychiatry Rep, 12:335-344, 2010
- Gallagher MD & Chen-Plotkin AS:Am J Hum Genet, 102:717-730, 2018
- Takayanagi Y, et al:Mol Psychiatry:doi:10.1038/s41380-020-00939-5, 2020
- Sumitomo A, et al:Hum Mol Genet, 27:3165-3176, 2018
- Hui KK, et al:Sci Adv, 5:eaau8237, 2019
- Sharon G, et al:Cell, 177:1600-1618, 2019
- Ballinger MD, et al:Neurobiol Dis, 82:176-184, 2015
- Nie X, et al:Neuron, 99:464-479, 2018
著者プロフィール
友田利文:東京大学大学院医学研究科卒業.京都大学メディカルイノベーションセンターを経て2016年よりトロント大学薬物依存精神疾患研究センターにて精神疾患の病態生理の研究に従事.精神神経機能障害に共通する認知機能・情動制御などの高次機能の異常を理解するうえでの共通原理を探し,分子・細胞・回路・行動レベルで理解することをめざす.