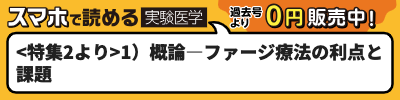概論
生存の基盤となる本能行動とその神経制御
Neural circuits underlying survival
岡 勇輝
Yuki Oka:California Institute of Technology /Division of Biology and
Biological Engineering(カリフォルニア工科大学生物・生物工学科)
本能行動は,個体の生存や種の繁栄に必須の生物機能である.本特集では特に生体の体内環境を保つ恒常性維持を担う本能行動と,その神経・分子基盤を議論したい.栄養や水分の恒常性,体温調節,睡眠・冬眠などの幅広い生物機能が制御されるしくみに着目し,これまで解明されたメカニズムを概説する.さらにその分野のさらなる発展をめざすうえでのボトルネックを提示し,可能な解決案を示したい.恒常性機能の異常は,肥満や不眠症などさまざまな疾患と直結している.それらの原因となりうる恒常性の神経基盤を明らかにする研究の最前線と展望も議論したい.
はじめに―本能行動とは? その種類と生物学的意義
学習行動としばしば対比される本能行動は,個々の種が生まれながらに習得している生得的な欲求とそれに伴う行動を指す.近年,神経操作やイメージング技術の普及により本能行動の脳研究は大きく発展した.しかし,その神経基盤の本質的理解のためには,本能行動の生理的意義,種類,またそもそも本能行動とは何なのかを考えることが大切である.
機能的な観点から,本能行動はおおまかに種の保存と個体の生存という2種類に大別できる.生殖欲求や社会的行動は自分の遺伝子を残し,種として繁栄するための本能行動である(概念図).一方,栄養摂取欲求や睡眠などは生物個体の体内環境の恒常性(ホメオスタシス)を維持するための行動といえるだろう.これらの2種類の行動は完全に分離できるものではないが,特に後者の恒常性維持は生存のために必須の本能行動である.現在社会でも大きな問題になっているように,恒常性破綻は過・拒食症や睡眠障害,高齢者の脱水などさまざまな疾患につながるため,基盤となる生理的メカニズムの解明は急務である.本特集では,近年めざましい発展を見せる恒常性維持を司る本能行動研究に焦点を絞り,最新の神経学的知見と将来展望を紹介する.

1新技術で切り開く本能行動の脳機能解析
われわれ人間を含む多くの種で共通の恒常性維持機構は,19世紀前半から積極的に研究されてきた.現在の恒常性研究の基礎となる概念は1920〜30年代にWalter B. Canonによって提唱されたフィードバック仮説である1).これは,体内の恒常性が崩れると(例えばエネルギー不足),脳が元の体内状態に戻そうとする働きを指す.この作用基盤を解明する従来の研究手法は,主にホルモン分泌の測定などの生化学手法,それら生理物質を受容する組織学を用いた脳部位の探索であった.しかし,1つの恒常性には複雑なホルモンや脳部位がかかわっており,実際にどの分子や神経回路が恒常性維持の行動を制御しているのかは明らかになっていなかった.そのようななか,近年のモデル生物における遺伝学やオプトジェネティクス(光遺伝学),ケモジェネティクス(薬理遺伝学)といった神経活性制御技術の発展により,本能行動と神経活動との相関が行動下の動物の脳内で確かめられるようになった2).これらの技術革新により,以前提唱されていた脳部位が実際に恒常性維持にかかわるのか,そしてその脳部位内のどの神経群が行動を支配しているのかが次々と明らかにされている.
また,カルシウムイメージングを代表とする神経細胞種レベルでの活動測定法により,恒常性を制御する神経群生体内動態がわかってきた3).これらの研究による予想外の発見の1つは,恒常性にかかわる神経群が,体内環境変化によるフィードバックに加えて,末梢の感覚刺激によっても即時的な調節を受けていることである.特に,栄養分の恒常性維持を司る中枢神経群は,飲水・塩分の摂取や摂食行動に伴う味覚,咽頭,腸管刺激により栄養吸収前に強く抑制されることがわかった4).このような体内変化を予測するような“フィードフォワード”制御も近年の恒常性維持機構における新たな発見である.
このように,本能行動の研究は技術革新とともに進展してきた.現在,神経活動を操作もしくは可視化する技術が普及したことで,ある脳領域の特定の神経群と本能行動との機能解析が生体内で行えるようになった.今後,複数の脳内の異なる神経回路がどのように協調するのかを解析できる技術が導入されれば,本能行動の神経基盤の理解がさらに前進するであろう.
2脳神経レベルでの恒常性制御
恒常性維持の第一歩は,脳が体の状態変化を感知することからはじまる.この体内知覚は“Interoception”とよばれ,末梢感覚系のような“Exteroception”と区別される.脳が血中環境や自律神経活動の変化を感知すると,脳内の“感覚神経”の下流にある神経回路を活性化し,大脳皮質や前脳前皮質などの情報処理を経て特定の本能行動が誘導される.生体の生存のためには,さまざまな要素の恒常性維持が必要なため,その基盤となる本能行動も多岐にわたり,それぞれの行動が脳内で特定の脳回路を介して制御されている(図).ここでは,個々の恒常性因子と最近明らかになった詳細な脳神経制御メカニズムを概説する.

❶ 水分・エネルギー恒常性
栄養分(水,塩分,およびエネルギー)の恒常性は生物の活動に必要不可欠である.では,どのように脳は食行動や飲水・塩摂取行動を制御しているのだろうか? これまでの研究により,脳内でどの栄養素を,いつ,そしてどれくらい摂取するかを決定する神経基盤が明らかになってきた5).例えば,体内の脱水は前脳に存在する感覚器官で感知され,特定の神経を介して飲水行動が誘導される.また,この過程にかかわるチャネルやトランスポーター分子も同定されつつあり,神経,分子レベルでの体液恒常性解析が大きく進展した(松田・野田の稿).一方,エネルギー恒常性は視床下部弓状核にあるペプチド性抑制性神経により支配される.これらの神経は主に血中ホルモン変化により活性化され,味覚や腸内感覚によるエネルギー感知によって制御される(戸田の稿).興味深いことに,これらの摂食誘導神経は単に摂食を引き起こすだけでなく,食べものにかかわる感覚シグナルの修飾も行うことがわかってきた.例えば,空腹時になぜ食べものの味やにおいがよりおいしく感じるか,などの恒常性にかかわる情動の変化に関する神経回路の解明も進んでいる(堀尾の稿,中島の稿).
❷ 体温恒常性
適切な体温の維持も重要な脳機能である.恒温動物と変温動物の間では異なるメカニズムで体温恒常性が保たれている6).ヒトやマウスのような恒温動物では,皮膚の感覚神経からの脳への入力により視索前野を視床下部の神経群が活性化し,自律神経を介して脂肪細胞や筋肉からの熱生産を促す(片岡・中村の稿).一方,昆虫のような変温動物は環境の温度を感知し,積極的に最適温度環境に移動することにより体温恒常性を保持する.特にショウジョウバエでの遺伝学を用いた実験により,環境の温度受容体とそれに伴う行動の変化が明らかにされている(水藤らの稿).
❸ 睡眠恒常性
おそらくわれわれの最も身近な恒常性の1つは睡眠であろう.睡眠が足りなくなるとそれを補う恒常性維持機構が働き,眠気がおそってくる.神経回路の操作技術により,視床下部や後脳を含めたいくつもの神経群が異なる睡眠サイクル(レム・ノンレム睡眠)を制御することがわかってきた7).これらの研究をとおして,なぜ生物は睡眠が必要なのか,睡眠欲求を生み出す因子は何なのか,といった根本的な問題へのとり組みが進んでいる(北園らの稿).一方,睡眠と関連する冬眠についても近年神経回路レベルでの研究がなされている.冬眠は単純な長い睡眠ではなく,代謝や体温維持とも大きなかかわりがあることが知られている.複数の恒常性因子が連携し,ダイナミックな覚醒・冬眠状態を生み出すメカニズムの解明が待たれる(砂川の稿).
3全脳,さらには個体レベルでの解析に向けて
最近の10年で,恒常性の神経科学は大きく進歩した.この先,恒常性維持機構のより深い理解のためには2つの大きなチャレンジを乗り越える必要があると筆者は考えている.第一に,脳全体としての神経ネットワークの解明である.神経細胞種レベルでの解析が可能となった現在,1種類の恒常性維持に複数の神経回路網がかかわっていることがわかってきた.例えば,オプトジェネティクスなどの機能獲得実験により,飲水や摂食行動は少なくとも3つ以上の異なる脳部位と神経細胞群がかかわることがわかっている.しかし,複数の神経回路が1つの恒常性機能を制御するしくみの全貌は明らかになっていない.特に,最近の神経科学研究は,新たな神経群を同定し機能獲得実験により行動との機能相関を示すといった単調なものになりがちである.このような状況を打開し,新たなブレークスルーを生み出すためには,表面に現れる本能行動に加え,同時に内分泌系や自律神経系といった恒常性維持に必須な全身機能を含めた包括的な解析が必須となるだろう.一方で,冬眠に代表されるように,それぞれの恒常性因子は必ずしも独立に制御されているわけではない.一例として,社会行動と摂食意欲は密接な関係があることが知られており,脳内の神経回路でも相互制御が働いている可能性が大いに示唆される.今後,個々の本能行動の基盤となる全脳ネットワークを明らかにすることで,異なる種類の恒常性がどの程度重複した神経回路により制御されているかの理解が深まるであろう.
もう1つの大きな課題は,個体レベルでの恒常性制御機構の解析である.神経操作技術の進歩により脳内の機能解析は進んだが,実際の恒常性や行動制御では脳は一要素に過ぎない.例えば,脱水状態では,脳がホルモンと自律神経を介して体内の水分保持を促す.と同時に,飲水行動が誘引される.また,われわれが報告したように,水を飲んだ刺激が咽頭部と腸管部の感覚受容器により脳に伝達され,口渇の抑制が起こる.つまり,1つの恒常性保持に,体内知覚,末梢感覚,内分泌系,そして自律神経系のすべてが複雑にかかわっている.このように本能行動研究は,複合領域を解析するためにまさに最適の分野であり,脳神経とその他の制御系が個体全体として恒常性を維持する機構の解明は今後の大きな課題といえる.また,恒常性は一般的に多くの種に普遍的なメカニズムであるが,生育環境によって飲水,摂食,体温,睡眠のストラテジーも大きく異なる.もし個体レベルでの恒常性維持機構が明らかとなれば,その神経回路が環境に適応した過程を進化的に解析するプラットホームにもなると思われる.
おわりに
摂食,睡眠障害をはじめとする恒常性関連の疾病はわれわれの健康と密接な関連がある.本特集ではこれらの恒常性が維持される神経科学的しくみや展望を紹介した.本能行動は種や個体保存のための行動であるが,その定義はじつは奥が深い.例えばわれわれは喉が渇いたら水を飲む.この飲水が表層部分での行動であるが,本当に飲水は本能行動とよべるだろうか? 飲水でなくとも果実の摂取でも水分補給はできるはずである.しかし,われわれはウォーターボトルから水を飲めば効率的に水分補給できることを経験的に知っている.つまり,本能は“水分欲求”であり,飲水はそれを満たすための学習行動と捉えることができる.このような考え方をすると,本能行動と学習行動の境界はそれほど明瞭ではなく,じつは本能行動も新たに“学習”することが可能なのかもしれない.水分やエネルギー欲求と異なり,睡眠欲求の本質はいまだに明らかになっていない.しかし,もし近い将来その本質が同定され,人工的に“睡眠欲求因子”を満たすことができれば,睡眠も他の行動に置き換えられるような未来が来ることも想像できる.恒常性は古典的研究分野と言われ,筆者が研究をはじめた7〜8年前には,恒常性の脳科学の大部分はすでに解明されたと考えられていた.しかし,その後も次々と予想外の新発見があり,非常にエキサイティングで活発な研究分野となっている.実際,米国国立衛生研究所(NIH)でもInteroceptionという分野が認知され,強くサポートする動きも出ている.本特集を通して,分子から神経細胞,全身ネットワークまで,恒常性維持という生物の最も根本的な欲求行動の理解と魅力を伝えられれば幸いである.
文献
- Walter C:Nature, 133:82-82, doi:10.1038/133082a0(1934)
- Aston-Jones G & Deisseroth K:Brain Res, 1511:1-5, doi:10.1016/j.brainres.2013.01.026(2013)
- Resendez SL & Stuber GD:Neuropsychopharmacology, 40:238-239, doi:10.1038/npp.2014.206(2015)
- Augustine V, et al:Cell, 180:25-32, doi:10.1016/j.cell.2019.11.040(2020)
- Andermann ML & Lowell BB:Neuron, 95:757-778, doi:10.1016/j.neuron.2017.06.014(2017)
- Tansey EA & Johnson CD:Adv Physiol Educ, 39:139-148, doi:10.1152/advan.00126.2014(2015)
- Saper CB & Fuller PM:Curr Opin Neurobiol, 44:186-192, doi:10.1016/j.conb.2017.03.021(2017)
本記事のDOI:10.18958/7175-00001-0000309-00
著者プロフィール
岡 勇輝:2007年,東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了,米国UCサンディエゴ,コロンビア大学での博士研究員を経て’14年,米国カリフォルニア工科大学(Caltech)助教授となり,’15年より研究を開始する.’20年より同大学教授.本能欲求の基礎となる脳神経,末梢神経基盤の解明をめざしている.海外で本能・恒常性研究を目指す学生やポスドクはぜひ連絡をいただきたい.http://www.okalab.caltech.edu/Main.html