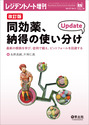レジデントノート 2025年2月号掲載
【解答・解説】発熱と吸気時の肩の痛みで来院した70歳代女性
ある1年目の研修医の診断
肝臓に大きな腫瘍がありそうです.たくさんあるので転移性肝腫瘍でしょうか.これだけあったら発熱していてもよい気がしますし.
肝膿瘍は,その名の通り肝に膿瘍を形成する病態である.日常外来診療ではあまり遭遇しないかもしれない.原因病原体の大半は細菌性であるが,非細菌性(アメーバや寄生虫など)も稀に経験される.感染経路には主に経胆道と経門脈があり,前者は胆嚢炎や胆管炎などに合併,後者は憩室炎や虫垂炎など骨盤内の感染・炎症が先行し,SMV(上腸間膜静脈)や門脈を経由して肝に波及することが知られる.大腸がんが原因で腸内細菌が門脈に移行し,肝膿瘍に至るケースも経験されるため,仮に骨盤内に腹痛などの症状がなかったとしても,肝膿瘍をみた場合にはCTなどによる丁寧な原因検索が望まれる.
症状としては,右季肋部痛や発熱,全身倦怠感などが多い.そのほかにも肝から右横隔膜,胸膜へと炎症が波及することによる胸痛や,さらに横隔神経を刺激することで生じる右肩や頸部の痛みなど,多彩な症状を示すことがある.治療には抗菌薬の全身投与のほか,原因病原体の同定と治療を兼ねた,経皮的ドレナージが行われることも多い.
CTでは,膿瘍腔にあたる部分は濃染を示さない低濃度域として認められるため,一見,頻度の高い肝嚢胞との鑑別が問題になるが(図2),肝膿瘍は単純CTで辺縁がやや不明瞭で(図3),造影効果を有する被膜が認められる点で判別できることもある.また膿瘍が存在する区域では,炎症により動脈血流が増多していることを反映して,動脈相(非提示)での造影効果の増強が認められ,こちらも診断に有用である.MRIでは,特に膿瘍腔が拡散強調像で強い高信号を示すことが特徴的である.
ただし上記のような特徴的な画像は,あくまでもすでに肝膿瘍を疑っている場合に「狙って」撮影された際に認められる所見である.仮に右肩や頸部の痛みを主訴に来院した場合,診療では「胸部」単純CTがオーダーされ,本例のように右胸水,胸膜炎などの所見があると,症状の原因として考えられることがある.しかし胸部CTでは必ず上腹部,横隔膜下の肝臓は撮影範囲に含まれている.肝膿瘍があれば,単純CTでも肝内に淡い低濃度域として認められうることから,右胸水や右肩の痛みを認める患者の読影をする際には特に,必ず撮影範囲の腹部の読影も忘れないようにしたい.画像に映っているものすべてを読影する,というのはどんな画像検査であっても必要なことではあるが,いま再認識しておきたい.
- 画像はクリック/タップで拡大します
プロフィール