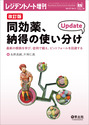レジデントノート 2025年3月号掲載
【解答・解説】発熱が持続するICU入室中の50歳代男性
化膿性脊椎炎
化膿性脊椎炎は,細菌が周囲臓器から直接進展,あるいは血行性に脊椎内に感染することで発症する.さらに血行性感染には脊椎栄養動脈を介する場合とBatson静脈叢を介する場合がある.感染初期には炎症は椎体内に限局しているが,進行すると骨破壊や周囲組織への炎症波及・膿瘍形成をきたす.症状は発熱,感染部位での疼痛であるが,硬膜外膿瘍や,破壊された椎体組織で神経が圧迫されることにより,運動障害,感覚障害ならびに膀胱直腸障害などをきたすことがある.
化膿性脊椎炎において,MRI,非造影CT,単純X線写真の順に診断能が高いと報告されているが1),モダリティの特性と化膿性脊椎炎の病態進行を考慮すると納得のいく結果である.つまり,感染初期の骨髄炎をとらえることができるのはMRIのみであるが,軽微な骨破壊や周囲脂肪組織への炎症波及や腸腰筋膿瘍を伴うとCTでも指摘され,さらに,明らかな椎体破壊が出現すると単純X線写真でも診断されると解釈できる.
松尾らは,非造影CTにおいて,椎体周囲の軟部陰影の変化,椎体周囲の軟部組織の肥厚,椎体骨破壊・骨びらん,腸腰筋の腫脹に着目することで,感度95%,特異度85%で化膿性脊椎炎を診断しえたと報告している2).横断像で脊椎病変を疑ったら,矢状断像,冠状断像を確認することをお勧めする(図3).軽微な椎体終板破壊や膿瘍の広がりを明確にとらえることにより,診断の確信度向上に寄与するためである.同様に圧迫骨折や腫瘍の転移など脊椎疾患を疑った際にも多方向から観察することは大切である.また,過去画像との比較はどのような場合でも有用な情報をもたらす.
本邦の救急医療での画像検査モダリティ選択の現状を鑑みれば,発熱,腰背部痛の原因検索目的で非造影CTを撮影する機会が少なくない.肝,胆,膵,脾…と主な臓器はもちろんのこと,椎体周囲もルーチンの系統的読影手順に加えるようにしたい.
- 画像はクリック/タップで拡大します
引用文献
- Hatzenbuehler J & Pulling TJ:Diagnosis and management of osteomyelitis. Am Fam Physician, 84:1027-1033, 2011(PMID:22046943)
- 松尾大地,他:化膿性脊椎炎の診断における単純CTの有用性.整形外科と災害外科,72:829-832,2023
プロフィール