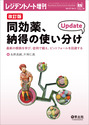レジデントノート 2025年4月号掲載
【解答・解説】発熱が続く70歳代男性
ある1年目の研修医の診断
症状からは尿路感染症かなと思ったんですけど,尿所見はきれいなんですよね.CTでも腎には異常がなさそうですし.でも頻度からやっぱり尿路感染症を疑いたいです.
腸腰筋膿瘍とは,大腰筋と腸骨筋によって構成される腸腰筋内に膿瘍が形成される病態である.起炎菌として黄色ブドウ球菌が最も多く,糖尿病患者や免疫不全状態の患者に好発する傾向がある.血行性に感染が成立する以外にも,周囲の臓器,例えば脊椎や椎間板,消化管,泌尿生殖器系の感染症が直接波及することで発症することもある.
今年の冬もインフルエンザやCOVID-19が流行し,外来に溢れかえる発熱患者を診察する際にはまず検査キット,という診察の流れが本邦では一般的になってきた.しかしそれで陰性,しかも肺炎,尿路感染症も否定的となった場合,発熱の原因として何を想起するだろうか.今回紹介するのは,そんな教訓的な症例である.
身体所見では発熱のほかに,股関節の可動域制限や筋力低下,疼痛を認めることが多い.本例では「歩きにくい」という訴えがあったが,このような訴えがないと,通常の診療をしていて下肢の筋力低下に気づくことは難しいかもしれない.また発熱をきたすさまざまな疾患では,筋肉痛は一般的な症状でもある.治療は,抗菌薬の投与と膿瘍ドレナージが主体となる.可能な限り起炎菌を特定し,適切な抗菌薬を選択することが望まれる.
画像診断においては,一般的にCT検査が用いられ,腸腰筋内に内部不均一な低吸収域として膿瘍が描出される(図2▶).造影CT画像では,膿瘍壁に造影効果を認め,周囲の脂肪組織の炎症性変化を伴うこともある.単純CTでも腸腰筋の左右差に気づくことができれば診断に近づきやすいだろう(図3).いずれにせよ,腸腰筋にも注意を払う癖を日頃からつけておくことが重要である.ただここで注意が必要なのは,脳出血や脳梗塞の既往による片麻痺や下肢のケガ,変形性胸椎・腰椎症などによって片側の腸腰筋の萎縮が認められることがある(本例でも右腸腰筋は萎縮している,図3▶)ため,腸腰筋に左右差が認められたとしても,熱源として決めるには総合的な判断が必要になる.ちなみに,本例は椎間板炎から膿瘍が連続していた(図4).
発熱を主訴とする患者は非常に高頻度に遭遇する.その原因検索にしばしば画像診断は有用であるが,あくまでも診断学のなかの1つのツールでしかないことを忘れてはならない.画像のほか,病歴や身体診察,血液検査などをバランスよく活用し,患者の訴えや病態の本質に迫ってほしい.
- 画像はクリック/タップで拡大します
プロフィール