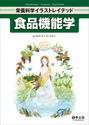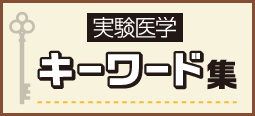概論
かゆみ研究の現在地
伝達経路を分類,そしてかゆみを引き起こす疾患の治療へ
Current knowledge in research on itch: the classification of transmission pathways and the treatment for pruritic
diseases
入江浩之,中嶋千紗,椛島健治
Hiroyuki Irie/Chisa Nakashima/Kenji Kabashima:Department of Dermatology, Graduate School of Medicine, Kyoto University(京都大学大学院医学研究科皮膚科学講座)
かゆみは,本来皮膚に付着した虫などの外敵や異物を除去するために行動を促す生理的感覚で,生体防御機構の一つである.近年,種々のかゆみメディエーターの発見やかゆみを伝達する特異的な神経の同定,そしてかゆみ知覚に関する知見の積み重ねにより,かゆみの発生・伝達・認識のすべての方面からそのメカニズムの理解が進んでいる.またアトピー性皮膚炎を中心に,かゆみを引き起こす疾患・病態ごとのメカニズムも徐々に明らかになりつつあり,ここ数年で新薬も複数開発されたため,今後これらの疾患の治療戦略が変わってくるだろう.かゆみとは何か,現在までに明らかになっている全体像を理解することは次なる病態解明,そして新規創薬の糸口となるであろう.
はじめに

かゆみは本来皮膚に付着した虫(ダニや
かゆみを起こす疾患として,皮膚そのものに異常のあるもの(ドライスキン,湿疹,アトピー性皮膚炎,蕁麻疹,皮膚真菌感染症など)と皮膚に異常を認めずに全身性の疾患によるもの(腎不全,慢性肝疾患,糖尿病,悪性腫瘍や神経・精神疾患など)に分けられる.かゆみの主因は疾患ごとに異なるが,知覚するまでの経路はおおむね同様である.すなわち,かゆみ信号を引き起こす「かゆみメディエーター(
しかしかゆみを引き起こす病態やメカニズムは,実のところかなり複雑である.近年,さまざまなアプローチを用いることでかゆみのメカニズムの詳細が徐々に明らかにされている.本特集ではかゆみの現場である皮膚や末梢神経系から,かゆみを伝達・知覚する中枢神経系にいたる経路の各所で明らかにされているかゆみのメカニズムを,基礎・臨床の側面から最新の知見を含めて解説し,今後の治療展開についても論じる.本特集がかゆみを包括的に理解する一助となれば幸いである.
1かゆみの定義
かゆみ(そう
皮膚の炎症や乾燥に伴い,皮膚からはさまざまなかゆみメディエーターが放出される1).代表的なかゆみメディエーターとしては,肥満細胞などが脱顆粒することで放出されるヒスタミン,トリプターゼ,サブスタンスPなどがあげられる.また近年,表皮角化細胞が産生するthymic stromal lymphopoietin(TSLP)や皮膚に浸潤したTh2細胞が主に産生するTh2型サイトカインとしてのインターロイキン(IL-)4,IL-13,IL-31が炎症のみならず神経に直接作用してかゆみを誘発することが報告されている.これらかゆみメディエーターについて,最近の知見も含めて冨永・髙森の稿にてまとめる.
2かゆみの伝達経路
かゆみの伝達経路としては,主に皮膚における末梢神経(一次感覚神経)が刺激され,脊髄後角を通り,脊髄視床路を介し脳へと伝達される経路が知られている(概念図).
❶ 一次感覚神経
末梢の一次感覚神経は
しかし,2000年代以降,痛みとは独立したかゆみ特異的神経の存在が次々に報告された.さらに近年,一細胞遺伝子発現解析により一次感覚神経の詳細なサブセット分類が進んでいる.Usoskinらは,マウスの一次感覚神経は髄鞘に関連するニューロフィラメント(neurofilament)遺伝子の発現を特徴とするNF神経,ペプチド作動性(peptidergic)神経のPEP神経(PEP1,PEP2),非ペプチド作動性(non-peptidergic)神経のNP神経(NP1,NP2,NP3),そして毛包周囲の低閾値機械受容器(low threshold mechanoreceptor)のTH神経に分類できると報告した2).これらのうちPEP1,NP1,NP2,NP3,THが無髄神経で従来のC線維に相当する.かゆみにかかわる神経としては特にNP神経が重要と考えられ,すべてのNP神経にはIL-4/13受容体が,また,NP1にはIL-31受容体が,さらにNP2とNP3にはヒスタミン受容体が発現している.またNP1からNP3のそれぞれに特徴的なかゆみメディエーター受容体の発現パターンを有することから,それぞれの末梢神経サブセットとかゆみとの関係が明らかになりつつある(岡田の稿).
❷ 脊髄後角から脳・中枢
さらに上流に目を向けると,かゆみメディエーターによる一次感覚神経を介したかゆみ刺激は,脊髄後角に入力され,脊髄視床路を通って脳へと伝達される.2007年には,脊髄において,かゆみ刺激のみを伝達する特異な経路が報告された.かゆみを伝達する一次感覚神経から,脊髄後角で脳性ナトリウム利尿ペプチド(Nppb)が放出されるとその受容体である心房性ナトリウム利尿ペプチド受容体(NPRA)を発現する脊髄後角の神経に伝達される.さらにその神経から,ガストリン放出ペプチド(gastrin-releasing peptide,GRP)が放出され,その受容体GRPR(GRP receptor)を発現する脊髄後角神経に作用するというかゆみ情報を選択的に伝達するというものである3)4).そして,脳へと伝達されるかゆみ情報は視床のみならず,橋結合腕傍核への経路なども報告されている5).
さらに,かゆみ刺激を伝達する経路以外に,かゆみの抑制経路も徐々に解明されつつある.例えば,脊髄後角内には,かゆみシグナルを特異的に抑制する抑制性介在神経としてBhlhb5(basic helix-loop-helix 5)神経があることが報告された6).このように,脊髄から脳にかけた中枢性のかゆみ伝達経路においても多くの知見が蓄積されており,穐山の稿にて詳細を解説する.
また,非常に興味深いことに,脊髄内グリア細胞も慢性的なかゆみに重要な役割をもっている.例えば,アトピー性皮膚炎モデルマウスであるNC/Ngaマウスや接触皮膚炎モデルマウスでは,脊髄後角でアストロサイトの活性化がSTAT3依存的に起こる7).この活性化アストロサイトではリポカリン2の発現が増強し,かゆみ増強因子として働くと考えられている.またミクログリアも慢性的なかゆみに関与する可能性が示唆されており,脊髄後角内におけるかゆみの制御機構が明らかとなりつつある(津田の稿).
3かゆみの分類

ここまで,かゆみを伝達する末梢・脊髄経路について記載した.かゆみメディエーターが末梢・脊髄にかゆみを伝達する経路は,ヒスタミン依存性とヒスタミン非依存性経路の大きく 2種類に分類される(図)1).ヒスタミン非依存性経路の代表的なかゆみメディエーターとして,IL-31やTSLP,Cowhage(八升豆の棘)などがあげられる.
また別の視点では,かゆみは末梢性のかゆみと中枢性のかゆみに大別される(図).末梢性のかゆみとは,前述のようなさまざまなかゆみを引き起こすメディエーターにより皮膚(末梢)-脊髄経路を介して伝達・知覚されるかゆみである.一方中枢性のかゆみとは,かゆみメディエーターが直接中枢神経系に作用して生じるかゆみである.中枢性のかゆみに関連する例としてμオピオイド系とκオピオイド系があげられる.μオピオイド系がκオピオイド系より優位であれば,かゆみが誘発され,逆にκオピオイド系が優位であれば,かゆみが抑制される.
4かゆみを起こす疾患
❶ 全身性の疾患に伴うかゆみ
ドライスキン,湿疹,アトピー性皮膚炎,蕁麻疹,皮膚真菌感染症など多くの皮膚の異常によりかゆみは誘発される.しかし,皮膚の異常によるかゆみ以外に,皮膚以外の基礎疾患によりかゆみが誘発されることもしばしば認められ,特に「皮膚病変が認められないにもかかわらずかゆみを生じる疾患」は皮膚そう痒症と定義される.原因別におおまかに分けると,①全身性(腎不全,慢性肝疾患,糖尿病,悪性腫瘍など)②神経障害性(神経障害,多発性硬化症などの神経原性疾患)③精神障害性・心因性(精神疾患,ストレスなど)④薬剤性(モルヒネや造影剤など)に分けられる(図).
腎不全,腎透析,胆汁うっ滞性黄疸,肝硬変などの全身疾患では抗ヒスタミン剤が奏功しない難治性のかゆみを認める.これらの難治性のかゆみにはオピオイドの関与が指摘され,中枢神経への直接的な作用が考えられている.KOR(κオピオイド受容体)作動薬であるナルフラフィンは,これらのかゆみにも有効性が認められ臨床応用されている.室田の稿では,皮膚炎以外の皮膚疾患や内臓疾患によるかゆみについてまとめる.
❷ 皮膚そのものの異常に伴うかゆみ:アトピー性皮膚炎を例として
かゆみを主症状とする代表的な慢性皮膚疾患としては,アトピー性皮膚炎が有名である.アトピー性皮膚炎の病態として,免疫応答の破綻,バリア機能の異常,かゆみが大きく関与している8).アトピー性皮膚炎の病態の根底にある免疫応答の破綻が,Th2反応の亢進,活性化である.一方,皮膚バリア機能に重要なフィラグリンの突然変異は,バリア機能の破綻の主な原因であると考えられている.
そして,アトピー性皮膚炎のかゆみの特徴として,激しい強度,かゆみ過敏状態の存在,抗ヒスタミン薬に対する抵抗性,
さらに,アトピー性皮膚炎の新規治療薬としてIL-4/13受容体を標的としたデュピルマブ,IL-31受容体を標的としたネモリズマブといった生物学的製剤や,pan-JAK阻害剤であるデルゴシチニブ外用薬が登場している.これらの新規治療薬はいずれも,既存の治療薬と比べ著明な止痒効果を認める.かゆみを抑える,すなわち掻破行為を抑えることでアトピー性皮膚炎を抑制するという,新たな治療戦略が展開されるだろう(中原・古江の稿).
おわりに
本特集では,さまざまなアプローチにより明らかになりつつあるかゆみのメカニズムについて,メディエーターおよびかゆみ伝達経路(末梢-脊髄中枢経路)を中心に解説した.またアトピー性皮膚炎を中心に,これまで難治と言われてきたかゆみを改善するような新規治療薬の出現により,掻破行為によるバリア機能の破綻を抑えるという画期的な治療戦略が展開されつつある.しかしかゆみのメカニズムにはいまだに多くのブラックボックスが残されており,今後のかゆみ研究の進展で明らかになるとともに治療選択肢も広がることが期待される.病態に即した効果的なかゆみ治療を行うためにも,かゆみのメカニズムを理解することはこれからさらに重要性を増していくであろう.
文献
- Yosipovitch G, et al:J Allergy Clin Immunol, 142:1375-1390, 2018
- Usoskin D, et al:Nat Neurosci, 18:145-153, 2015
- Sun YG & Chen ZF:Nature, 448:700-703, 2007
- Sun YG, et al:Science, 325:1531-1534, 2009
- Akiyama T, et al:J Comp Neurol, 524:244-256, 2016
- Ross SE, et al:Neuron, 65:886-898, 2010
- Shiratori-Hayashi M, et al:Nat Med, 21:927-931, 2015
- Kabashima K:J Dermatol Sci, 70:3-11, 2013
- Cevikbas F, et al:J Allergy Clin Immunol, 133:448-460, 2014
- Oetjen LK, et al:Cell, 171:217-228.e13, 2017
- Wilson SR, et al:Cell, 155:285-295, 2013
著者プロフィール
入江浩之:2012 年九州大学医学部卒業.北野病院(大阪)での初期研修期間を経て,’14 年京 都大学皮膚科入局.京都大学医学部附属病院,大阪赤十字病院で皮膚腫瘍を中心とした皮膚科 全般の臨床に従事した後,’18 年京都大学大学院医学博士課程入学.現在は皮膚末梢神経系と かゆみや免疫の関係をテーマに,新しい切り口を模索しながら日々研究に励んでいる.
中嶋千紗:2005 年大阪市立大学医学部卒業.卒後,京都大学皮膚科に入局し,関連病院で研 修.’14 年京都大学大学院医学研究科 博士課程修了.’14 年4 月より京都大学医学部皮膚科助教 を経て,’17 年から,日本学術振興会特別研究員として,京都大学皮膚科で勤務,現在に至る.
椛島健治:1996 年京都大学医学部卒業.横須賀米海軍病院,京大皮膚科,米国ワシントン大 学レジデント,京大神経細胞薬理学( 成宮周教授),UCSF 免疫学(Dr. Jason Cyster),産業 医大皮膚科(戸倉新樹教授),京大皮膚科(宮地良樹教授)を経て,2015 年より現職.皮膚免 疫の多様性に魅了され,その機序の解明と臨床応用に取り組み中.趣味は面白くないと不評の ブログ更新(http://www.kenjikabashima.com/blog/),ゴルフ,マラソン(2 時間54 分 37 秒@別府大分マラソン2020.2.2).