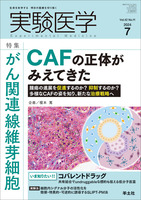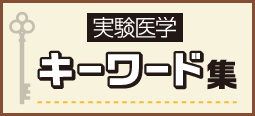- [SHARE]
- ツイート
-
本コーナーでは,実験医学連載「Opinion」からの掲載文をご紹介します.研究者をとりまく環境や社会的な責任が変容しつつある現在,若手研究者が直面するキャリア形成の問題や情報発信のあり方について,現在の研究現場に関わる人々からの生の声をお届けします.(編集部)
第169回 博士学生の研究戦略:サブテーマで専門性を広げよう!
大学院生が広く深い専門性を身につけるには,どのように研究を進めるとよいだろうか? 生命科学の研究対象は分子から個体(群)まで幅広く,研究手法も多岐にわたるため,さまざまな技術や知識は研究者としての強力な武器となる.しかし,1つの研究テーマから習得できるスキルには限界があるため,専門性が狭くなりやすい.そこで本稿では,博士学生がサブテーマをもつことを提案する.
サブテーマの主な恩恵:メインテーマだけでは培えない専門性の拡大
石坂は院生時代のメインテーマで,大気中で失活するマイナーな酵素のX線結晶構造解析を行い,この酵素群に関する専門知識や技術を深めた.しかし,主に無酸素環境で実験する必要があったため,修士課程では常に「所属研究室にある装置の大半に触ったことがない状態では,専門性が狭すぎないか?」と感じていた.そこで,指導教員に相談し,博士課程からはサブテーマとして,大気中で失活しないtRNA結合酵素の熱安定性解析やクライオ電子顕微鏡の単粒子解析にも取り組んだ.その結果,メジャーな装置を扱う技術や幅広い知識が身につき,さまざまなタンパク質の物性や構造を解析できるようになった.さらに,研究室の進捗報告会で実験条件や結果の解釈などの質問をしたり,メインテーマの実験が上手くいかないときに解決策を考えたりできるようになった.また,サブテーマで培ったスキルが評価され,クライオ電子線トモグラフィーを軸とする細胞生物学の研究室にも内定をもらえた.サブテーマでクライオ電子顕微鏡を学んでいなければ,X線構造生物学を専門にしている私は,門前払いだったに違いない.
[オススメ]申請書の書き方を中心に,応募戦略,採択・不採択後の対応などのノウハウを解説.
サブテーマの副次的効果:生産性向上,リスク分散
一方で,「サブテーマはメインテーマの時間を奪うので,メインテーマに集中してほしい」と考える先生方もいらっしゃるだろう.では,研究室の独自のノウハウを伝承したり,人手不足で中止していた研究課題を再開したりする機会として,サブテーマを活用するのはどうだろうか? 石坂が最も強調したいサブテーマの副次的効果は,研究室全体の生産性向上につながることだ.例えば,塩漬けになっていた未発表データを論文発表できたり,メインテーマの空き時間をサブテーマに充てたりできる可能性がある.また,サブテーマで学んだ技術や知識は後輩指導にも役立つため,複数のテーマを進めている学生個人だけでなく,研究室全体がサブテーマの恩恵を享受できる.さらに,他の研究室によってメインテーマの成果が発表されてしまった場合でも,サブテーマがあれば被害を減らせる.特に博士学生の場合,標準年数内に論文発表するためのリスク分散となる.
サブテーマ成功の鍵:メインテーマとのバランス,始めるタイミング
それでは,どうすれば複数のテーマを両立できるだろうか? 例えば,メインテーマとサブテーマの共通点があまりないと,負担が重くなりすぎるため本末転倒だ.特に,メインテーマが挑戦的であればあるほど,サブテーマは確実性が高い方がよい.さらに,メインテーマの研究時間を十分に確保するために,サブテーマの仕事量をメインテーマの2割程度に抑えたり,試料調製とデータ測定を分担する共同研究にしたりするのも一案だ.また,博士課程で他大学に進学した場合などは,メインテーマで論文発表の目途を立ててからサブテーマに取り組むことで,専門性を広げるのが現実的だ.
本稿により,サブテーマの恩恵が専門性の拡大だけでなく,多岐にわたることが伝われば幸いである.サブテーマを始めたいと思った学生さん,研究計画を立て,指導教員に相談しに行きましょう! 誌面の都合で紹介できなかった「サブテーマの他の恩恵」にも気づけるかもしれません.
石坂優人,長瀬茉莉(生化学若い研究者の会 キュベット委員会)
※実験医学2024年7月号より転載
![[Opinion―研究の現場から]](images/opinion_header.png)