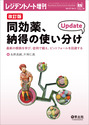特集にあたって
特集にあたって
血糖指示もこわくない!ワンランク上の研修医をめざして
三澤美和
(大阪医科薬科大学病院 総合診療科)
今日もきっと出会う糖尿病の患者さんのために
全国の研修医の皆さん,こんにちは.今年度も終わりが近づき,この1年も成長できる年になったでしょうか.実際医師免許を手にして,現場で患者さんにかかわる今,どんな景色が見えていますか?
2016年に行われた厚生労働省の「国民健康・栄養調査」では,20歳以上の糖尿病の可能性が否定できない人(糖尿病予備軍)と糖尿病が強く疑われる人(糖尿病を有すると考えられる人)の合計は日本人口の約24%,合計2,000万人に上ると考えられています(図)1).
20歳以上の人だけで24%ですから,日本人の4人に1人くらいは糖尿病または予備軍に準じる状況であり,臨床の現場で糖尿病の人に出会わない日はないと考えられます.糖尿病内科以外の研修中も,基礎疾患として糖尿病をもっている人は毎日のように診療していくはずです.糖尿病は本当にコモンな疾患で,私たち医療者ももちろん,身の周りにも糖尿病を抱えながら生活をしている人はたくさんいることを知っていてください.

患者さんが抱える想いを想像しよう
2022年11月,日本糖尿病協会は日本糖尿病学会と連携して「糖尿病」という名称の変更を検討する方針を発表しました2).糖尿病の患者さん約1,000人のアンケートで,8割の人が病名に何らかの抵抗感・不快感をもって変更を希望しているということがわかったことが大きな理由です.「糖尿病」という言葉を使わなくなる日も近いかもしれません.想像してみてください.もしあなた自身が「糖尿病」と診断を受け,食事のこと,運動のこと,生活のこと,通院・薬など今後の人生で「ずっと」続くとしたら?
研修生活では多くの患者さんを診断や治療の観点から診ることと思いますが,大切なことは一人ひとりの患者さんが病気に対する想いや,不安,葛藤といったさまざまな感情を抱え,誰一人同じではない「病いの経験」をしているということです3).これは糖尿病に限らずすべての患者さんにいえることで,皆さんが医師として成長していく過程でいつも心の隅に忘れずにいてほしいと思います.また糖尿病に関する差別や偏見をなくしていこうという活動も活発になってきました.日本糖尿病学会と日本糖尿病協会が共同で出しているポスターや声明もぜひのぞいてみてください4)※.きっと今日から目の前の糖尿病を抱える患者さんにやさしくなれると思います.
血糖指示をスマートに!デキる研修医になるために
本特集では研修医の皆さんが糖尿病の患者さんを診るうえで困るであろうトピックを,病棟での場面と救急での場面を想定して,経験豊富な皆さんの先輩方がこころを込めてまとめました.小児科研修や産婦人科研修中に糖尿病の子どもさんや妊産婦さんを担当することもありますので,これらも内容に盛り込みました.
「先生,“スケール” 入れておいてください」
「先生,低血糖指示入ってないですよ!」
「先生,パニック値です.救急の患者さん,血糖が1,000 mg/dLです!」
そんな連絡がきたときにかっこよく的確な指示をするデキる研修医をめざして,ぜひ先輩が込めたメッセージを読んでほしいと思います.
研修医の皆さんはちょうどコロナ禍のなか,不自由な学生実習を経てさまざまな制約のある研修医生活を送ってらっしゃるはずですが,どんな状況でも医師として働けることに喜びを感じて,そして何より日々の「臨床」を楽しんでくださいね.この特集を通じて皆さんが少しでも成長できることを心から願っています.
引用文献
- 厚生労働省:平成28年 国民健康・栄養調査結果の概要
- 日本糖尿病協会:糖尿病について、ご一緒に考えてみませんか?
- Stewart M, et al:The First Component: Exploring Health, Disease, and the Illness Experience.「Patient-Centered Medicine Transforming the clinical method, 3rd Edition」(Stewart M, et al, eds), pp35-66, CRC Press, 2013
- 日本糖尿病学会,日本糖尿病協会:日本糖尿病学会・日本糖尿病協会 アドボカシー委員会設立~糖尿病であることを隠さずにいられる社会づくりを目指して~.2019
著者プロフィール
三澤美和(Miwa Misa)
大阪医科薬科大学病院 総合診療科
2005年滋賀医科大学卒.家庭医療専門医,糖尿病専門医,総合内科専門医.
医学部5年生のときに家庭医療に出会い,幅広く患者さんの健康問題に対応し,心理社会的問題を含めたまるごと「人」を診られる医師にあこがれ経験を積んできました.尊敬する家庭医の大先輩の言葉を借りて,気持ちはいつも「万年研修医」です.
“医師として学ぶことをやめるときは引退するとき”.
日々楽しく,泣いたり笑ったりしながら患者さんの人生をほんの少しお手伝いできるような診療をこころがけています.