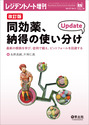特集にあたって
特集にあたって
救急画像のオーダー戦略
金井信恭
(東京北医療センター 救急科)
1救急の現場にて
一般的に救急外来には搬送・独歩などで小児〜高齢者の軽症〜重症,さまざまな傷病・病態の患者が来院します.なかでも超高齢社会を迎えているわが国の救急外来においては多くの高齢患者が受診されます.問診で訴えがわかりづらい,複数の疾患を抱えている,典型的な症状を呈さないなどから検査の閾値が下がる場合も少なくありません.わが国においては医療アクセスがよく,画像検査であるCT・MRIに関して人口100万人あたりの設置台数は,諸国と比べてもダントツに1位です.一方でわが国はこれらのアクセスがきわめてよい環境にあるため,『とりあえず』『何かあってはいけないので』『念のため範囲を広げておこう』などの理由により,オーダーして/されてしまう場合があります.時間的な制約のある救急医療においては診断に迅速にたどり着くために効率的かつ適正な画像診断が要求されます.短時間に多くの情報を得てひとまずの診断や治療方針を導くためには,必然的にCT・MRIのような画像診断に依存せざるをえなくなります1).ここで生じることは前述の過剰あるいは不適切な検査による,被ばくなどの患者側の不利益,診療スキルの低下,見落としなどになります.近年では必要かつ副作用の少ない医療を賢く選びとることにより医療を最適化する-Choosing Wisely-という国際的なキャンペーン活動も広く知られるようになり2),侵襲的な検査を行う前により低侵襲な検査はないか,患者の臨床経過に影響を与えないような検査を選択してはいないだろうか,そもそも本当に今この検査が必要かなど,救急の現場においてオーダーの前にきちんと考える必要があります.
『とりあえず』
言葉のとおりです.『とりあえず』オーダーの前に患者に対する検査から得られる利益が不利益を上回るか,ほかに代替手段はないかなど,今一度検査内容の最適化を考えましょう.
『何かあってはいけないので』
「何か」とは何でしょうか? 「何か」とは医療過誤に対する昨今の社会的背景・風潮もあり,後でみつかった場合に致死的となりうる疾患(killer disease)を指している場合が考えられます.これらをルールアウトするために,『何かあってはいけないので』検査が増えてしまう場合があります.killer diseaseを知り,診療スキルを磨き,検査前確率が低い場合には,「何か」を過剰,侵襲的な検査に頼らないで上手にルールアウトできるとよいですね.
『念のため範囲を広げて』
わかります.私も経験があります.さまざまなプロブレムリストを抱える患者,意識障害・精神疾患・高齢者・認知症などで訴えがはっきりしない場合,転倒外傷や多発転移などで原発巣がわからない場合などに,どうしても画像検査が増えてしまい,結果的にwhole bodyだったという場合も生じます.今本当に救急外来で必要な検査であるかどうかを丁寧に検討し,省略できるあるいは後日でよいなど,立ち止まって考える時間が必要です.複数部位撮影時には診療報酬加算においてCTにもMRIにも点数表で撮影料のところに「一連につき」と記載されてあり3),他部位を複数撮影しても点数は同じとなります.傷病名欄には撮影した部位すべての傷病名が必要になりますので,記載漏れには注意が必要です.
2モダリティ選択と画像オーダー
おのおのの施設により臨床研修医の医療行為の基準は異なりますが,原則として研修医が行うあらゆる医療行為には指導医の許可が必要です.多くは指導医の許可を得たうえで単独で行ってよい医療行為として,単純X線検査,超音波検査など検査結果の判読・判断,CT・MRI・核医学検査などインフォームドコンセントの必要な検査指示があります.日々さまざまな症例に接していますと,現場の研修医から救急疾患に対し画像検査をオーダーするうえでどんなモダリティを選択し,どのように画像オーダーを行えばよいか?という疑問は実に多く聞かれます.そのなかでも今回は「画像診断・読影より前の段階である,どの画像検査を選択・オーダーするか,読影依頼文をどう書くかなど画像検査のファーストタッチの部分も知りたい」といった「オーダーのしかた」をテーマにすることを考え,今回の特集に至りました.どんな症例で,何を想起してどのモダリティを選択し,どうオーダーするか,そのオーダーでどのような画像が撮影されるのか,画像で何を見て何を考えるべきかまでを学べる内容となっており,読影依頼書の文例などオーダーについて具体例をも記載しています.各セクションごとに第一線でバリバリに活躍されているエキスパートに救急画像の最適なモダリティ選択と画像オーダーについて重要なポイントを解説,また教訓を込めてメッセージをいただきました.臨床の傍に本特集が少しでも皆さんの救急現場で役に立つよう祈念しております.
引用文献
- 「画像診断ガイドライン 2021年版 第3版」(日本医学放射線学会/編),金原出版,2021
- 小泉俊三:Choosing Wiselyキャンペーンについて.日本内科学会雑誌,105:2441-2449,2016
- 「診療点数早見表 2024年度版」(医学通信社/編),医学通信社,2024
著者プロフィール
金井信恭(Nobuyasu Kanai)
東京北医療センター 救急科
1995年に東京女子医科大学救命救急センター入局,救急画像診断・IVRに興味をもち,1999年聖マリアンナ医科大学放射線医学教室に入局.画像診断のトレーニングを受け,救急科専門医に加えて放射線診断専門医,IVR指導医の資格を得た.現在東京北医療センター副センター長・救急科科長・臨床研修センター長.
『救急画像診断一例一例の経験を大切に,一度見て学んだことを次につなげて成長していきましょう』