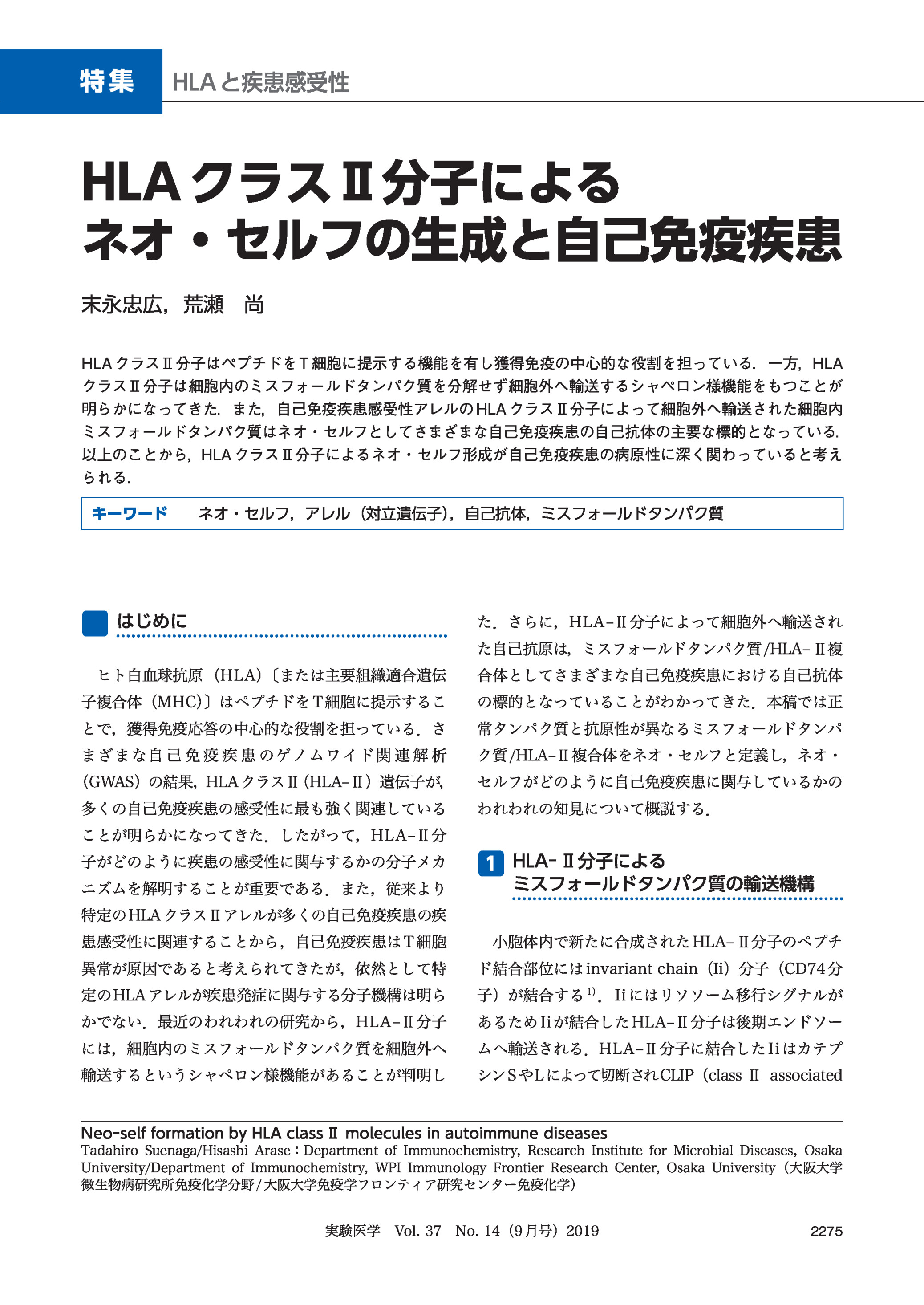はじめに
坂野 仁 今回の対談では「嗅覚研究を通してヒトの意識を考える」というテーマで話を進めたいと思います.ヒトの意識や情動・行動の問題は,われわれをとりまく外的世界,すなわち宇宙や時空,物質の問題とともに,古くから哲学の重要な課題として語られてきました.この3つの柱のうち2つについては,素粒子論物理学や天体物理学によって理論と実験の両面からかなり理解が深まってきたと思います.しかしながら,3つ目のヒトの心や意識という内なる問題,すなわちわれわれは何であるか,という問いについては長いあいだ想像の域を越えることができませんでした.ヒトの心や意識の理解が自然科学からとり残されてきた理由は主に,アプローチのための技術的手段の問題,すなわちそれを自然科学的に扱うための手だてがなかったことにあると思います.もちろん,ヒトの心や意識というものを特別視するある種のタブーがあったことも事実ですし,脳神経科学の目的が精神疾患の理解やその治療に向けられていたことも原因の一つであったように思われます.近年の目ざましい分子生物学の進展によって,これまで生理学と解剖学の世界であった脳神経科学が,分子のことばで記述できるようになり,状況は大きく変わりました.そこで今回は,嗅覚研究に長年携わって来られた森憲作先生とともに,自然科学の立場からヒトの意識や心の理解がどこまで進んだかについて議論してみたいと思います.私は京都大学理学部の生物物理学専攻で志村令郎先生から分子生物学を,また小関治男先生から分子遺伝学の教育を受けた研究者ですが,森先生御自身について少し紹介していただけませんか.
森 憲作 私は今から半世紀前,大阪大学理学部の大学生だった頃,「この世界は何から出来ているのか」を問う物理学を学びました.自分の周りにある宇宙や時空や物質の性質について理路整然と明確に説明する物理学者の考え方が気に入っていたからだと思います.大学院に進学するにあたり,どのような学問分野がいいだろうかと探していたところ,塚原仲晃先生が「この世界を人間はどのように知るのか」を問う脳神経科学の研究室を主宰されているのを知りました.そこで物理学とは異なる視点で研究を進める大阪大学基礎工学部の塚原研究室の修士課程に入学しました.塚原研究室では,スウェーデンのイェーテボリ大学医学部から1年間の留学で来日されていたHans Hultborn先生から電気生理学の基礎を学び,瞳孔の対光反射の神経経路の研究に参加しました.網膜神経節細胞―視蓋前域細胞―Edinger-Westphal核細胞―副交感神経節後線維とつながる瞳孔反射の神経経路を調べていく生理学的研究手法は,物理学研究の手法とそれほど異なりませんでした.しかしながら瞳孔は,睡眠時には小さいけれども驚いたり緊張すると大きくなり,意識や覚醒レベルと連動して常時調節されていることを学んで不思議に思い,当時の物理学では全く説明できなかった意識や情動についてはじめて思いを巡らせました.
坂野 私は1976年「RNasePの変異株を用いたtRNA前駆体のプロセシングの研究」で学位を取得し,カリフォルニア大学サンディエゴ校化学部のJohn Abelson教授のラボに留学しました.日本の外に出てみると,遺伝子クローニングや塩基配列決定法など遺伝子解析の技術が革命的に進歩しつつあり,新しい時代のはじまりを予感しました.それまでウイルスやバクテリアを材料にして進んでいた分子生物学が真核生物の研究へと移り,高等動物の複雑系に対するチャレンジの気運が出てきていたのです.高次システムとしては発生や分化,免疫や神経系がありますが,当時はいまだ脳神経科学を遺伝子レベルで扱うには程遠い状態でした.私はまず免疫系の抗体遺伝子に着目し,限られた種類の抗体遺伝子で無限種類の抗原を排除する「多様性識別」の問題にとり組みました1)〜3).その研究成果で後に利根川先生がノーベル賞を受賞することになるわけですが,私は次に同じような多様性識別の問題を特定の遺伝子に注目して神経系で扱えないかと考えるようになりました.そこで嗅覚受容体遺伝子に着目したわけです.森先生はどのようなきっかけで嗅覚研究に入られたのですか.
森 私は塚原研究室での修士課程を終えて,群馬大学の高木貞敬先生の研究室に助手として赴任しました.高木先生は日本の嗅覚研究のパイオニアでおられたので,嗅覚神経系の生理学的研究を通じて大脳の高次機能に迫りたいと考えました.その当時は,大脳の感覚皮質における感覚情報処理の研究が主流でしたので,「大脳の1次嗅皮質である嗅球は外界の匂い情報をどのように処理するのか」という問いにチャレンジしたいと思い,嗅球の神経回路の生理学的解析に着手しました.
その後,イェール大学のGordon Shepherd教授の研究室に留学し,帰国後,大阪バイオサイエンス研究所,和光の理研,東京大学医学部と場所を変えて嗅球の機能研究を行いましたが,「大脳は匂い情報をどのように処理するのか」という視点はずっと同じでした.ところが2007年の坂野先生の研究室との共同研究4)が基盤となり,大脳の嗅皮質を研究するには「匂い情報をどのように処理するか」だけでなく「匂い情報をどのように行動出力に変換するか」を考える必要があるという,発想の大きな転換が起こりました.この発想転換は大脳全体の働きを考える際にも適用でき,「大脳はどのようにして外界や内界の感覚情報を行動判断へと結びつけるのだろうか」という新しい視点が生まれました.
その後,脳神経科学は大きく発展し,「この世界はどのようなものか」とか「感覚情報は大脳の感覚皮質でどのように処理されるのか」を理解するだけでなく,「大脳は外界や内界の感覚情報をどのように行動判断に変換するのか」や,「人間の精神(意識や情動)はどのように働くのか」を自然科学の言葉で理解することを,私自身もめざすようになりました.
坂野 私は免疫学者であった頃,先にも述べましたように,多様性の識別をテーマに研究を行なっていました.したがって脳神経科学に移った後の最大の興味は,嗅覚系における多様性識別のメカニズム解明でした.免疫系では数百種類の抗体遺伝子の断片が,DNAの体細胞組換えを用いて,さまざまな組合わせ(combinatorial)と接合部の塩基の欠失・付加による多様化(junctional diversification)により108以上の多様な受容体遺伝子をつくり出します1)〜3).一方嗅覚系では,ヒトの場合385種類,マウスでも一千種類程度の受容体遺伝子で,さまざまな匂い分子の組合わせからなる無限種類の匂い情報を識別しています.ところが嗅覚受容体遺伝子にはリンパ細胞でみられたような遺伝子変換や組換えによる多様化はみられなかったのです.それでは「どのようなメカニズムで嗅覚系は多様な匂い情報を識別しているのか」が免疫学から嗅覚研究に移った研究者達の抱いた疑問で,その謎の解明に道を拓いたのが森先生の匂い地図の考え方でした.森先生が立花隆さんとの対談でこのことを語って居られたのを読んで,深い感銘を受けました.これは嗅覚受容体遺伝子の発見される少し前,今から30年以上も昔のことになりますが,森先生がこの匂い地図のアイディアを思い付かれた頃の話をしていただけませんか.
森 「大脳の一次嗅皮質である嗅球には,どのような神経地図,すなわち匂いマップがあるのだろうか?」と考えはじめたのは1987年頃です.当時は,大脳の視皮質や聴皮質,体性感覚皮質には,よく似た感覚入力に応答するニューロンが集合して小さな機能カラムを形成していることや,機能カラムが各感覚皮質に整然と並んで感覚地図を形成していることが解っていました.
嗅球にはこの機能カラムに相当すると思われる糸球体が並んでいて,きっと糸球体を単位とする糸球地図があるだろうと思いました.そこで,個々の糸球体に属する僧帽細胞や房飾細胞が,どのような匂い入力に応答するのかを調べはじめました.坂野先生のご指摘のように,われわれをとりまく世界には無限種類の匂いが存在します.当時,多種多様な匂いのなかからどの匂いを用いて実験すればよいのかたいへん迷いましたが,鼻腔にある嗅細胞を刺激する匂い分子のパネルとして,脂肪酸類,アルデヒド類,アルコール類,およびエステル類の匂い分子群を用いることを決断しました.同じ官能基をもつ匂い分子群は似た匂いの「質感」をもつこと,また同じ官能基をもつ直鎖の匂い分子群のなかでは,匂いの「質」が炭素鎖の長さに対応して徐々に変化することが知られていましたので,これらの分子パネルがきっと「匂い地図解明」のヒントになると思ったわけです.
例えば直鎖脂肪酸類の匂いの質は,酢酸(C2,酢の匂い),プロピオン酸(C3,刺激的な酸っぱい匂い),酪酸(C4,足の悪臭),吉草酸(C5,蒸れた靴下の匂い),カプリル酸(C6,ヤギの体臭),と炭素鎖の長さとともに徐々に変化します.直鎖脂肪酸類はどれも嫌な匂いで,実験の際に辛い思いをしましたが,その後,嗅球の匂い地図のなかの「忌避すべき匂いを担当する背側ドメイン」のアイディアにつながり,この実験をしてよかったと思っています.
これらの分子パネルを用いて嗅球ニューロンの匂い分子に対する応答選択性を調べていくと,「個々の糸球体に属するニューロンは分子構造が類似した一群の匂い分子に特異的に応答すること」がわかり5)〜7),これを「匂い分子受容範囲」とよぶことにしました.また直鎖脂肪酸の匂いに応答する背側ドメイン内では,炭素鎖の短いものは前方に,長いものは後方に配置されていることもわかりました.
これらの匂い分子パネルを用いて個々の糸球体の匂い応答選択性を調べる実験は,1999年頃に私の研究室で内田直滋さんが内因性信号の光学的測定法を用いて行いました8).それ以降,さまざまな構造をした匂い分子に応答する糸球体の空間配置,すなわち匂いマップを実際に目で見て観察することができるようになったのです.
嗅覚研究のこれまで
坂野 森先生の匂い地図や糸球体機能に関する概念を裏付けるべく,匂い情報受容の研究が大きく進んだのは1991年にコロンビア大学のRichard Axel教授とそのグループにいたLinda Buck博士が嗅覚受容体遺伝子を同定したことがきっかけでした9).その後,個々の嗅細胞の発現する嗅覚受容体遺伝子は1種類のみであること(1嗅細胞・1受容体ルール)10)11)や同じ種類の受容体を発現する嗅細胞の軸索は特定の糸球体に収斂すること(1糸球体・1受容体ルール)12)が明らかとなりました.すなわち,嗅覚神経地図は個々の糸球体が特定の嗅覚受容体の種類に対応する,いわば糸球体を画素とするデジタル画面であることが判明しました.免疫系の場合,抗原と抗体の対応は1対1で厳密なone to one ontoの関係になっていますが,嗅覚系の場合は基質と受容体の関係が緩く,類似した匂い分子と受容体どうしが複数対複数の関係で対応します.したがって個々の匂い分子は強弱はあるものの複数種類の糸球体を活性化し,糸球マップというデジタル画面に発火した糸球体の組合わせパターンとして展開されることがわかってきました.すなわち似た匂いでも糸球マップの活性化画像が微妙に異なり,脳がその違いを識別しているというわけです.この匂い入力の位置情報への変換が,一千種類程度の受容体で多様な匂いを判別する鍵となっているのです.ここで匂い地図の考え方が一歩大きく前進したことになりますが,森先生は当時のことをどのように御考えになりますか.
森 この頃に,1嗅細胞・1受容体ルールや1糸球体・1受容体ルールが次々と明らかになり,大脳が多種多様な匂い分子を識別するために用いる神経回路のロジックが判明しはじめて,たいへん興奮したのを覚えています.そして私も,嗅球の匂い地図の全容を生理学的な手法で解明したいと考えていました.
坂野 私達のグループでは,この糸球体マップの形成を支える「1嗅細胞・1受容体」と「1糸球体・1受容体」という2つの基本ルールの分子基盤の解明に挑みました.これらの課題はなかなかの難問で,当時ニューヨークの学会で会ったAxel博士は私に,「Lindaはよく頑張って遺伝子を見つけてくれた.しかし自分は遺伝子を採るのが目的ではなくそれを使って解明したい問いが3つある.まずは2つの基本ルールの分子メカニズムであり,もう一つはそれらを支えるシグナル系と神経活動の解明だ.しかしこれら3つの問題は,遺伝子がクローニングされて10年経った今でも解決されていない」と.特に2つ目の,発現する受容体の種類によって指令的に行われる嗅細胞の軸索投射については,「そのモデルすら思い浮かばない」と云っていました.これは2001年春のBunbury Conferenceでのことでしたが,その後10年をかけてわれわれのグループの若い人たちが頑張って,上記3つの謎の答えをほぼ明らかにしたのです.ちょうどその頃に森先生が和光の理研から東京大学医学部(生理)の教授として移られ,われわれとの共同研究が開始されたのでした.森先生は本郷に場所を変えて,どのような研究をはじめようとされていたのですか?
森 東京大学へ研究場所を移した頃にまずめざしたものは,嗅球の匂い地図の全容をさまざまな研究手法を使って解明することでした.長尾伯先生は組織化学的手法を使い,高橋雄二さんや五十嵐啓さんは光学的測定法を用い,稲木公一郎さんはZif268発現法を用い,匂い分子の分子構造とその匂いで活性化する糸球体の位置との対応関係を詳細に決定し,嗅球の展開図のうえにその結果を記入した「匂い分子構造地図(molecular-feature map)」をつくりました.第二の目標は,嗅球に入った匂い情報が,大脳のどの部位に送られどのようにプロセスされるかを,嗅球の匂い地図の知識を土台として考えることでした.
坂野 私のグループではまず,免疫系と相似性がある1嗅細胞・1受容体ルールの解明にチャレンジしました.当時大学院生だった芹沢尚さんと石井智浩さんが,特定の嗅覚受容体遺伝子にGFPまたはlacZのタグを付けたマウスをつくってかけ合わせ,これらが同時発現することがないことを証明しました10).また,石井智浩さんや坪井昭夫さんらは嗅覚受容体遺伝子の対立形質排除を染色体のRNAマッピング(ISH)法を用いて可視化しました13).受容体の単一発現については,1つの遺伝子の任意な活性化と,機能的受容体の発現によって他の受容体遺伝子の新たな活性化を抑制する「負のフィードバック」の考え方を導入することで見事解決しました11).これは芹沢尚さん,宮道和成さん,中谷洋子さんらの努力によるものです.また,1つの嗅覚受容体遺伝子を活性化するcisに働くエンハンサーの実体は,西住裕文さんのゼブラフィッシュを用いた変異解析で明らかになりました14).
続いてチャレンジしたのが1糸球体・1受容体ルールの解明で,これはまさに難問でした.嗅覚系における軸索投射と回路形成に関して最も注目されたのが,嗅覚受容体によって軸索の投射・収斂が主導的(instructive)に制御されるという特殊性です.当時Axel博士のグループやそこから独立したMombaerts博士のグループは,嗅覚受容体が嗅細胞の軸索末端にも存在することから,「受容体自身が投射先の検出と糸球体分離のための軸索選別に直接かかわるのでは?」と提唱しました.私はこの嗅覚系にのみ通用する「投射先の嗅ぎ分けモデル」に違和感を抱き,もっと一般的なメカニズムがあるのではと考えました.当時Buck博士にこの話をすると,「自分はAxel博士の考えに同調したくはないが,他にどのようなモデルが考えられるのか?」と云っていました.視覚系では神経細胞の位置に対応して投射先が決まります.またSperry博士が提唱した,軸索の先端がターゲットである投射先の目印(cue)を目ざして軸索を伸長しシナプスを形成するという化学親和性モデル15)が一般的に古くから受け入れられていました.実際この「Chemo-affinityモデル」に乗っかったのがAxel博士やMombaerts博士らの「嗅ぎ分け投射モデル」だったのです16).また糸球体の形成に関しては,同じ種類の嗅覚受容体を発現する軸索はその同種親和性によって束になり,異なる受容体をもつ軸索は反発し合って軸索の分別・収斂が起こるとMombaerts博士らは考えました17).この「Self-nonselfモデル」もきわめて解りやすい考え方で今でもこれを信じている人が多くいますが,森先生はこの辺りのことについて当時どのようにお考えでしたか?
森 私の研究室でも吉原良浩先生との共同研究で,嗅上皮の腹側ゾーンにある嗅細胞サブセットの軸索表面に選択的に発現する細胞接着分子OCAMを見出していましたので,嗅細胞での嗅覚受容体の発現とその軸索表面での細胞接着分子の発現が関連するだろうと想像していました.ただ,嗅覚受容体自身が投射先の検出に直接かかわるというアイディアには共感しませんでした.たとえそれが事実であったとしても,それは嗅細胞の軸索投射にだけ成り立つメカニズムであり,大脳全体の神経細胞がどのように軸索でつながって機能するのかを知りたい私にとっては,それほど重要だとは思えなかったのです.
さてOCAMを発現する嗅細胞軸索の投射先の糸球体の空間配置地図を調べることにより,予想もしなかった「嗅上皮の腹側ゾーンに分布する嗅細胞の軸索は嗅球の腹側ドメインへと投射し,背側ゾーンの嗅細胞の軸索は背側ドメインへ投射する」ことが1985年にわかりました18).しかし,見つかったゾーンやドメインの機能を推測するには1嗅細胞・1受容体ルールや1受容体・1糸球体ルールの解明を待たなければなりませんでした.また,OCAMを発現した嗅細胞の嗅上皮での分布と嗅球での投射先にあたる糸球体の分布の相関を調べることにより,「嗅上皮の背外側部に分布する嗅細胞の軸索は嗅球の外側へと投射し,腹内側部に分布する嗅細胞の軸索は嗅球の内側へと投射する」こともわかってきましたが,その機能的な意義を理解するにはさらに多くの時間がかかり,2021年になってようやく推測ができるようになりました19)20).
嗅覚神経地図形成の基本原理
坂野 私は2000年代のはじめ頃,嗅ぎ分けモデルや親和性モデルに違和感を感じていましたが,それらを覆して論文を書くのは簡単なことではありませんでした.まず軸索投射に関しては,修士課程の学生だった今井猛さんが大きな発見をしました.彼は個々の嗅覚受容体がその種類に応じた固有なレベルの基礎活性をもち,それがcAMPというシグナル分子を介して軸索投射分子の転写量を制御していると考えたのです(図1A)21).
嗅覚受容体が生み出すマップ形成のための2種類のシグナル.嗅覚神経地図形成には嗅覚受容体の種類に応じて固有なレベル産生される2つのタイプの受容体活性が関与する.A)一つは受容体の基礎活性で,未成熟嗅細胞においてGsを介して産生される低レベルのcAMPが神経活動を介さずに軸索投射分子の転写を制御している26).B)一方,成熟嗅細胞では,Golfを介して受容体の種類に固有な量産生される高レベルのcAMPが神経活動を発生させ,その発火レベルが軸索選別分子の発現量を制御して,糸球体の選別に寄与している.
当時,匂い情報はGolfというGタンパク質によってcAMPの産生を誘導しそれがCNGというイオンチャネルを開いて神経活動を生み出し,その信号が脳に伝えられることが知られていました.したがってG olfやCNGチャネルをノックアウト(KO)したマウスでは匂いの識別ができなくなるのですが,驚いたことに嗅細胞の投射には影響が出ないのです.そこでその頃は,嗅覚受容体によって生み出されるシグナルが軸索投射に関与するという考えは否定的にみられていたのです.ここで今井さんは,Golfとは別の種類のGタンパク質が軸索投射に関与し,出生前に起こる投射に神経活動が必要ないと仮定すれば,このジレンマは解消すると考えました.事実,Golfの代わりにGsが使われ,CNGチャネルではなくタンパク質リン酸化酵素PKAを介したシグナル経路を用いて,Nrp1やSema3Aなど前後軸に沿った軸索投射分子の転写が制御されていたのです.今井さんはまた,嗅細胞軸索がSperryモデルではなく,ターゲットからのcueに依存しない軸索間の相互作用によって自律的かつ相対的に決まることを見出しました22).
前述したように背腹軸に沿った軸索投射は視覚系の場合と同様に位置情報で制御されており,嗅上皮の背側にある嗅細胞は嗅球の背側に,腹側の細胞は腹側に投射することが判明しました23).またこの背腹軸に沿った軸索投射は,背側から腹側へと嗅球構造が拡大するのに合わせて順に起こり,背側の軸索が後で投射してくる腹側の軸索を反発性因子Sema3Fによって押し下げて相対的な投射位置が決まるのです.この研究は竹内春樹さんをはじめとする井ノ口霞さんや青木真理さんらの大学院生チームによってまとめられ,アスコーナの学会に来ていたCellの編集長の目にとまって世に知られることとなりました24).
このように,最初に形成される嗅覚神経地図は視覚系などと同様,軸索誘導因子の濃度勾配を用いた連続マップであるわけですが,生後,嗅覚神経地図は約一千個の糸球体を画素とする不連続マップになるのです.この連続マップから不連続マップへの変換は出生前後に神経活動に依存して起こります(図1B).これを支える嗅細胞の軸索末端と糸球体構造の仕分けに関しては,芹沢尚さんを中心に宮道和成さんや竹内春樹さんらが,嗅覚受容体の種類に固有なレベル産生される接着分子と反発分子を同定し,香港の学会に来ていたBuck博士がCellの編集長に芹沢さんを紹介してすんなり論文が受理されました25).しかし私の頭のなかに残っていたのはAxel博士の言っていた「神経活動とシグナルの問題」です.すなわち同じ嗅覚受容体のidentityとcAMPを基礎に,どうやって同じ嗅細胞のなかで,神経活動に非依存的な軸索投射と依存的な糸球体分離という2つの制御が行えるのかが大きな謎でした.しかしこれについては今井猛さんが,軸索の投射制御はGsを用いて出生前の未分化嗅細胞で,また糸球体分離の制御はGolfを用いて出生前後の成熟嗅細胞で,受容体分子の基礎活性と神経活動をそれぞれ用いて独立に制御されていることをGタンパク質のKOと受容体の再構築系を使って示しました(図1)26).
A)嗅覚受容体などGタンパク共役型受容体(GPCR)は活性型と不活性型の2つの構造をとり,基質のない状態では,熱運動に伴う分子ゆらぎによりこれらの状態を行き来する.この際,一定の確率でGタンパク質が結合して基礎活性が生じ受容体の種類に固有なレベルのcAMPが産生される.B)このcAMPによってタンパク質リン酸化酵素PKAが活性化され,Nrp1やSema3Aなど,前後軸の投射を制御する軸索誘導分子の転写レベルが,嗅覚受容体の種類特異的に決められる26).
最後に残った課題は,嗅覚受容体のidentityを表現する受容体の基礎活性の実態です.以前から自然発火による基礎活性は広く知られていましたが,神経活動を伴わない受容体の基礎活性が何であるかは不明でした.今井猛さんの見つけた前後軸の投射を制御する嗅覚受容体の基礎活性は,CNGチャネルを必要としないもので神経活動を含みません.これが何だろうと思案していたときに発表されたのがスタンフォード大学のグループによるGタンパク質共役型受容体(GPCR)の立体構造解明の論文でした27).私は,隣の研究室の濡木理先生と大学院生だった加藤英明さんに来て貰って,GPCRの構造と基礎活性について相談しました.一般に,活性型と非活性型の2つの構造は,それぞれアゴニストとアンタゴニストによって安定化され,受容体活性が切り替わります.私はこの論文を見て,出生前は匂い基質が不在なので嗅覚受容体は熱運動によって2つの構造を自由に行き来する,すなわちこの分子ゆらぎの合間をぬって出入りするGタンパク質がノイズレベルのcAMPを産生し,そのゆらぎの平均値が嗅覚受容体のidentityを表現していると考えたのです(図2).このアイディアはGPCRの基礎活性の変異体を用いて証明され,大学院生の中嶋藍さんや竹内春樹さんらの論文としてCell誌に発表されました27).この時レフェリーの一人は,「この論文は長年,坂野研究室から発表された一連の仕事の総決算であり,仕上げの成果(cap stone)だ」と評してくれました.また発表当日,ハーバード大学のJeff Macklis教授からメールが届き,「生命現象は一見confusingでdisorderedなように見える.しかし科学者がそれに或るものさし(ruler)を当てるとマトリクス変換のように姿を変えその本質をあらわす.これこそが科学することの美(beauty)であり,それを成しとげることが科学者の勝利(triumph)だ.おめでとう!」と.
──第2回「先天的な出力判断」へ続きます
文献
1) Sakano H, et al:Nature, 280:288-294, doi:10.1038/ 280288a0(1979)
2) Sakano H, et al:Nature, 286:676-683, doi:10.1038/ 286676a0(1980)
3) Sakano H, et al:Nature, 290:562-565, doi:10.1038/ 290562a0(1981)
4) Kobayakawa K, et al:Nature, 450:503-508, doi:10.1038/nature06281(2007)
5) Imamura K, et al:J Neurophysiol, 68:1986-2002, doi:10.1152/jn.1992.68.6.1986(1992)
6) Yokoi M, et al:Proc Natl Acad Sci U S A, 92:3371-3375, doi:10.1073/pnas.92.8.3371(1995)
7) Mori K, et al:Science, 286:711-715, doi:10.1126/science.286.5440.711(1999)
8) Uchida N, et al:Nat Neurosci, 3:1035-1043, doi:10.1038/ 79857(2000)
9) Buck L & Axel R:Cell, 65:175-187, doi:10.1016/0092-8674(91)90418-x(1991)
10) Serizawa S, et al:Nat Neurosci, 3:687-693, doi:10.1038/ 76641(2000)
11) Serizawa S, et al:Science, 302:2088-2094, doi:10.1126/science.1089122(2003)
12) Mombaerts P, et al:Cell, 87:675-686, doi:10.1016/s0092-8674(00)81387-2(1996)
13) Ishii T, et al:Genes Cells, 6:71-78, doi:10.1046/j.1365-2443.2001.00398.x(2001)
14) Nishizumi H, et al:Proc Natl Acad Sci U S A, 104:20067-20072, doi:10.1073/pnas.0706544105(2007)
15) Sperry RW:Proc Natl Acad Sci U S A, 50:703-710, doi:10.1073/pnas.50.4.703(1963)
16) Mombaerts P:Annu Rev Cell Dev Biol, 22:713-737, doi:10.1146/annurev.cellbio.21.012804.093915(2006)
17) Feinstein P & Mombaerts P:Cell, 117:817-831, doi:10.1016/j.cell.2004.05.011(2004)
18) Mori K, et al:J Comp Neurol, 242:214-229, doi:10.1002/cne.902420205(1985)
19) Mori K & Sakano H:Front Neural Circuits, 16:861800, doi:10.3389/fncir.2022.861800(2022)
20) Mori K & Sakano H:Front Behav Neurosci, 16:943647, doi:10.3389/fnbeh.2022.943647(2022)
21) Imai T, et al:Science, 314:657-661, doi:10.1126/science.1131794(2006)
22) Imai T, et al:Science, 325:585-590, doi:10.1126/science.1173596(2009)
23) Miyamichi K, et al:J Neurosci, 25:3586-3592, doi:10.1523/JNEUROSCI.0324-05.2005(2005)
24) Takeuchi H, et al:Cell, 141:1056-1067, doi:10.1016/j.cell.2010.04.041(2010)
25) Serizawa S, et al:Cell, 127:1057-1069, doi:10.1016/j.cell.2006.10.031(2006)
26) Nakashima A, et al:Cell, 154:1314-1325, doi:10.1016/j.cell.2013.08.033(2013)
27) Rasmussen SG, et al:Nature, 477:549-555, doi:10.1038/nature10361(2011)
森 憲作:1974年,大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程修了(’78年工学博士).群馬大学医学部助手・講師,イエール大学医学部Research Associate,を経て’87年,大阪バイオサイエンス研究所副部長.’95年,理化学研究所ニューロン機能研究グループグループディレクター.2000年から東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻教授.’15年,東京大学名誉教授.’15年より理化学研究所脳神経科学センター客員主管研究員(現在に至る).
坂野 仁:1976年,京都大学大学院理学研究科生物物理学専攻博士課程修了(理学博士),カリフォルニア大学サンディエゴ校化学部博士研究員.’78年,スイスバーゼル免疫学研究所研究員,’81年,カリフォルニア大学バークレー校微生物・免疫学部Assistant Professor,Associate Professorを経て’92年,同分子細胞生物学部免疫学部門Full Professor(’96年まで).’94年から東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻教授,2012年,東京大学名誉教授.’13年より福井大学医学部高次脳機能部門特命教授(現在に至る).