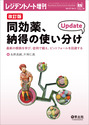こちらも御覧ください!
本文を見る
市原のオリジナル索引
| 読み | 項目 | サブ項目 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 1このち | 1個の中性脂肪分子は1個のグリセロールと3個の遊離脂肪酸になります | 64 | |
| 3ばんめ | 3番目のリン酸基を切り離すことでその化学的なエネルギーを解放して利用 | 22 | |
| 4にんで | 4人で旅すると他のメンバーの意向にも旅程が影響される | 143 | |
| ATP | ATPは生体のエネルギー通貨 | 22 | |
| 「ATP分解」とはATP分子がリン酸基に蓄えられていたエネルギーを解放してADPになること | 23 | ||
| βさんか | β酸化はアセチルCoAの好気的代謝を前提としていますから、心筋は血流途絶による酸素欠乏に非常に弱い | 144 | |
| cell | cellには細胞や電池という他に、刑務所の監房という意味もある | 56 | |
| CO2 | CO2から炭酸同化で食料の糖質を生産するプラントができると理想的 | 102 | |
| HDL | HDLが肝臓に回収してきたコレステロールから合成される胆汁酸(コール酸) | 85 | |
| TCA | TCA回路の最大の存在意義は基質の炭水化物からプロトンを奪うこと | 37 | |
| TCA回路(別名クエン酸回路あるいはクレブス回路) | 32 | ||
| VLDL | VLDL合成速度が相対的に遅いと中性脂肪は肝臓に蓄積して脂肪肝 | 83 | |
| あふれた | 溢れた門脈血はどこへ逃げ道を見つけるか | 111 | |
| あみのさ | アミノ酸からアミノ基を外すと炭水化物になってエネルギー代謝に利用できる | 44 | |
| あるぶん | ある分子から水素を奪うことも広い意味での酸化です | 21 | |
| ある分子に水素を結合させることは還元反応になります | 21 | ||
| あんもに | アンモニアの二面性 | 109 | |
| アンモニアを除去したい時(グルタミンシンターゼ) | 110 | ||
| いっぱん | 一般に糖尿病の症状と思われているものは、血液中にだぶついたグルコースによって浸透圧が上昇し、血管がダメージを受けたための副次的な合併症 | 72 | |
| いわかげ | 岩陰からすばやく餌に食いつくヒラメのような白身の魚 | 141 | |
| いんすり | インスリンは血糖を下げるホルモンではなく、グルコースの利用と貯蔵を促進するホルモンであると覚え直してください。 | 69 | |
| うんどう | 運動しなければやっぱり中性脂肪は減らない | 81 | |
| えんいに | 遠位尿細管でATPが必要 | 49 | |
| えんぶん | 塩分(NaCl)と水分を保持して故郷の海と同じ体内環境を維持することは死活問題 | 49 | |
| がいこく | 外国のアニメで監獄の囚人が足首に鉄の球をはめられているようなもの | 55 | |
| かいとう | 解糖系優位の細胞は何か | 141 | |
| かいどく | 解毒に関与する滑面小胞体 | 85 | |
| かじょう | 過剰なアセチルCoAはアセト酢酸、3ヒドロキシ酪酸、アセトンという3種類のケトン体と呼ばれる物質に変換されます。 | 67 | |
| 過剰な糖質摂取も結局はアセチルCoAを生み出すので、肥満の原因になります | 80 | ||
| かつてわ | かつてわが国の国民病とまで言われた脚気 | 91 | |
| かんこう | 肝硬変に至ると、この小葉構造が変形して血液はさらに流れにくくなり | 107 | |
| 肝硬変の患者さんはなるべく肉食を避けた方がよいと言われるのは | 107 | ||
| 肝硬変を起こすと本来肝門脈に流れるはずだった血液が、この分水嶺を超えて大静脈に逆流する | 108 | ||
| かんぞう | 肝臓で合成された中性脂肪を末梢の脂肪組織に輸送するのが超低密度リポタンパク質(VLDL) | 83 | |
| 肝臓と筋肉ではグリコーゲンの利用法が異なる | 58 | ||
| 肝臓は主として全身の血糖維持のためにグルコースを新しく合成しています | 49 | ||
| かんどう | 肝動脈・肝門脈・胆管の3本が並走する構造をグリソン鞘 | 106 | |
| きがじの | 飢餓時と糖尿病のエネルギー代謝 | 68 | |
| きちょう | 貴重な燃料である石油からビニールやプラスチックなどの化学製品をつくるように、グルコースにも燃料以外の素材としての側面があります | 136 | |
| きなーぜ | キナーゼはリン酸基を結合させる酵素の意味、ホスファターゼはそのリン酸基を分解して外す酵素という意味です | 56 | |
| きんにく | 筋肉に溜まった乳酸はそのままではエネルギーとして利用できませんから、糖新生でグルコースにつくり直す | 41 | |
| くうふく | 空腹時の心臓のエネルギー産生は脂肪酸のβ酸化に60%以上依存しています | 144 | |
| くえずに | 食えずに急いで蹴飛ばして少し怖いな風鈴のおっさん | 33 | |
| くえんさ | クエン酸シャトル | 78 | |
| ぐりこー | グリコーゲンが枯渇すると、中性脂肪の分解がはじまります | 64 | |
| グリコーゲンはグルコースの分子が枝分かれをしながら鎖状に重合した物質 | 55 | ||
| ぐりせろ | グリセロールはジヒドロキシアセトンリン酸に変換されて、そのまま解糖系を逆行してグルコースに至ります | 64 | |
| ぐるこー | グルコースが入ってこない時間帯のエネルギー代謝をいかに維持するか | 54 | |
| グルコースからピルビン酸までは解糖系 | 28 | ||
| グルコーストランスポーターが正常に機能するためには血清中のカリウムが必要 | 74 | ||
| ぐるこき | グルコキナーゼ 鎖を付ける看守 | 56 | |
| ぐるたみ | グルタミン酸とグルタミンの相互変換こそ生体内のアンモニア調節メカニズムの最も重要な反応です | 110 | |
| くれあち | クレアチンに預けて貯めておけるエネルギーバックアップシステム | 141 | |
| けっとば | “蹴飛ばす”前後に二酸化炭素が1分子ずつ抜けて炭素原子数が1個ずつ減っていきます。 | 33 | |
| けとあし | ケトアシドーシスと呼ばれる状態が糖尿病の本質 | 72 | |
| けらちん | ケラチン(上皮組織)、デスミン(筋肉)、ラミニン(核膜)、GFAP(神経細胞)など多彩 | 133 | |
| げんぱつ | 原発性アルドステロン症などで低カリウム血症があると、グルコースをうまく細胞内に取り込めず、まるで糖尿病のような高血糖を示す | 74 | |
| こうおん | 高温やアシドーシスなどの厳しい状況下ではその乏しいATP産生を犠牲にしてまで末梢組織により多くの酸素分子を配給する | 131 | |
| こうがい | 郊外から都心部へ主要道路が放射状に集中する東京やパリのような都市 | 111 | |
| こうきて | 好気的代謝をするミトコンドリアがあれば、末梢組織に運ぶべき酸素をつまみ食いしてしまう | 131 | |
| こうぞう | 構造的に肝内の血流は渋滞しやすい | 107 | |
| こうふん | 興奮している細胞の内部はプラスに荷電 | 24 | |
| こきゅう | 呼吸で大気中から吸入した酸素はここで使われる | 34 | |
| こっかく | 骨格筋はβ酸化への依存度が低いうえに、心臓と違って随意的収縮を休んでいれば筋肉内に蓄えられたグリコーゲンだけでかなりもちこたえます | 144 | |
| このかが | この化学反応が止まることはすなわち死を意味する | 37 | |
| これがな | これがなければ動物の進化と繁栄も起こらなかった | 35 | |
| これすて | コレステロールもアセチルCoAが原料 | 82 | |
| コレステロールを必要な組織に輸送するのが低密度リポタンパク質(LDL) | 83 | ||
| さいぼう | 細胞膜を物質が通過できるのは幕内に存在するタンパク質がゲートとして存在するからで、大きく分けて2種類あり、1つはトランスポーター、もう1つはチャネル | 70 | |
| さんかて | 酸化的脱アミノという奥の手 | 100 | |
| さんかは | 酸化反応は電子(e−)を奪う反応と定義されるが、生物学的には水素(H+)を奪う反応と考えるのが理解しやすく | 14 | |
| さんそが | 酸素が利用できない場合でも1個のグルコース分子から合計2個のATPが合成される | 31 | |
| 酸素が利用できる好気的条件の下では、いよいよミトコンドリアの出番 | 32 | ||
| じつは | 実は脱核という現象は非対称細胞分裂 | 124 | |
| しぼうさ | 脂肪酸のβ酸化が亢進して大量のケトン体が産生されて血液中に放出 | 72 | |
| 脂肪酸のβ酸化だけではTCA回路が空焚き状態になる | 67 | ||
| 脂肪酸はβ酸化でアセチルCoAを経てTCA回路へ | 65 | ||
| じゅうそ | 重層扁平上皮の細胞もミトコンドリアはもっていてもエネルギー産生は解糖系に頼らざるを得ない | 140 | |
| しょうか | 消化管で吸収された中性脂肪や他の脂質を肝臓に輸送するのがキロミクロン | 83 | |
| 消化管で発生したアンモニアのフィルターになっているのが肝臓 | 103 | ||
| しようせ | 脂溶性ビタミンをAとし、水溶性ビタミンをBにしようと予定していたところ、各種の水溶性ビタミンが続々と発見されてB1、B2と呼ぶうちに命名が後手に回った | 90 | |
| しょくど | 食道から上と、直腸の下部から流出した静脈血は直接大静脈に帰ります | 108 | |
| 食道の静脈が拡張して食道静脈瘤、直腸肛門の静脈が拡張して痔の悪化 | 111 | ||
| しょくぶ | 植物性炭水化物の摂取は、他の動物を捕食する労力に比べたらはるかに効率的で楽な生き方ですし、しかも糖新生という化学反応も省略することができます | 46 | |
| 植物は地球環境を酸化 | 14 | ||
| 植物を主食としないライオンやトラなどの肉食動物はどのようにしてATPを合成しているのでしょうか | 40 | ||
| しりめつ | 支離滅裂なビタミンB | 90 | |
| しんぞう | 心臓が収縮と拡張をくり返して鼓動するときに心筋細胞の集合体がプラスとマイナスに交互に荷電する境界面が移動するのを記録するのが心電図 | 25 | |
| じんぞう | 腎臓は糖新生をさかんに行っている | 49 | |
| 腎臓は夜間睡眠中に何をしているのでしょうか | 49 | ||
| じんたい | 人体内には炭素原子が偶数個の脂肪酸が多い | 65 | |
| ずいがい | 髄外造血が行われる部位は、ヘム合成の過程で遊離したアンモニアを除去するうえで非常に都合のよい配置になっている | 118 | |
| すいりょ | 水力発電所のようにタンパク質分子が回転して大量のATPが合成されます | 19 | |
| せいしつ | 性質も機能も全く異なる物質が無秩序に命名されて羅列されている | 88 | |
| せいしま | 静止膜電位と活動電位の約100 mVの差が神経細胞の長い軸索の中を移動していくのが神経伝導 | 25 | |
| せっきん | 赤筋はマラソンランナーの筋肉 | 141 | |
| せっけっ | 赤血球の膜にもアクチンがあるということは、赤血球も能動的に動く | 125 | |
| せんてん | 先天性の酵素欠損のためにグリコーゲンの利用が障害される疾患を総称して糖原病 | 59 | |
| ぜんりょ | 全力ダッシュするときの筋肉は速筋(白筋)といい、ミトコンドリアに乏しく、解糖系の代謝で酸素がなくても瞬発的な収縮をします。 | 47 | |
| 全力ダッシュはきわめて短時間に力尽きてしまう理由 | 47 | ||
| そしきち | 組織中に余ったコレステロールを回収して肝臓に逆転送するのが高密度リポタンパク質(HDL) | 83 | |
| たいない | 体内すべて水分のあるところには常に尿素がある | 51 | |
| 体内でアンモニアが必要とされる理由 | 109 | ||
| 体内に蓄積された中性脂肪の脂肪酸の炭素原子数は偶数のものがほとんど | 79 | ||
| ただしも | ただし元は絶世の美女 | 112 | |
| たんすい | 炭水化物の基質から引き抜いたプロトン4個をミトコンドリアの膜間腔からマトリックスに流入させるたびに1分子のATPが産生される | 35 | |
| たんそげ | 炭素原子数にだけ注目 | 29 | |
| ちちおや | 父親のミトコンドリアはここで使命を終える | 149 | |
| ちゃねる | チャネルはいわゆる穴の構造になっていて、それを開閉することで水や電解質など低分子の物質の通過を調節 | 70 | |
| ちゅうか | 中間径フィラメントという芸のない名前 | 132 | |
| ちゅうせ | 中性脂肪を減らすためにはミトコンドリアマトリックスで大量に発生するアセチルCoAをTCA回路で消費して、最終的に二酸化炭素と水にしてしまわなければいけません。 | 80 | |
| ちょうき | 長距離を回遊するマグロのような赤身 | 141 | |
| つごうの | 都合のよいシステム | 110 | |
| てつは3 | 鉄は3価の状態でフェリチンに貯蔵され、トランスフェリンによって骨髄に運搬 | 120 | |
| でんかを | 電荷を最も安全に外せる場所がミトコンドリアマトリックス | 120 | |
| でんきげ | 電気現象は細胞膜をはさんだ細胞内と細胞外の電位差 | 24 | |
| どうして | どうしても記憶しておかなければ気がすまない | 93 | |
| とうしん | 糖新生が行われる臓器は肝臓と腎臓で | 49 | |
| 糖新生という化学反応でグルコースを合成 | 40 | ||
| とうにょ | 糖尿病のエネルギー代謝は飢餓時と同じ | 69 | |
| どうぶつ | 動物の体は実は相当な量のアンモニアを必要としている | 109 | |
| 動物の体内の電気現象で電子の流れと捉えてよいのはミトコンドリア内膜に存在する電子伝達系だけ | 24 | ||
| 動物は地球環境を還元 | 14 | ||
| どのよう | どのような条件でヘモグロビンは酸素分子を手放しやすくなるのでしょうか。 | 129 | |
| とらんす | トランスアミナーゼ(アミノ基転移酵素)の作用 | 99 | |
| トランスポーターは分子の形を変えながらグルコースなど高分子の物質を通過させる | 70 | ||
| とりあえ | とりあえず「FAD(H)」あるいは「NAD(H)」という水素受容体(供与体)として押さえておいて、 | 93 | |
| なぜさい | なぜ細胞内がマイナスに荷電するのでしょうか | 24 | |
| なぜしゅ | なぜ瞬発力も必要としないがん細胞が解糖系優位なのでしょうか | 145 | |
| なとりう | ナトリウムの再吸収による体液の保持 | 51 | |
| なんきょ | 南極の岬に高木の名前を刻んだ | 96 | |
| にくしょ | 肉食動物は獲物の肉をアミノ酸に分解した後、アミノ基転移反応で炭水化物に変換してエネルギー代謝を行い、ATPを産生している | 46 | |
| にゅうさ | 乳酸を再び糖新生でグルコースに変換する際、筋肉と肝臓はアミノ基転移反応を使って非常に巧妙な共同作業を行っています | 47 | |
| にょうそ | 尿素回路でアンモニアを無害化 | 101 | |
| 尿素合成も肝臓で行われます。尿素だから腎臓で合成されるんだろうなどと誤解している人も多い | 85 | ||
| 尿素は炭素原子に2つのアミノ基が付いていて、この隙間に水の分子を抱き込むので非常に水との親和性が高く | 51 | ||
| にんげん | 人間の脂肪組織の色は鮮やかな黄色ですが、これはビタミンAの中間代謝産物が貯蔵されている本来の色 | 96 | |
| ねんりょ | 燃料にならないグルコース〜五炭糖経路 | 136 | |
| のうがぐ | 脳がグルコースしか代謝しない殿様なので、割を食う格好で他の重要臓器の肝臓や心臓などは脂肪酸で我慢しなければなりません | 144 | |
| のうはへ | 脳は平時はグルコースしか代謝しません | 144 | |
| はっきん | 白筋はスプリンターの筋肉 | 141 | |
| ひきだて | 引田天功さん | 124 | |
| ひひっす | 非必須アミノ酸の生合成は糖新生の逆反応である | 109 | |
| ひまんし | 肥満者の腹部に沈着するギトギトした気持ち悪い物質という偏見は捨ててください | 62 | |
| びりょう | 微量であってもアンモニアが体循環の血液中に入れば人間は昏睡状態から死に至ります。 | 98 | |
| ふるくな | 古くなった赤血球に含まれるヘモグロビンの分解産物であるビリルビン | 85 | |
| へそをち | 臍を中心に静脈がウネウネと怒張して | 111 | |
| へむはさ | ヘムはサーモンが生まれ故郷の川に戻ってくるように再びミトコンドリアマトリックスに戻ってくる | 119 | |
| へむはみ | ヘムはミトコンドリアの中で生まれる | 115 | |
| へもぐろ | ヘモグロビンの酸素解離曲線 | 127 | |
| べんきょ | 勉強の意欲も湧いてくる | 38 | |
| ほかのあ | 他のアミノ酸はアミノ基をパス回しのようにαケトグルタル酸に受け渡しグルタミン酸に変えた末、最終的にグルタミン酸がアンモニアを遊離させてゴールシュートを決めるようなものです。 | 100 | |
| ほんらい | 本来リポタンパク質に善玉悪玉の区別はありません | 83 | |
| まのじか | 魔の時間帯に腎臓はレニン・アンギオテンシン・アルドステロン系を最大限に働かせて体内の水分を引き止めている | 49 | |
| まるあん | 丸暗記しないで下さい | 94 | |
| みおぐろ | ミオグロビンというバックアップシステム | 142 | |
| みとこん | ミトコンドリアマトリックスは細胞内で最も二酸化炭素濃度が高い場所 | 102 | |
| ミトコンドリアを失った赤血球の代謝はすべて解糖系に依存する | 125 | ||
| めいしょ | 名称とギャップがありますが、一番太いのが微小管 | 131 | |
| もうさい | 毛細血管を出て次の毛細血管までをつなぐ血管が門脈であり、人体では肝門脈と脳下垂体門脈の2カ所しかありません | 103 | |
| ようしょ | 洋食を嫌う日本人のために米食から麦食やパン食へ切り替えた | 91 | |
| りくせい | 陸生動物は最初はすべて肉食で、互いに共食いをしていた | 46 | |
| りんごさ | リンゴ酸シャトル | 43 | |
| るいどう | 類洞を通っていく間に肝細胞の尿素回路によってアンモニアが除去 | 106 | |
| れにんあ | レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系の機能を一言でいえば、血液量が減少したときに尿中に排出するナトリウムを再吸収することです。 | 49 | |
| われわれ | 我々の細胞はエネルギープラントであるミトコンドリアの排気ガス(二酸化炭素)を使って劇物の処理を行っている | 102 |
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)
本記事の関連書籍