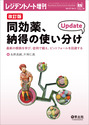こちらも御覧ください!
本文を見る
第4回
小説みたいに免疫学で
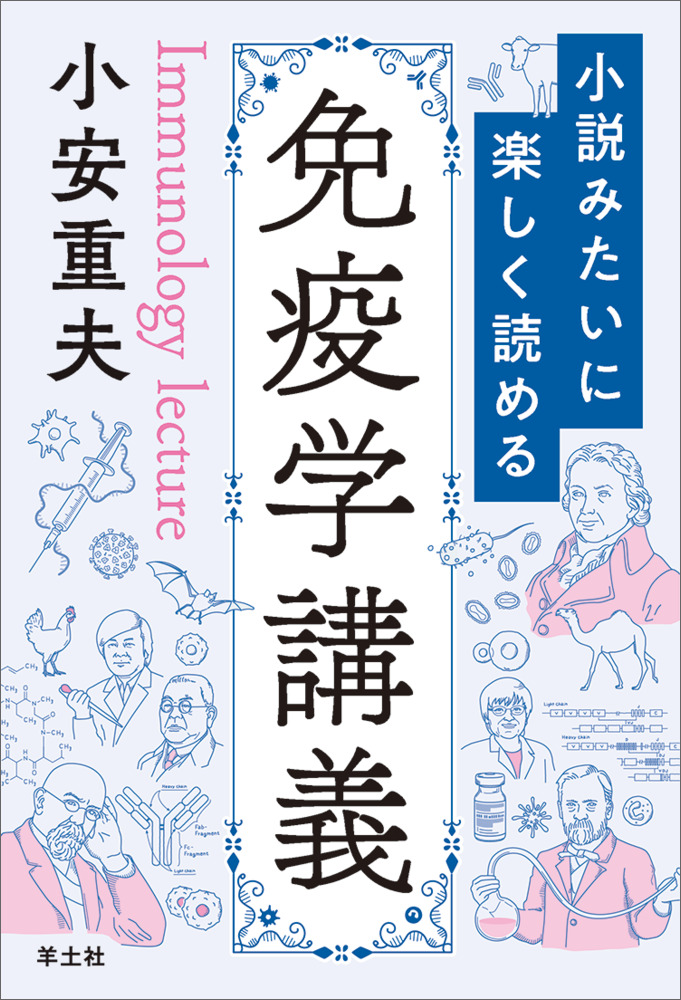
小説みたいに免疫学で
勝手に索引!
の完全索引
小説みたいに楽しく読める免疫学講義
著/小安重夫
■定価2,420円(本体2,200円+税) ■四六判 ■288頁 ■羊土社
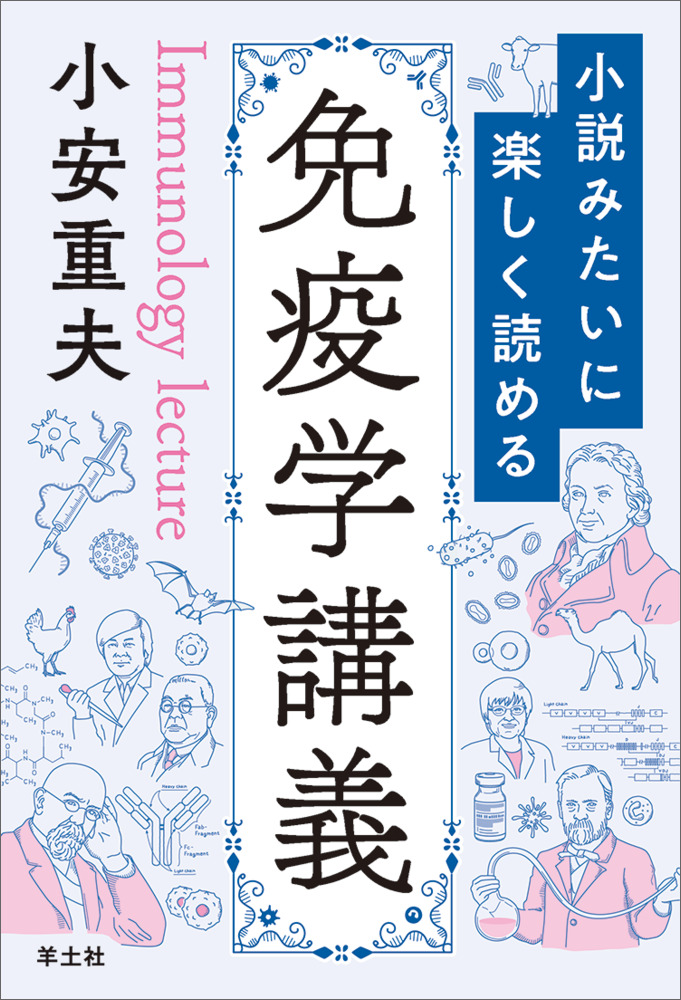
市原のオリジナル索引
| 読み | 項目 | サブ項目 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| Iがたあ | Ⅰ型アレルギー | 53,116 | |
| Ⅲがたあ | Ⅲ型アレルギー、あるいは発見者の名をとってアルツス反応 | 231 | |
| 100を | 100を超える何とか因子という名称が整理・統合 | 51 | |
| AID | AID | AIDがはたらかないとクラススイッチが起こらず、IgMしかつくられません | 186 |
| AIDの遺伝子は常染色体にあり、両方の染色体の遺伝子に変異があると高IgM血症になります | 187 | ||
| Aire | Aire | Aireは胸腺の髄質にいる上皮細胞でつくられる | 152 |
| Aireをもつ上皮細胞でインスリンをはじめとするたくさんの臓器特異的と考えられたタンパク質がつくられる | 152 | ||
| aとsは | aとsは米原と一緒に抗体をつくった石井愛と米原伸の名前(愛と伸)の頭文字という説も有力です | 205 | |
| Bさいぼ | B細胞 | B細胞が抗原に出会うと細胞の表面の抗体に抗原がくっつき、これがきっかけとなってB細胞は分裂して増えはじめ、さらにそれまで細胞の表面にあった抗体を細胞の外に分泌するようになります | 182 |
| B細胞がつくる抗体と大きく異なる点は、T細胞受容体は抗原に直接結合することができないことと、抗体のように分泌されない点 | 119 | ||
| B細胞が、瀘胞樹状細胞の表面の抗原を取り合い、より強く結合できる抗体をつくるB細胞の方が刺激されて生き残ると考えられています。これが親和性成熟のしくみです | 190 | ||
| CAR-T | CAR-T細胞療法は簡単にいうと、T細胞に抗体を入れてしまおうという考え | 257 | |
| CD25 | CD25をもつT細胞が5%くらい存在 | 158 | |
| CD28 | CD28に結合して刺激するタンパク質は複数あり、これらはB7ファミリーとよばれ、抗原提示細胞である樹状細胞、マクロファージ、活性化されたB細胞の三種類の細胞がもっています | 156 | |
| CD8 | CD8というタンパク質を表面にもちキラーT細胞になるT細胞がMHCクラスⅠとともに抗原をみる | 124 | |
| HIV | HIVは、白血球上の二つのタンパク質を受容体として感染します | 264 | |
| IgA | IgAは、ウイルスや細菌が粘膜に結合して侵入する前にそれらの病原微生物に結合し、水際でその侵入を食い止めています | 171 | |
| IgG | IgGは血液中に最も多く含まれる抗体で、四本の鎖でできたY字のような構造をしています | 115 | |
| MBLや | MBLやCRPなどは、感染が起こっている場所でマクロファージなどがつくるIL-1βが肝臓に作用してつくられるタンパク質です | 110 | |
| MHC | MHC | MHCクラスⅠは細胞の中(例えば、ウイルス)の、MHCクラスⅡは細胞の外(例えば、細菌)の抗原を提示する | 131 |
| MHCと関係なく抗原をみるようなT細胞をつくってしまおうというのがCAR–T細胞療法です | 257 | ||
| MHCの組合わせはいわば個人を特定するQRコードのようなもの | 96 | ||
| NKさい | NK細胞は自分と同じMHCクラスⅠをもたない骨髄細胞や、自分のMHCクラスⅠがウイルスの感染によって著しく変形したり、あるいはがん細胞のように表面のMHCクラスⅠの量が減った細胞を殺す | 135 | |
| NKT細胞もMAIT細胞も自然免疫ではたらくリンパ球 | 200 | ||
| NK細胞が戦っている間に、B細胞が抗体をつくり、抗体がウイルスにくっつくことで感染の広がりを抑える | 169 | ||
| NK細胞はT細胞受容体をもちません | 133 | ||
| O-157 | O-157などの腸管病原性大腸菌は貪食されることなく、食細胞の表面にくっついたまま増えます | 268 | |
| RNA | RNA | RNAでも私たちがもつトランスファーRNAやリボソームRNAはいろいろな化学修飾を受けていて炎症を起こさない | 220 |
| RNAはTLR3やRIG-Iなどを介して強い炎症を起こす | 220 | ||
| 私たちはRNAからRNAをつくることができませんから、ウイルスは自分で道具をもっているのです | 17 | ||
| SARS | SARSの場合には感染するとほぼ100%発症した | 10 | |
| TLRの | TLRのリガンド | 105 | |
| TLRは | TLRは微生物由来の異物を見分けるアンテナ | 48 | |
| TNFα | TNFαやヘルパーT細胞のつくるγ型インターフェロン(後述)のようなサイトカインは、マクロファージの貪食・殺菌能を強めることで感染の拡大を抑え込みます | 166 | |
| Toll | Toll遺伝子がきっかけとなり、アジュバントがはたらくしくみが明らかに | 48 | |
| Tさいぼ | T細胞 | T細胞が中心となる自己免疫疾患 | 237 |
| T細胞がつくるインターロイキン(IL)-4やIL-5によってB細胞は分裂・増殖し、さらにIL-6の作用によって最終的に抗体を分泌する形質細胞となり、IgMを分泌します | 182 | ||
| T細胞受容体が抗原の一部であるペプチドとMHCタンパク質の複合体をみている | 129 | ||
| T細胞受容体とCD28から刺激を受けた後、IL-2によって分裂・増殖するに従って、細胞内の顆粒に他の細胞を殺すためのさまざまな道具を用意して、はじめてキラーT細胞となります | 196 | ||
| T細胞受容体の形は抗体とそっくり | 118 | ||
| T細胞とB細胞はT細胞受容体とMHCによって互いに接触し、さらにサイトカインを使って効率よく抗体をつくる | 192 | ||
| T細胞とよばれるリンパ球のはたらきを自分の目で見ることができる数少ない機会 | 25 | ||
| T細胞に抗原をみせる細胞が必要 | 121 | ||
| T細胞のなかでもCD4というタンパク質を表面にもちヘルパーT細胞になるT細胞がMHCクラスⅡとともに抗原をみる | 124 | ||
| T細胞は胸腺で皮質にいる上皮細胞によって自分のMHCを学び、樹状細胞などの骨髄から来る細胞によって髄質で自分に反応する細胞をとり除きます | 241 | ||
| あたらし | 新しいものを見つけたときには魅力的な名前を付けることが大事 | 51 | |
| あなじー | アナジー | アナジーとよばれる状態 | 156 |
| 移植した臓器を攻撃するT細胞をアナジーの状態へもっていければ、成功率は上がるはず | 248 | ||
| あれるぎ | アレルギーを起こす花粉の成分はこのタンパク質分解酵素です | 229 | |
| いちにち | 一日待てば樹状細胞が抗原をもちかえったリンパ節の中でその抗原をみることができるT細胞とB細胞が出会える | 192 | |
| いっちょ | 一兆個がリンパ球 | 19 | |
| いでんし | 遺伝子再構成は、核の中のDNAにある遺伝子の情報は不変であり、あらゆる細胞はその遺伝子の情報によって規定された運命をたどるという、それまでの考えをうち砕く驚天動地の結果でした | 86 | |
| いまでは | 今では野外実験など考えられません | 37 | |
| いんすり | インスリン受容体に結合する抗体ができて、インスリン受容体にインスリンが結合できなくなると、糖が細胞に取り込まれずに血糖値が上がって糖尿病 | 235 | |
| いんたー | インターフェロン | インターフェロンが作用した細胞は、いろいろなウイルスに対して抵抗性を獲得する | 49 |
| インターフェロンが作用した細胞は、いろいろなウイルスの感染に対して抵抗性を獲得します | 168 | ||
| いんふら | インフラマソームははたらき過ぎると炎症が起こるので、そのはたらきは厳密に制御されていますが、遺伝子の変異によってブレーキがかからなくなることがあり、そうなると無菌性炎症が起こります | 108 | |
| ういるす | ウイルス | ウイルスが細胞へ入ってしまえば抗体ではお手上げ | 169 |
| ウイルス感染で死んだ細胞を取り込むことによって、樹状細胞はウイルスの抗原をMHCクラスⅠとMHCクラスⅡの両方に提示する | 174 | ||
| ウイルス感染防衛線 | 168 | ||
| ウイルスと戦えるリンパ球が10万倍以上に増え | 20 | ||
| ウイルスに感染した細胞を殺すキラーT細胞は、自分の細胞が感染したときのみ殺すことができて、他人の細胞がウイルスに感染しても殺すことができない | 121 | ||
| ウイルスにはじめて感染した場合には、まずウイルスに結合するIgMが生産され遅れてIgGがつくられますが、二度目に同じウイルスに感染したときには最初からIgGがたくさんつくられます | 188 | ||
| えんしょ | 炎症性マクロファージあるいはM1マクロファージ | 206 | |
| おおきく | 大きくなったがんは監視機構をくぐり抜けたことからすでに免疫にとっては脅威です。また、その過程で最初は反応できたかもしれないT細胞がアナジーに陥っているかもしれません | 255 | |
| おおくの | 多くのイヌがショック死 | 53 | |
| おぷそに | オプソニン化とは味つけをするというような意味 | 45 | |
| かいすい | 海水浴客を上得意とするモナコ王室にとってはクラゲやイソギンチャクの被害は大きな問題 | 53 | |
| がくせい | 学生実習が失敗することはままあることです | 58 | |
| かたちが | 形が全く異なる形質細胞とリンパ球が関連するとは当時の人は思いつかなかった | 60 | |
| かんせん | 感染経路の違いによってつくられるヘルパーT細胞の種類も違ってくる | 210 | |
| 感染しても無症状か軽症で終わらせるのがワクチンの目的なのです | 21 | ||
| かんれい | 寒冷凝集素がまさに溶血性貧血を起こす自己抗体 | 234 | |
| きけんか | 危険仮説:アジュバントの効果 | 179 | |
| きせいち | 寄生虫に感染する人が少なくなり、IgEはあまり必要のない抗体 | 227 | |
| 寄生虫に特異的なIgEは消化管の肥満細胞を刺激することで粘液の成分であるコンドロイチン硫酸を大量に分泌し、寄生虫は腸管内に定着できずに便とともに排除される | 227 | ||
| きょうせ | 胸腺 | 胸腺という名前から想像できるように、内分泌器官と考えられていた時代もありました | 56 |
| 胸腺由来の細胞を胸腺(Thymus)の頭文字をとってT細胞 | 60 | ||
| きょうせ | 胸腺大学 | 胸腺大学の講師陣:上皮細胞と樹状細胞の役割 | 150 |
| 胸腺大学の卒業試験はたいへん難しい | 141 | ||
| きょうつ | 共通項はタンパク質分解酵素です。タンパク質分解酵素が上皮細胞を壊してIL-33が放出され、それに反応したILC2がアレルギーを起こす | 229 | |
| きょぜつ | 拒絶にかかわる遺伝子が複数あり、主要組織適合性複合体〔MHC(Major Histocompatibility Complex)〕とよばれています | 94 | |
| 拒絶反応もウイルスに対する戦いも細胞性免疫が関与します | 25 | ||
| きらーT | キラーT細胞の細胞傷害性 | 197 | |
| くらすす | クラススイッチは、定常領域の遺伝子が再構成を起こして次々に置き換わっていく現象 | 185 | |
| けいしつ | 形質細胞となって抗体をどんどんつくるようになったB細胞は、輸出リンパ管からリンパ節を離れ、最終的には骨髄へと移動してさらに抗体をつくり続けます | 192 | |
| けつえき | 血液中で職務質問をするパトロール隊:補体 | 109 | |
| けっかく | 結核菌の死骸を浮遊させた鉱物油は、一緒に投与した物質に対する抗体の作製に驚異的な力を発揮 | 47 | |
| けっせい | 血清に入れる塩の量を増やしていったときに、早く沈殿してくる「グロブリン」というタンパク質群 | 77 | |
| げんざい | 現在ヒトに使われるアジュバントは水酸化アルミニウムです | 220 | |
| こうえん | 抗炎症性マクロファージあるいはM2マクロファージ | 208 | |
| こうげん | 抗原が樹状細胞によってMHCと一緒にみせられて、かつB7ファミリーがCD28を刺激しない限り活性化しない | 157 | |
| こうたい | 抗体 | 抗体のことをγグロブリンとよぶこともあります | 77 |
| 抗体の多様性を生み出しているのは、個々の抗体がN末端側に特有のアミノ酸の並び方をもつため | 82 | ||
| 抗体の発見です。この結果を応用したのが三種混合ワクチンです | 40 | ||
| 抗体は抗原の細かな形の違いを見分けて特異的に結合するとともに、Fcの違いで異なるはたらきをする | 116 | ||
| 抗体をつくろうと思ったら、アジュバントとともに投与することが必要 | 178 | ||
| 抗体を用いてCTLA-4やPD-1による抑制を外すという新しいがんの治療法 | 201 | ||
| こつずい | 骨髄は英語でBone Marrowですから、都合のよいことにここでも頭文字はBでした | 60 | |
| こっほは | コッホは炭疽菌を分離し、動物に炭疽病を起こし、さらにその動物から再び炭疽菌を分離してみせました | 35 | |
| このとき | このときに私たちの肺の細胞は壊れて死んでしまいます | 17 | |
| さいきん | 細菌感染防衛線 | 165 | |
| 細菌に獲得免疫のようなはたらきがあることの方が衝撃 | 85 | ||
| 細菌やウイルスではDNAはメチル化されず、例外はありますがヒストンもくっついていません | 105 | ||
| さいごま | 最後まで沈殿しない成分が「アルブミン」 | 77 | |
| さいぼう | 細胞の中にも異物を見つけ出す受容体があります | 105 | |
| さるとう | サル痘の予防のために種痘が復活するかもしれません | 219 | |
| しげきさ | 刺激されたB細胞は、それまでは細胞の表面につくっていた抗体を細胞の外へ分泌するようになります | 117 | |
| 刺激されたヘルパーT細胞がつくるγ型インターフェロンによってマクロファージの殺菌能が大幅に亢進し、細胞内の結核菌を殺す | 194 | ||
| じこえん | 自己炎症性疾患 | 108 | |
| じここう | 自己抗体によって起こる病気は、別名Ⅱ型アレルギー | 236 | |
| 自己抗体によって病気が起こる自己免疫疾患は、自分の細胞に危害を加えるものと、細胞機能を失わせるものに分類されます | 234 | ||
| しぜんめ | “自然免疫”とよばれる免疫のはたらきの研究の草分け | 42 | |
| 自然免疫にもキラーT細胞やヘルパーT細胞と同じようなはたらきをする細胞がいた | 215 | ||
| しばらく | しばらく経ってから免疫抑制剤の投与をやめても拒絶反応が全く起こらなくなる場合もあります。おそらくアナジーが効率よく誘導されたのだと思われます | 249 | |
| じぶんの | 自分の成分(これを自己抗原とよびます)に反応する可能性のあるリンパ球は、成熟する前に自己抗原に出会うことによって除去される | 71 | |
| じゅじょ | 樹状細胞は抗原を捕捉すると同時にTLRによる刺激を受けて成熟することでリンパ節に移動します | 178 | |
| 樹状細胞は細菌やウイルスに感染した細胞を貪食し、細菌やウイルスの成分によってTLRが刺激されると、リンパ管やリンパ節でつくられるケモカインに結合できる受容体をもつ | 177 | ||
| 樹状細胞はマクロファージよりも強力で、最も強力にT細胞を刺激する抗原提示細胞 | 174 | ||
| しょうか | 消化管ではむしろ積極的に異物を無視するためのしくみがあると考えられています。これを経口寛容とよびます | 181 | |
| しょくさ | 食細胞が集まり、その部分が赤く腫れ、熱をもち、痛みが出ることを炎症とよびます | 166 | |
| 食細胞が細菌を選ばないようにインターフェロンもウイルスを選びませんので、ウイルスの感染に対する第一線の自然免疫のはたらきです | 168 | ||
| 食細胞の重要性を説きましたが、抗体の発見やワクチンの驚異的な効果の前に彼の声はかき消された | 42 | ||
| しょっく | ショック死した犬のように… | 223 | |
| しんがた | 新型コロナウイルスではじめて使われたmRNAワクチンも、遡れば20年くらいの研究の歴史のうえに開発されました | 18 | |
| 新型コロナウイルスの研究が進むなかで自然免疫での新しい概念も生まれました。訓練免疫(Trained Immunity)という考え方です | 216 | ||
| じんこう | 人工アジュバントベクター細胞療法はいわば細胞を使ったワクチン療法です | 262 | |
| しんぞう | 心臓移植に成功した後であれば、心臓と同じ提供者からの皮膚を移植するとうまくいきます | 250 | |
| 心臓のクッション | 56 | ||
| せいぎょ | 制御性T細胞はTGFβがたくさんつくられる腸に多い | 162 | |
| せいげん | 制限酵素からCRISPR-Cas9 | 84 | |
| せいぶつ | 「生物は無からは生じない」 | 35 | |
| せかいじ | 世界中の人が多田の背中をみることになり、世界で一番有名な背中 | 226 | |
| せっけっ | 赤血球にMHCクラスⅠがないからこそ、血液型さえ合えば輸血ができる | 97 | |
| ぞうきと | 臓器特異的タンパク質がAireやFezf2の作用によって胸腺の中でつくられ、そのような自分のタンパク質に反応するT細胞がとり除かれる | 153 | |
| そのひと | その人からはき出されるウイルスの数を少なく抑えることもワクチンの目的です | 21 | |
| たくさん | たくさんの食物が通過する腸には、パイエル板とよばれる特殊なリンパ節があり、腸から直接抗原を取り込むことによって病原細菌などの異物を監視 | 180 | |
| だつかん | 脱感作療法 | 230 | |
| だれかが | 誰かが発表をはじめると、すぐにマイクの前に質問者の列ができる | 23 | |
| ちくさん | 畜産関係の雑誌に発表したために、医学関係者には気づかれませんでした | 58 | |
| ちちゅう | 地中海熱 | 108 | |
| ちょうな | 腸内細菌も免疫のレパートリーに大きな影響を与える | 73 | |
| ちょうに | 腸には食べ物由来のいろいろな異物が入ってきますから、免疫をある程度抑えることが必要 | 162 | |
| つうふう | 痛風は尿酸の結晶がNLR経路で認識される | 108 | |
| てんねん | 天然痘の患者が使った毛布をスペイン人がもち込んだ | 28 | |
| とうさの | 糖鎖の違いを見分ける受容体として、レクチンと総称されるいろいろな糖鎖に特異的に結合するタンパク質が知られています | 103 | |
| どくしょ | 貪食やインターフェロンなどの自然免疫の防衛戦が破られるとT細胞やB細胞の出番 | 172 | |
| とくてい | 特定の自己免疫疾患とMHCの型が密接に関連している場合が多い | 233 | |
| とくにけ | 特に結核菌の死骸を浮遊させた鉱物油はこれを完成させたフロイントの名を冠してフロイントの完全アジュバントとよばれ、現在も抗体をつくるときには頻繁に使用されています | 47 | |
| どくへび | 毒蛇に噛まれた場合に、すみやかに抗毒素血清を注射することによって多くの命が救われている | 41 | |
| どくをま | 毒をまくけど自分だけは解毒剤をもっているようなもの | 113 | |
| なんらか | 何らかの微生物感染が自己免疫疾患のきっかけになる可能性は高い | 238 | |
| にどなし | “二度なし”現象 | 18 | |
| にどめ | 二度目 | 二度目に同じ毒素を投与すると、今度はすみやかにIgGが大量につくられます | 79 |
| 二度目につくられるIgGの方が最初につくられるIgMやIgGよりも抗原に結合する力が強く、毒素を無毒化する力も強い | 79 | ||
| 二度目は「かからない」という意味は「感染はするが発症はしない」という意味です | 21 | ||
| ねんまく | 粘膜をつくる上皮細胞は殺菌作用を示す抗菌ペプチドを分泌します | 171 | |
| はじめに | はじめに、第一線で戦うのはマクロファージや好中球などの食細胞 | 166 | |
| はつかね | ハツカネズミのことを研究の世界ではマウスといいます | 58 | |
| ひとつの | 一つのB細胞は一種類の抗体しかつくらない | 64 | |
| ひふにく | 皮膚に比べて心臓、肝臓、腎臓などの方が移植は簡単です。その理由の一つとして、これらの臓器には皮膚よりも樹状細胞が圧倒的に少ない | 248 | |
| ふぁぶり | ファブリキウス嚢(Bursa of Fabricius)由来の細胞をやはり頭文字をとってB細胞 | 60 | |
| ぶれーく | “ブレークスルー感染”といって騒いでいますが、感染するのは当たり前です | 21 | |
| へるぱー | ヘルパーT細胞と同じような役割をもちながら抗原をみる受容体をもたないリンパ球が次々と見つかりました。自然リンパ球の発見です | 210 | |
| ヘルパーT細胞のいろいろ | 207 | ||
| へるぺす | ヘルペスウイルスの仲間は芸術的ともいえる戦略 | 270 | |
| ヘルペスウイルスはMHCに似たタンパク質をつくることでこれに対抗します | 270 | ||
| ほたい | 補体 | 補体とよばれる一群のタンパク質の発見 | 44 |
| 補体の結合が貪食を助けるという発見は重要 | 44 | ||
| 補体は相手を選ばずすべての細胞に結合するのですが、私たちの細胞はそれを止めることができるので細菌だけにはたらく | 111 | ||
| 補体が結合してオプソニン化された細菌は、よりすみやかにマクロファージや好中球に貪食されます | 166 | ||
| またおな | また同じウイルスが感染すれば、再びそのウイルスと戦えるリンパ球のクローン増殖が起こり、免疫記憶も維持されます | 69 | |
| まてんろ | 摩天楼のようにみえるということでマンハッタンプロット | 245 | |
| めんえき | 免疫が、どうして自分自身を攻撃しないのかという自己寛容の説明 | 71 | |
| 免疫記憶がどのように維持されるかは、残された大きな謎の一つ | 70 | ||
| 免疫チェックポイント阻害剤 | 256 | ||
| もっとも | 最も強力な抗原提示細胞が樹状細胞 | 123 | |
| らいきん | らい菌や結核菌などのマイコバクテリアとよばれる種類の細菌が、食べられても細胞内で生き延びる | 44 | |
| りすてり | リステリア菌やサルモネラ菌は食胞から細胞質へ逃れ、細胞質の中で増えます | 268 | |
| りんぱき | リンパ球 | リンパ球の多くが成熟する途中で死んでとり除かれる | 72 |
| リンパ球は血管とリンパ管の両方を通り、一日に一回はからだの中を循環する | 177 | ||
| リンパ節では処理しきれずに血液中に入った抗原や、はじめから血液中に侵入した抗原は脾臓において樹状細胞が捉え | 180 | ||
| リンパ節には血管が入り込んでいて、そこを常に白血球や赤血球が通りますが、ここからT細胞とB細胞だけがリンパ節に入っていきます | 176 | ||
| リンパ節や脾臓の胚中心でB細胞が抗体をつくることを助けることに特化したヘルパーT細胞が濾胞ヘルパーT細胞(Tfh) | 208 | ||
| りんぱそ | リンパ組織を発達させることで出会いの場をつくり | 180 | |
| れいせい | 冷静な学級委員長:制御性T細胞 | 158 | |
| わくちん | 「ワクチン」という言葉はパスツールの作ですが、彼はこれをラテン語でウシを意味する「ワッカ」からとって、ジェンナーの功績を讃えた | 37 | |
| ワクチンやツベルクリン検査は獲得免疫の応用 | 25 | ||
| わたした | 私たちの細胞はC3を分解したり、他の補体成分が結合することを阻止することのできる、補体制御因子とよばれるタンパク質を複数もっています | 111 | |
| γδTさい | γδT細胞は微生物がつくるピロリン酸化合物をみて活性化されることがわかっており、自然免疫にはたらくT細胞 | 199 | |
| κとλ | κ(カッパ)とλ(ラムダ)と名付けられた | 81 |
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)
本記事の関連書籍