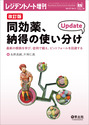こちらも御覧ください!
本文を見る
第5回
緩和ケア×生命倫理×社会学で勝手に索引!

緩和ケア×生命倫理×社会学で勝手に索引!
の完全索引
臨床現場のもやもやを解きほぐす 緩和ケア×生命倫理×社会学
著/森田達也,田代志門
■定価2,640円(本体2,400円+税) ■A5判 ■212頁 ■医学書院

市原のオリジナル索引
| 読み | 項目 | サブ項目 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| Goffman | Goffmanという社会学者はたいそうな皮肉屋 | 58 | |
| Kleinman | Kleinmanのいう「説明モデル」 | 79 | |
| prepare | prepareの話題に入るときのことを「患者のペースに合わせる!!タイミングは逃さない!!!」という言い方をします(!のところに意気込みがある) | 57 | |
| あつかっ | 「あ,使っても身体に合わなければやめていいです」と説明されるほうがかえって内服するハードルが下がる | 70 | |
| あどばん | アドバンス・ケア・プランニング(ACP)的な話題 | 158 | |
| あなたに | あなたに当てはまるというわけではないんだけど…… | 12 | |
| あのせん | あの先生は,どうも自分が死ぬまでの道筋がわかってるみたいなんだよなぁー | 13 | |
| あんらく | 安楽死の焦点は精神的苦痛に移っている | 128 | |
| いきてい | 生きているには楽しみが必要だからね | 112 | |
| いきるい | 「生きる意味がない」といった苦悩(suffering)への対処もまた医療が担うのだ | 132 | |
| いきをひ | 息を引き取るのは,死者であり同時に死を見守った人たちである | 182 | |
| いこうし | 移行した後に生じることを家族が引き受ける,という局面を重く見る人は家族側に寄り添った発想に近づいていく | 185 | |
| いしきこ | 意識混濁があるときに見落とされやすい苦痛の原因として知られているのは,尿閉,宿便,体位による苦痛です | 166 | |
| 意識混濁した井本さんでも,薬を飲むのが本当に嫌だ,点滴するのが本当に嫌だ,ならどこかにその素振りが出るでしょう | 153 | ||
| いしにい | 医師に言ったことと看護師に言ったことが食い違っていたとすれば,いずれかが「正解」というよりも,その間で揺れている,と受け取ればよい | 160 | |
| いしやか | 医師や家族によるQOL評価が,本人よりも低い | 159 | |
| いぜんは | 以前話し合って決めた内容は,本人が決めることができなくなった時点でその通りになるとは限らないけれど,とても大事な考慮事項の1つ | 158 | |
| いっぱん | 一般的ではない医療については,医師には良心的拒否権のようなものはあり | 53 | |
| いまから | 今からずっと眠るってなんだか安楽死に近い気もするし…… | 112 | |
| いまこの | 今この時間は業務といえば業務だけど趣味でやってる研究だといえば趣味の時間でもある | 189 | |
| いままで | 「(今までは楽しかった)食事の時間が最近つらい」「ご飯一緒に食べないから話すこともなくなっちゃって……」「毎日毎日こんなに準備しているのにぜんぜん食べてくれなくて……」「あれこれ作っても残っちゃうから,残りものばっかり食べてて体調がおかしい」といったつらさ(distress)のなかに, 容貌に関する,「あんなにまるまるしてて元気そうだったのに(こんなにやせちゃって)」 | 175 | |
| いりょう | 医療化が進んだ結果,人びとの間には「良い死に方」に関する自らの判断に関してもホスピス・緩和ケアの専門家に依存するようになる | 130 | |
| 医療者が家族と一緒に患者さんの身体に触れながら,亡くなるプロセスを共有している | 181 | ||
| 医療者の側から家族に対してこうした影響を払拭するような積極的な「再教育」をしない限り,「まずは家族に」という慣行は変化していかない | 35 | ||
| えそれほ | 「え?それほどじゃないよね?」という苦痛に対して,患者の意識を下げることを前提とした方法をとっていいのかは国内外でも議論があり | 113 | |
| おなじじ | 同じ人物に複数回のインタビューを行うと同じエピソードが細部を変えて繰り返されたり,別の解釈を伴って提示されることを指摘し, これを「ヴァージョンのある話」と呼びました | 161 | |
| おぴおい | オピオイドの増量をしない患者の理由 | 71 | |
| おみまい | お見舞いのときだけとか夜だけとかだと,一番つらいときや夜眠れない時間の患者さんの状況がわからない | 22 | |
| おらんだ | オランダの安楽死法は「患者の権利」として安楽死を認めているのではなく,医師の「確信」によるもの, と位置づけています | 131 | |
| かんがい | 感慨深い一方でどこへ向かっていくのやら | 126 | |
| かんじゃ | 患者が苦痛を緩和してほしい 対 家族はもっとがんばってほしい | 22 | |
| 「患者 対 家族」問題(のようなもの)がよく臨床現場で起こること | 33 | ||
| 患者と「友達になる」とか「好きになる」といった戦略は取られておらず,むしろ職務として患者の拒否的態度の背景を探るという「限定的な」視点から実践が組み立てられている | 99 | ||
| 患者との信頼関係が強固であればあるほど医師は予言者に近づいてしまう | 17 | ||
| 「患者の意向 対 患者への利益や害」という軸で考える | 25 | ||
| 患者の意識がないからといって,自分のストライクゾーンだけを見て決めるわけではない | 156 | ||
| 患者の心に届くときをじっと待っている | 57 | ||
| かんせつ | 「間接的安楽死」と呼ばれるカテゴリー | 115 | |
| がんちり | 「がん治療して当たり前」と「痛み治療して当たり前」が同じになってないかな | 82 | |
| がんでい | がんで痛いというのは初めての経験で何か言い方が悪くてうまく伝わってないだけじゃないかしら | 77 | |
| かんわけ | 緩和ケア医のなかには,医療技術の問題を超えて「良い死に方」を指南したり,さらにはそれが逆照射する「良い生き方」を明示的に呈示したりする人がそれなりにいますよね | 130 | |
| 緩和ケア医のアイデンティティをprepare for the worstに見出す | 61 | ||
| 緩和ケアの専門家が人生の専門家のような気になってしまうことはある | 133 | ||
| きゅうじ | 休日勤務外の日でも呼び出してください。一緒に行ってきま~す☆☆ | 96 | |
| きょうま | 今日, 全くprepareのほうがなかったと思うんですけど | 48 | |
| きんむじ | 勤務時間外には対応しないほうが,結果的には長く安定してケアできる | 97 | |
| くつうを | 苦痛を緩和しようとすると意識を犠牲にせざるをえない | 28 | |
| くるしみ | 苦しみに積極的な意味を見出す | 74 | |
| くるしむ | 「苦しむことのできる意識が残っていることは善である」という見方 | 119 | |
| くるまを | 車を買いたいと思っていない人にいくら個別の車のCM を見せても何の記憶も残らないのは当たり前 | 56 | |
| けいしき | 形式的な平等には反するけれど,ニーズに応じて公平である | 92 | |
| けーきを | 「ケーキを買ってきてあげること」というのが,必要不可欠なことではなく,一見「オプション」のように見えるところがポイント | 93 | |
| げんだい | 現代の緩和ケア医は「冷却」にだけ強いアイデンティティを持たなくてもよい | 62 | |
| こうてき | 公的なサポートが不十分なまま家族にケアの負担を担わせ続ける | 37 | |
| この4ぱ | この4パターンは医療において患者の積極的治療が難しくなってきた場合に取りえる選択肢の説明 | 60 | |
| さきざき | 「先々起こること」を,起こっていないうちから想像して備えるのはとても難しい。ただ,「起こり始めたとき」には,必ず,身体でわかる,見てわかる時期が来る | 65 | |
| 「先々必要になる(かもしれない)ときに備えて,信頼関係をつくっている」と考えると,「待ち」の苦手な医療者(特に医者)には良さそう | 57 | ||
| さんどう | 賛同しかねますが,意識の低下した人の利益よりも,これから生きていく家族の利益のほうが大事だ,と考える人もいる | 177 | |
| じっさい | 「実際になってみると,健康なときに思っていたほど悪くない」文脈 | 156 | |
| しっぱい | 失敗への適応類型 | 59 | |
| してほし | 「してほしい」という意向より「してほしくない」という意向のほうが強く尊重される | 73 | |
| しにゆく | 「死にゆく体を『さわる』」こと | 179 | |
| しのだつ | 死の脱医療化を目指していたら,結局より医療化した | 133 | |
| じぶんに | 「自分にはホントのことを伝えてほしいけど,家族が深刻な病気の場合には本人じゃなくてまず私に教えて」というダブル・スタンダード | 39 | |
| じぶんの | 自分の亡くなる過程を家族や知人に見られるのは嫌だと意思表示していた患者 | 172 | |
| しぼうち | 死亡直前の意識混濁のある患者で,うんうんうなっているときに行うべき緩和ケア | 144 | |
| しゅうき | 宗教がないか反宗教の人は鎮静を選択しやすいという国際文脈でのメタ分析 | 31 | |
| しゅうま | 終末期せん妄の本態は「意識の障害である」 | 143 | |
| 終末期では逆に,「思っていたよりつらい」のほうを聞くことも少なくない気がする | 157 | ||
| 終末期の意識混濁を「せん妄」と呼ぶことそのものにも議論があり | 143 | ||
| 終末期の話は家族が先に聞くものだという習慣 | 34 | ||
| じゅくれ | 「熟練された多職種チームがいなければ豊かに死ねない」みたいな世界がつくられつつあるということ | 132 | |
| じょうど | 「情動レベルでの意向」を取り入れて意思決定していく | 153 | |
| しょくぎ | 職業的アイデンティティの危機 | 74 | |
| しんたい | 身体的苦痛と精神的苦痛が一体化するっていうところが終末期の苦痛の特徴だしねぇ | 112 | |
| しんぱい | 「心肺蘇生は絶対にしてくれるな」と言っていた終末期のがん患者さんが不整脈で倒れて搬送中に「心肺蘇生しますか」と聞くと頷く | 147 | |
| 心肺蘇生不要の指示(DNAR指示)について同意を得た瞬間から,心肺蘇生以外の治療やケアについても十分な対応がなされなくなる | 187 | ||
| すこしは | 「少し早い時期」に持続鎮静を希望する患者さんに悩むという臨床現場の声が増えてはいる | 125 | |
| すしやに | 寿司屋に来たなら寿司が大好きで来るんだろう | 82 | |
| ぜんじん | 全人的医療とか大きな風呂敷を広げても,モンブランの願いがかなわないならちょっと虚構を感じます | 95 | |
| そのかぞ | その家族も患者の人生の一部 | 43 | |
| そのきさ | その気さえあれば抗がん剤を世界中から取り寄せできる世の中に驚くが | 48 | |
| そのとき | そのときの顔を見られたくない!って,京さんはあんなに言ってたじゃないですか!! | 170 | |
| それなり | それなりに出番があったと喜んでしまうところが医者としての悲しい業というもの | 85 | |
| だいたい | 「代替療法の相談に乗ってくれた」が「希望を持ちながら心残りのないようにできた」ことに関係していた | 49 | |
| たしゃか | 他者から与えられた線引きに沿って行うケアは自ら考えることを放棄した「業務的」なものになってしまい,それは結果としてケアの質を下げてしまう | 101 | |
| たっせい | 達成できなかったとしても肯定的な意味を持たせる装置がもともとは医療の外に多くあった | 62 | |
| ちょっか | 直感的に正しい(妥当だ,頷ける) | 151 | |
| ちんせい | 鎮静には何種類かある?の歴史的経緯 | 122 | |
| 鎮静の場合,そういうプラスを享受する意識そのものを喪失してしまう | 117 | ||
| 「鎮痛薬を使わないほうがトータルの苦痛は少ない!」という気づきというか境地 | 77 | ||
| つうじょ | 通常診療を超えた範囲での治療の相談に乗る | 49 | |
| どうして | 「どうして今くらいの痛み(苦痛)でいいか」を聞くのが最初の入り口 | 69 | |
| 『どうして具体的な時間の目安が必要ですか』ってふわっと聞いてみたら | 4 | ||
| どうやら | どうやら世界にはいくつかの鎮静の類型のようなものがあるのでは? | 121 | |
| どのはん | どの範囲なら職業としても継続できるかを自分で問い直すこと(戦略的限定化) | 105 | |
| なぜそこ | なぜそこまでして(本人が希望していない)痛みの治療を追求するのか | 75 | |
| なにもす | 何もすることはありませんと言われた | 49 | |
| なんかほ | なんか,堀さんから求められている役割を果たそうとしていくとこうなっていくんだよねぇ…… | 48 | |
| なんとか | なんとか苦痛に耐えられるようにと医療者が一生懸命になること自体を煩わしいと思う価値観の人がいる | 137 | |
| にほんご | 日本語であきらめる(諦める)というのは(真理を)明らかにするという意味もあって | 62 | |
| にほんの | 日本の社会制度が「何かあったらまず家族でなんとかしてね」という発想で組み立てられている | 38 | |
| にゅうい | 入院してる人みんなに公平にしなきゃって言うんです!! | 89 | |
| はふだん | は? 普段から寝てるときはこんな顔ですけど | 145 | |
| はやくい | 早く医者に連れて行けばよかった,私がストレスかけたからだ | 23 | |
| ひこくに | 被告人になった途端に「罪人」扱いしてしまうのもその1 つでしょうし,死にゆく過程のなかで,死が近づくと「死者」のように扱われてしまう,というのもその1つだと思います | 186 | |
| びょうど | 平等(equality)と公平(equity)の違い | 92 | |
| ふろうふ | 「不老不死」への欲望を煽る文化が医療のなかでは支配的 | 61 | |
| ほすぴす | ホスピス・緩和ケアは,従来批判してきた延命至上主義の医療以上に広い範囲を医療化することに成功してきた | 133 | |
| ほんにん | 本人の意向は1つの「本音」に収れんするものではなく,ある幅のなかで複数の意向が競合しており | 159 | |
| 本人はそこまでひどいと思っていなくても, 医療者や家族が「こんな状態になってかわいそうだ」と思い込み,そこから「本人はこうしたいに違いない」という憶測を始めてしまう | 159 | ||
| まやくに | 麻薬についての誤解があるから説明すれば患者は内服する――という単純な問題ではない | 70 | |
| みけんの | 眉間のしわ問題 | 145 | |
| みじかい | 短い時間なら笑い話になりやすいうんうん | 145 | |
| みとられ | 看取られる側の患者と看取る側の家族の間の「関係」を支援している | 182 | |
| みとりい | 看取り以前にあらゆるケアは,ケアされる人とケアする人との関係のなかで生じていることなので,どちらかの「持ちもの」ではないはずです | 182 | |
| もういき | 「もう生きている意味がない」などの実存的苦痛 | 127 | |
| もしこん | もしこんなことがまかり通るようなら安心して病院では死ねない | 176 | |
| もしじぶ | もし自分が患者だったら,もし家族だったら一一誰に最初に伝えてほしいか | 34 | |
| やくぶつ | 薬物は害なので何も使いたくありません。完全に自然な状態になれば苦しくないはずです | 67 | |
| やばくな | 「やばくないか」「大丈夫か」「このままいって問題ないか」というざわざわした気持ち | 103 | |
| ようぼう | 容貌のケアは,近年では「アピアランスケア」と呼ばれて, 1 つの大きな領域 | 189 | |
| よげんし | 「予言者」としての役割 | 16 | |
| よげんの | 予言の自己成就 | 14 | |
| よごその | 予後そのものの長さを知りたいとも限らないので,まずは理由を聞け | 5 | |
| よめいは | 余命は言った! ――患者は何も変わらない, とかになりかねないな | 10 | |
| よめいを | 余命を聞きたがると思うんだけど,それは伏せてもらえませんか | 3 | |
| 余命を伝える伝えないの正義論みたいにしなくても | 5 | ||
| りけいは | 理系はこんなに役に立っている(のに,文系学問って何の役に立つの?)という, やや見苦しいアイデンティティ観 | 194 | |
| りんしょ | 臨床試験や治験に対する患者さんのイメージも,一昔前の「人体実験」から,最後のそして最新の治療選択肢の1つ,という見方へと舵を切っている途中 | 52 | |
| れいせい | (冷静に考えて)「もう耐えられない」と表現する患者さんはわりといらっしゃいます | 113 | |
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)
本記事の関連書籍