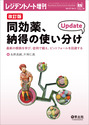- [SHARE]
- ツイート


ウェブで公開された「第0回」をお読みいただいていない方々も多かろう.前口上は全てそこに書いてあるのだが,これを読んでいない読者諸氏はいきなり企画がはじまると面食らうかもしれない.そこで,くり返しになってしまうけれども,簡単に本企画の内容を説明しておく.
「通読できるように作られた医学書の索引を,“市原のオリジナル索引”に作り直して遊びます」.
以上.
余計置いてけぼりになっている人もいるかもしれないが,知ったことではない.さっそくはじめよう.
◆ ◆ ◆
今回のお題は,超人気著者である田中竜馬先生の教科書である.数多くの出版社から本を上梓されている方だが,記念すべき企画第1回の選書でいきなり医学書院の本を選ぶとスーさん(担当編集者)が泣くだろうなと思い,羊土社の本にした.でも別に忖度オンリーで選書したわけではない.非常にいい本である.余談だが,國松淳和先生も本書のことを絶賛していた.
本書を再読して索引項目を揃えるのにかかった日数はわずかに2日であった.この速さで読み終えられることが本書の大きな価値であろう.異常に読みやすい.そもそも研修医は何日もかけて1つの教科書を読む時間をとれないし,仮に満身創痍になりながら一度読み通したとしても,二度目,三度目と読むことができなければ身につかない.何度も読める本というのは多忙な医師にとって,宝物だ.この本はこれからも,何度も読むだろう.
というわけで,今後の再読時に,自分が使いやすいようにこしらえたオリジナル索引を,さっそく皆さんにお目にかけよう.ただし,完全版(完全索引)を掲載するとそれだけで紙幅が埋まってしまうので,一部分だけ抜粋する.全体を見たい人は,ウェブにアクセスして欲しい.別に出し惜しみしているわけではなくて,ほんとうにでかいのだ.
市原のオリジナル索引①
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| Too | Too good to be trueやな | 91 | |
| wind | window hypothesis」β遮断薬の話 続き | 335 | |
| あすぴり | アスピリンはすぐ再開!? | 274 | |
| あにおん | アニオンギャップ | ――で代謝性アシドーシスを見極める | 15 |
| ――の基準値 | 19 | ||
| ――が正常の代謝性アシドーシス | 20 | ||
| ――をアルブミンにより補正 | 21 | ||
| ――が疑いの余地なく高いね | 22 | ||
| あまいこ | 甘い口臭はアセトンの臭い | 32 | |
| あみらー | アミラーゼが上昇する原因 | 359 | |
| あらたま | 改まってどうしたん. | 71 | |
| いきなり | いきなりドッカンとインスリンを投与してはいけない | 3 | |
| いけてま | イケてませんね | 111 | |
| いざ! | いざ! | 187,360 | |
| いつもそ | いつもそう言われます. | 284 | |
| いつもの | いつものことです. | 397 | |
| いやため | いや,試したんやけどな | 120 | |
| いんすり | インスリン | ――の働き | 23 |
| ――の入れ方 | 54 | ||
| えすとろ | エストロゲンによる症状 | 307 | |
| えらくか | えらくかわいらしい名前のRCT | 415 | |
| えらくべ | えらくベタなギャグ飛ばす大阪弁の変な指導医 | 15 |
こんな感じの項目が延々と並ぶ.本連載の冒頭部分,煽り文句のところでは「遊びます」と失言しているが,実際にはおおまじめに,使うときのことをめちゃくちゃ考えて作った.どのようにカスタマイズした索引であるか,これから具体的に解説しよう.
まず,私が今後本書を手繰る際に,「アニオンギャップ」だけで検索しようと思うわけがない.だから,「アニオンギャップ」という項目だけでは索引として不十分だと考えた.
アニオンギャップ——が疑いの余地なく高い症例ってどんなのだっけ?
引き方としてはこうなるはずである.アニオンギャップというコンテンツ名だけでなく,アニオンギャップを取り巻く文脈(コンテキスト)にこそ,未来の私は興味があるはずなのだ.
そこで我がオリジナル索引にはコンテキストの香りを残すことにした.
単語だけではなく,単語にたどり着くまでの流れ,さらには単語から派生した話題や,その際に選ばれた味のある言葉,文脈を思い出せるような特徴あるフレーズを,そのまま索引項目として採用したのである.
市原のオリジナル索引②
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| じゅうし | 重症敗血症は存在しない!? | 207 | |
| しゅうち | 集中治療を志す者にとっては大興奮の出来事 | 87 | |
| しゅうち | 集中治療で,『~はよくするけど,死亡率は下げない』みたいな治療 | 197 | |
| しゅうち | 集中治療医の調整能力も問われます | 337 | |
| しゅうち | 集中治療医の腕の見せどころ | 410 | |
| しゅっけ | 出血性ショック (上部消化管出血:II-第1章) | バイタルサインはどのような順番で変化する | 213 |
| 血圧は鋭敏な指標ではない | 214 | ||
| 何でも中心静脈カテーテルってワケじゃない | 219 | ||
| ――に昇圧薬? | 222 | ||
| 輸液は細胞外液でしたよね? | 223 | ||
| 輸液とかICUでの輸血の話をちょっとまとめとこか | 224 | ||
| 血便をみたときに最初から下部消化管やと決めつけてしまわずに | 232 | ||
| 上部消化管出血と下部消化管出血を区別する | 232 | ||
| ――の原因を絞ろうと思ったら | 241 | ||
| アルコール中毒患者 | 242 | ||
| しゅっさ | 出産後に母乳が出なかった | 161 |
たとえば,「重症敗血症は存在しない?」という項目.「重症敗血症」という単語だけのために未来の私がこの本を検索する機会はおそらくないと思う(あなたはどうか).だから,コンテキストとして,「——は存在しない?」を加える.索引をぱらぱら眺めてこの項目が目に入ると,文脈ごと記憶が蘇り,「敗血症の定義が変わり,かつて重症敗血症と言われていた病態は,現在そのまま敗血症の定義にすっぽり入ってしまっているんだったな」と,内容まで思い出すことも可能だ.
「出血性ショック——における輸液は細胞外液でいいんでしたよね」.文中で研修医が問いかけたことに対して,指導医はなんて答えたんだっけ…….たしか,循環血液量の確保が最優先となるべき場面だから…….
「出血性ショック——血便をみたときに最初から下部消化管やと決めつけてしまわずに」.そうだそうだ,血便だから絶対下部消化管とは言い切れないのであった.たしか,大量の上部消化管出血があって,それが高速で腸管内を移動してきた場合もあるんだよな.
コンテキストを含めた索引を読むと,本文にたどり着く前にコンセプトが想起される.これが,私なりの,通読型の医学書を実際に通読したあとに役立つ実用的な索引の姿である.
……本書を読んだことがない人にとって,こういう索引はどういう意味を持つのか? 中を読んでいないと面白みは半減するかもしれない.
「ごるぁー」とか,「ジェロニモとか」あたりは,読むとめちゃくちゃわかる.けれども読んでない人にはわからないだろう.
◆ ◆ ◆
索引を作りながら本書を読んでいると,著者・田中竜馬先生が本書を著すにあたり仕掛けた深謀遠慮が少しずつあきらかになってくる.
本書は大きく内分泌編と消化器編からなり,それぞれに章があって,章の中には小項目がある.
第1章 糖尿病ケトアシドーシス・高浸透圧高血糖症候群
8. DKAの治療1
小項目ごとに,必ず,「前半の会話パート」と「後半の解説・まとめパート」が配置される.この構成は本書の強みをうまく引き出していると思う.
最初は,「前半の会話パート」を読んだときに,「最近の出版社はしょっちゅう会話パートを入れるなあ,会話形式って文字数が稼げて著者にとってもラクなんだろうな」くらいのことを考えていた.全く失礼な話である.
ところが,オリジナル索引を作りながら再読してみると,後半の解説パートよりも,前半の会話パートからキーフレーズが多く抽出されているので驚いた.
「そ,そうか,本書は,会話パートに医療現場のナラティブを仕込むことで,単発の医学知識をどんどん横につなげているのか!」
研修医と指導医の2名が,漫才……というか,シチュエーションコントに近い形式で「現場あるある」を対話することで,clinical questionが明確に提示される.とあるclinical settingで研修医が考えるであろうこと,指導医が気にするであろうことなどが,わかりやすく読者に示される.必要な知識を後半のまとめパートでおさらいし,side noteでさらに一段深める.
まとめパートだけ読めば学術的な内容は手に入る.しかし,通読型の索引として抽出したくなるのはむしろ前半の「会話パート」のほうだ.なぜならそこには強力なナラティブ(物語)がある.医療現場のナラティブが教科書のコンテキスト(文脈)を支えているのだ.
市原のオリジナル索引③
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| またっ! | またっ! | 186 | |
| またなに | また何かいい加減な言葉つくりましたね | 409 | |
| みゃくあ | 脈圧が小さいっていうのも | 133 | |
| めっちゃ | めっちゃくさい液やったらしい | 245 | |
| もやもや | モヤモヤ感がハンパじゃない | 202 | |
| もんみゃ | 門脈圧亢進 | ――の機序 | 302 |
| ――と門脈体循環シャント | 304 | ||
| 過剰な輸血は――を悪化させる恐れ | 314 | ||
| ――に対するβ遮断薬の作用 | 331,335 | ||
| りゃくし | 略してDKA | 22 |
私は索引を作りながら次第に考え込んだ.この会話,大阪弁でゆるゆると進められているが,実際ものすごく計算されている.クリアカットに答えの出ない,集中治療領域ではいまだcontroversialな部分が,会話でうまくフォローされている.研修医はある場面でこう言った.
「モヤモヤ感がハンパじゃない」
最新のエビデンス,あるいはガイドラインも絶対ではないのだという現場の肌感覚が,親しみやすい会話パートにきちんと練り込まれている.
市原のオリジナル索引④
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ばんとよ | 「バン」と読むとハンバーガーのパンの部分のこと | 238 | |
| ひとこと | ひと言で言うと,まあひと言では言いにくいんやけど | 86 | |
| びょうり | 病理医 | 181 | |
| ぴろりき | ピロリ菌を除菌 | 274 |
「一言で言うと,まあ一言では言いにくいんやけど」
本書はやはりただものではない.数々のシチュエーションで研修医を悩ませる輸液,副腎クリーゼや甲状腺クリーゼのような国家試験的疾患に対する“血の通った”対処方法,集中治療室での基本「A,B,C」がくり返し語られる教育的展開…….
市原のオリジナル索引⑤
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| はいけつ | 敗血症 | ――は『medical emergency』 | 156 |
| ――でのステロイド治療 | 195 | ||
| はいけつ | 敗血症性ショックで血圧が保てんかったら(ステロイドを)使ってもいいよ | 186 | |
| はいけつ | 敗血症性ショックでの輸血の目標 | 229 | |
| はいどう | 肺動脈楔入圧とは? | 325 | |
| ばっかん | 抜管してもいいですか? | 345 | |
| はらへっ | ハラ減った | 26 | |
| はらをわ | 腹を割って話してみませんか | 186 |
二度は読んだはずの教科書に深く練り込まれたナラティブを知って私は「索引を勝手に作ること」の魔力に取り付かれてしまった.このペースで毎月,すぐれた通読型医学書を読み直していったら,なんだか,とてもおもしろいものがいろいろと見えてくるのではないだろうか?
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)