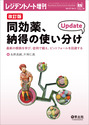- [SHARE]
- ツイート


第3回.本企画の担当編集者のスーさん(薄幸そう)をして,「こんな本を作れる編集者になりたい」と言わしめた本である.帯の口説き文句にぐっとくる.「現代を生きる外科系医師に!」
よし,私もこう見えて「外科病理」に携わる人間であるぞ.だったら読んで損はないだろう.
ところがパラパラとめくってみると,ガイドラインや切除範囲診断など,病理に関係がありそうな内容はほとんど,というか全く出てこない.これはもしや,手技とか処置のことを書いた本なのかな?正直,少し気後れしてしまう.表紙のフォントの中にメスや鑷子があしらわれている点も象徴的だ.
病理医というのは解剖以外の手技をほとんど行わない職種である.いわゆる「修行」の末にたどり着くような,「条件反射」,「神の手」,「徒弟制度で叩き込まれる匠の技術」にはとんと縁が無い.うーむ,これ,私が読んでいい本なのだろうか.
執筆者のお名前を表紙の折り返しに見つける.お二人とも形成外科医である.一般的な外科医が書いているわけでもない,あぁ,後ずさりする歩調が早まっていく.
◆ ◆ ◆
おっかなびっくり読み始め,一時間半.
……私は大喜びでTwitterに投稿していた.「すごい本を見つけたぞ!」さっそくもう1冊購入して当院の初期研修医室に寄贈する.多くの若手医師にぜひ読んで欲しい.読む前になぜあれほど躊躇していたのか,自分の不明を恥じるばかりだ.これぞ,教科書.克誠堂出版さんってすごいな.最初,「知らない版元だ」と死んだ目をしたシンジ君みたいなことを言ってどうもすみませんでした.歴史ある版元で,麻酔や形成外科などの(私が無知な)ジャンルで本・雑誌を多数出版されている.
緊張と緩和のカタルシスに紙幅を使っている場合ではない,そろそろ今回の「勝手に索引」を見ていただこう.いつものように,Webでは完全版を公開.本稿では一部を抜き出して説明する.
市原のオリジナル索引①
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| あんぎお | アンギオソームという概念 | 150 | |
| あんちょ | 安直なポケット版やタブレットのアプリでしか解剖を勉強しない外科医 | 106 | |
| いきてこ | 生きてこそのQOLでしょ | 213 | |
| いたいの | 痛いのは,皮膚と筋膜 | 80 | |
| いと | 糸 | 95, 97 | |
| いとのい | 糸の意図,つまりきれいに治したいという術者のメッセージ | 47 | |
| いんあつ | 陰圧 | ――閉鎖療法 | 120 |
| ――の刺激により肉芽が増殖するメカニズムは完全には解明されていない | 120 | ||
| うたがう | 疑うような沈黙,もう,やめないか | 201 | |
| うみがた | 膿が溜まっている状態に薬を使っても,焼け石に水 | 100 | |
| おんせん | 温泉で創が治るんですか? | 53 |
こうしてまとめてみると索引項目の大半が「セリフ調」だがこれには理由がある.
本書は小説仕立てのストーリーパートと,章ごとに挿入されるイラスト解説・ミニマンガコーナーとで構成されている.登場人物のセリフはもちろんだが,地の文もどことなく散文的で,いわゆる学術書然とした表現はほとんど出てこない.だから索引の語句も自然とやわらかくなる.というか普通こういう本に索引はない.
医学書には「辞書型」のものと「通読型」のものがあるということを,私は本連載の第0回(Web掲載)で述べたが,本書は完全に通読型である.さらに言えば,かつての大学入試センター試験・国語の大問1のような論説ではなく,「大問2」,すなわち物語だ.現場の文脈をゲシュタルトごと与えてくれる形式ということである.まるで我が企画のために書かれたような本……というと自意識過剰だけれども,「文脈を思い出すことで芋づる式に知識を取り出せるような索引を作る」という本企画にとって,医療現場のナラティブがセリフ形式で書かれた本ほどマッチするものはない.
もっとも,小説+マンガだからいい本だと安直に結論したいわけではない.どうせ読者諸氏はそろそろ鼻白んでくるころだろう.「医療現場を小説仕立てにした本? あーなんかもう想像つくからいいよ」「マンガでわかる? そういうのさんざん読んだよ」「ヒマでしょうがないときにさらっと読んでやってもいいけど」くらいの方もいらっしゃるのではないか.
そういう方と私は,たぶん気が合うと思う.私も,読者の知能を低めに想定した教科書が嫌いだ.そして,だからこそ,私が本書を読了したあとに作った索引には本気で目を通して欲しい.この本が「安易な教科書」だったら,たとえばこんな索引項目は作れないと思う.
市原のオリジナル索引②
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| はかくと | 「破格」とされた多くの事象が,術者の勘違いであった | 106 | |
| はくり | 剥離 | 鞘,膜,疎性結合織,ここで剥がせば――は簡単だ | 35 |
| 適度な牽引で――すべき線が見えてくる | 34 | ||
| ヘルニアは膜の――,血管は鞘の―― | 36 | ||
| みかんを剥くのも――と一緒 | 37 | ||
| ――の道具 | 39 | ||
| はっきん | 薄筋で骨盤底の支えを作って,皮島部分で皮膚欠損の再建,なるほど | 144 | |
| はっぽん | 八本入りのコントロールリリースの糸が一本足りなくてもう一パック出したり | 96 |
「剥離」にこれだけ興味を惹かれることが病理医の日常にどれだけあるだろう?まさかの「手技の説明」に感動し,索引として抽出してしまうという誤算.読ませる,考えさせる,うーん,テクい!
とはいえ,「剥離」でみかんの話かよ,などと,まだイマイチ信用していない(私に似た)読者諸氏には,こちらもご覧頂きたい.
市原のオリジナル索引③
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ばんそう | 伴走者の襷 | 237 | |
| ひつよう | 必要な組織をデザインする | 144 | |
| ひべん | 皮弁 | 植皮ができない場所を塞ぐ場合やそのまま縫うと緊張が強い場合に覚えておくと役に立つ | 133 |
| ポートやペースメーカーなどの露出,抗癌剤の点滴漏れによる皮膚壊死などにも有効 | 133 | ||
| ――の形にルールはあるんですか? | 134 | ||
| 局所――の適応 | 137 | ||
| ――の種類 | 137 | ||
| ――血流あれこれ | 140 | ||
| 最終的には遊離―― | 144 | ||
| 筋――のこと,ちゃんと理解してる? | 145 | ||
| 茎が長いひまわり(花が――)のようなイメージ | 145 | ||
| 遊離筋――は台木に穂木を繋ぐ接ぎ木のイメージ | 145 | ||
| 有茎移植では,被覆したい場所が――の末梢端,つまり最も血行が悪い部分になるのが欠点 | 145 | ||
| ふきぬけ | 吹き抜け骨折や頬骨骨折の診断にはCTが有効 | 110 | |
| ふくしは | 複視はないか? 上口唇や歯茎のしびれは? 開口制限や咬合のずれは? | 110 | |
| ふつかめ | 二日目のカレーを常温で置いておく | 119 |
いやいやいや……と(読んでない人は)ツッコむだろう.「皮弁」にのめりこみ過ぎである.ぶっちゃけ自分でも驚いた.でも読んだ人は納得するはずだ.「皮弁に感動するよね」「患者の傷跡についてめちゃくちゃイメージしやすくなるね」「皮弁の適応までスッと思い浮かぶようになるよね」.
創処置,瘻孔,軟膏……そして,メス,糸.
「外科の人間が『修行』の末に身につけるものであり,病理医には一切関係ない」と思っていた内容たちが,おもしろくてしょうがない.
そもそもこれらは初期研修において多くの医師が知りたいと感じているはずの内容だろう.医学生時代にはほとんど習うことがなく,「現場で慣れるしかない」と言われ,看護師に冷たい目でみられながらコチコチと秒針の音を気にしながら汗をかきながら泣きながら取り組んできた実務の数々.それが見事に物語化され,イメージとして縮約されている.マンガという「解釈に空間を用いる表現」と,小説という「解釈に時間を使う表現」とが,互いの背中を守りながら,「手技」や「処置」といったこれまで後輩に伝えることが難しかった内容を,どでかい船ときらびやかなタックルで正々堂々釣り上げようという松方弘樹的な本.
市原のオリジナル索引④
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| むかしの | 昔のエラい先生は,みんなヒゲだね | 208 | |
| めす | メス | ――の刃の種類 | 25, 29 |
| ――の持ち方 | 26, 30 | ||
| ――を立てたら,この重さを感じることはできない | 26 | ||
| ――先に,上肢全体の重さをどっしりかける感じで,力を抜いて,すぅーっ | 30 | ||
| めんじゃ | 面じゃなくて線での癒合だな | 165 | |
| もののつ | モノの伝え方には,絵や造形のような空間を使うものと,音楽や言葉のような時間を使うものがある | 162 | |
| ゆうりそ | 遊離組織移植の診療報酬は92,460点 | 147 | |
| ラスボス | ラスボスのイラスト | 148 | |
| らっしゃ | らっしゃい | 28 | |
| ラップ | ラップ | 18, 21 | |
| ろうこう | 瘻孔 | ――の治療には三原則がある | 157 |
| ――とはなんぞや | 159 |
ここまで書いてもなお疑心暗鬼の方に向けて,以下を記す.
正直に申し上げて,こういう形式の教科書を考えつく著者は「死ぬほどいる」.私だって,自分が何か本を書こうと思ったときに「定期的にマンガ挟んでもらえたら読者を惹き付けることができてラクだろうな」と何度思ったことか.しかし,本書では小説部分とマンガ部分のクオリティが類を見ないほどに高い.相当な量の本を読んできたが,「稀有」だと思う.
なぜここまで高次元のハーモニーを達成できたのか.あくまで本書の場合だが,職業小説家やマンガ家を介さずに,ガチの医師2名が小説パートとマンガパートを自分で創作しているというのがキモだと思う.私は何度も奥付を振り返ったりググったりしながら,「この人たちはもしや“元医師”で,今はプロの小説家とかプロのマンガ家だったりしないのかな?」と確認した.担当した編集者はきっと原稿を見て泣いただろう.
異常に文章が美しい寺尾先生.医療現場のナラティブを小説的ナラティブと重奏させるための,モチーフの選び方にほれぼれする.表現が巧みなのにいやらしさがない.すごいな.テレビドラマの脚本とか普通に書いてそう.

ここで細かいけど重要なポイントを1つ指摘しておく.小説の序盤にある登場人物表を見て,「なんか知らん名前がいっぱいだなー」と軽く引いたあと,本を読み終わってもう一度登場人物の一覧を見て,「全員わかるぜ!」と喜べる.これ,案外珍しいと思う.キャラクタに血を通わせてないと無理.プロの作家が書いても時折やらかしている(失礼).その点,この本は人物一人ひとりが生きている.血流が通っている.例えるならば,きちんとデザインされた皮弁だ.皮下組織からの血流を「ディレイ」で利用するように,バックグラウンドをきちんと描いて「血を通わせてから」,最終章で「概念編」を語る構築のうまさ!
その寺尾先生を,199ページのイラスト内で「ホントいろいろよく知ってるなー」とメタにほめたたえる去川先生がまたすごい.「えっ,マンガの監修してるわけじゃなくてご自身で描かれてるの?」と二度見してしまう.ご本人いわく「戯画」とのことだが,愛着の湧く絵柄と正確な描写はもちろん,間合いと目線(作者,読者,そしてマンガの登場人物すべて)とが絶妙で,文章とは違う角度から「外科センス」を見事に描き出す.形成外科医としての視点をイラストレーションに溶け込ませることは,プロのマンガ家にとっては難しいだろう.プロの形成外科医だからこそできることだ.
◆ ◆ ◆
索引に「相葉(あいば)」が入っている理由,これはもう,読んだ人にしかわからない.読了した人がいるなら握手をしよう,その人はあるいは「茉奈」とか「優香」を索引に入れたいとゴネるかもしれないが,それはそれで「わかる」,私たちはきっとわかり合える.
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)