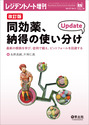- [SHARE]
- ツイート


第2回として選んだ「通読型の教科書」は,循環器内科医の本である.心エコーの本だ.知人にこのことを告げると,さすがにみんな驚いた顔をした.一人はこう言い放った.
「心エコーの勉強する病理医だって? いったい何が目的なの?」
もはやサイコパスの犯人に語りかける私服警官みたいな言い方である.
◆ ◆ ◆
病理診断医は普段,人体から取り出してきた動かぬ一部分(検体)もしくは動かぬ全部(死体)を対象として仕事をしている.その意味で,心臓や血流といった「動くモノ」については専門外,とみなされていることも多い.しかし,顕微鏡ばかり見て,生体ダイナミズムのことを全く知らなくてもいいとは思わない.あまり知られていないが,病理学の成書は循環機能やショックの項目にかなりの紙幅を割いている.そもそも,循環器を知らずして剖検報告書を書くというのは無理だ.命に関わる疾患の何割が循環器由来だと思う?
別に剖検に限った話でもない.我々の大事なクライアントである臨床医と日常的に仕事をしていこうと思ったら,彼らが修めている学問,さらには彼らが大事にしている価値観を全く知らないままでは話にならない.臨床医が外来で患者と対話する上で「ある種のスキル」を必要とするように,私たち病理医も臨床医とコミュニケーションするスキルが求められるが,その根幹にあるのは人当たりの良さや傾聴の技術ではなく(それもあるけど),臨床学問だ.循環器疾患に関する知識は,病理医としてのキャリアを積むうちに磨かれていく.急性冠症候群,肺血栓塞栓症,大動脈解離,弁膜症,各種の心筋炎.
とはいえ,意識しなければ脳に入ってこない知識もある.それは一般に「循環器専門医にまかせておけばよい」と呼ばれる類いのものだ.
臨床各科には俗に「あとは専門医で」と言われるような高次専門領域が存在する.当直マニュアルで,ここまでは当直医が対応しておきなさいとされるラインよりも奥の部分.専門医以外はあまり手を出さない場所.
研修医のみなさんならおわかりだろう.自分が将来進む予定のない科で学ぶものの多くは,いずれは「専門医におまかせ」する部分になる.振り分けるところまでやればよしとされる場所.あとは自分の責任からだんだん外れていく.そういうものが,医療の中には山ほどある.結局のところ,「ここまではみんなで理解しよう,ここからはプロに任せよう」という線引きが必要なほどに,今の医療は複雑になりすぎている.無数の線がもたらしたものは分断である.
手術前に患者がさまざまな専門科に「かけられる」ところを目にする.HbA1cがちょっと高いと糖尿病内科医に,血液サラサラの薬をちょっと飲んでいると循環器内科医に,呼吸機能が悪めだと呼吸器内科医に「かけられて」,患者はあらゆる専門科の意見の間に埋没する.
それが悪いとは言わない.ただ,他科の医者に患者を押しつけるならばせめて,そこで何が行われているのかを知ろうとするくらいはやっておいたほうがよいのではないか?
◆ ◆ ◆
循環器領域で私がもっとも「専門医にまかせっきりだった部分」がある.それは心不全だ.「えっ,そんなポピュラーな疾患が?」と笑われてしまうかもしれない.やはり病理医というものは,臨床医の心は全くわかっていないのだなと,あざけられてしまうかもしれない.
しかし,私は今こそ,世に棲む医師のみなさんに尋ねたい.そこの消化器内科医,そこの整形外科医,そこの皮膚科医,そこの耳鼻咽喉科医の諸君,あなたがたは本当に,心不全を理解しているか?Forrester分類に合わせて治療方針を考える「以上」のことをどれだけ勉強しているか?
私は,サルコイドーシスやアミロイドーシス,肥大型心筋症のように「病理と交差する領域」の循環器内科疾患については勉強してきたし,病理解剖の原因となるような肺血栓塞栓症,大動脈解離,さらには心筋梗塞についても,現場で必要に駆られて,ヤマイのコトワリを考え続けてきた.しかし,心不全こそは,循環器内科医に任せっきりだった.慢性心不全で投薬中の患者が別の理由で(最も多いのは癌だ)病理に「かけられる」とき,私は心不全に付随する種々の病態に目を向ける必要がないまま,「形態学でシロクロを付けられる病理組織の部分」の評価だけを行い,患者を主治医の元に返していた.そういう疾患だと思っていた.それで十分だったと思っていた.
「心不全を避けて通っている」のは,私だけか? ほかの病理医は? 他科の臨床医は? 研修医諸君,あなた方は?
患者の一部に詳しくなり,一側面においてもっぱら「かけられる」ことは,専門家としての矜持だ.けれども,患者のすべてに思いを馳せることをやめたら,それはもう医師ではない.
市原のオリジナル索引①
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| しんふぜ | 心不全 | 急性――において最初にプローブを当てただけでどこまで心不全がわかるか | 324 |
| 急性――の病態が2分でわかる! | 324, 329 | ||
| P-Vループで(慢性)――を読み解く | 342 | ||
| ――では症状そのものが症候群の中心的な構成要素 | 154 | ||
| ――は「心臓+血管系+神経体液性因子(交感神経系,RAAS系)」の全身疾患 | 156 | ||
| BNP,NT-proBNP値の――診断へのカットオフ値 | 158 | ||
| ――の基本病態は「うっ血」と「組織への低灌流」 | 162, 330 | ||
| 右室の機能評価は難しいが,右室の拡大の有無だけでも評価すべき | 162 | ||
| 急性――と慢性――は区別して考える | 164 | ||
| 急性――と慢性――では検査の目的が異なる | 277 | ||
| 急性非代償性――が急性――の多くを占めます | 164, 345 | ||
| EFを指標とした――分類(HFpEFとHFrEF) | 166 | ||
| HFpEFの頻度は過小評価されているのかもしれません | 168 | ||
| HFpEFの予後はHFrEFより悪くはなく,どちらかといえばやや良好といえそう | 168 | ||
| EFが40~50%の心不全(HFmrEF)はHFrEF,HFpEFと異なった特徴があり | 171 | ||
| はじめはEF≦40%であった例が治療によってEF>40%に改善した――症例 | 173 | ||
| 予後の評価について最初のEFよりも改善後のEFが関係する | 174 | ||
| ――の重症度評価の指標(表) | 176 | ||
| NYHA心機能分類(特に慢性心不全の重症度評価) | 177 | ||
| Killip分類はあくまで急性心筋梗塞の重症度指標であり,急性――に適応するときには注意 | 178 | ||
| Forrester分類が優れているのは――の評価に留まらず,治療方針の指標となる点 | 179, 298, 330, 333 | ||
| Nohria-Stevenson分類は「2分間で」――の重症度が評価できる | 181, 279, 340 | ||
| “Cold and Wet”の症例は特に予後不良 | 183 | ||
| 急性――の発症早期の病態を評価し,適切な治療を選択するためにクリニカルシナリオ | 183, 279, 333 | ||
| 最重症の――の分類にはINTERMACSプロファイル | 185 | ||
| 急性――では詳細な病因の解明より迅速な血行動態の評価が優先 | 278, 280 | ||
| 慢性――とは心臓だけの疾患ではなく全身疾患であり | 278 | ||
| 急性――の治療方針 | 282, 333 | ||
| 慢性――では必ずしも循環血漿量が過剰であるとは限りません | 288 | ||
| 急性――での右心機能の評価 | 378 | ||
| しんふぜ | 「心不全なら利尿剤打っときましょう」「脱水だよ!」 | 163, 297 | |
| しんぼう | 心房細動 | ――での心機能評価 | 250 |
前回,Dr.竜馬1)の教科書には多数の疾患が登場したので,索引項目も多彩となった.しかし今回,Dr.岩倉の教科書に「勝手に索引」を作ってみると,その様相は前回とだいぶ異なることに気づく.本書に掲載されている疾患の数自体はさほど多くない.なにせ本書の紙幅の後半50%がすべて心不全に関する記載で占められているくらいだ.したがって,索引もこのようになる.サブ項目が広くなる.

生まれてはじめて,こんなにまじめに心不全の勉強をした.本書の狂言回しは,心エコーという「時間分解能が最強である臨床画像モダリティ」.これが実に効果的である.時間軸を俯瞰する必要がある疾患の代表である心不全を深く学ぶにあたり,媒介ツールとして心エコーをかたわらに置いていることが効いている.私は,ようやく! ようやくHFrEFとHFpEFを理解した!
市原のオリジナル索引②
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| Dだいま | D -ダイマー | ――が正常値であれば急性の肺血栓塞栓症や深部静脈血栓症の可能性は非常に低い | 122 |
| ――は年齢とともに検査の特異度が下がり,80歳以上では10%程度になる | 122 | ||
| EF | 左室駆出率(EF) | ――とは心臓がいかに効率よく作動しているかを示す指標 | 189 |
| 循環血漿量(前負荷)や血管抵抗(後負荷)の影響を含めた循環系の状態を把握できる | 198 | ||
| 肥大心や心アミロイドなどの左室容積の縮小を伴う心不全例では――では収縮能を過大評価してしまう | 300 | ||
| ――=心拍出量と単純に考えない | 330 | ||
| Emax | Emax | ――なんて臨床で役に立たないぞ そうだ! そうだ! そうだ! そうだ! | 284 |
| ――は負荷によらない収縮能の指標 | 307 | ||
| FOCU | FOCUS | 心エコーを専門としない救急医のための――では各断面から左室収縮能を三段階で評価する | 43, 198 |
| Fran | Frank-Starlingの法則 | 250, 285 | |
| ――の一番わかりやすい例は,利尿や輸液による循環血漿量の変化が心拍出量あるいは血圧に与える効果 | 288 | ||
| ショックの病態と―― | 291 | ||
| 傾きが心臓の収縮能によって変化する | 296 | ||
| Forrester分類を――で考える | 298 | ||
| ――の最大の限界は後負荷の効果をうまく扱えないこと | 301 |
正直に言うと私はFrank-Starlingの法則もP-Vループも全く理解していなかったし,それでもいいと思っていた.「だって病理医だぜ」.病理医が左室拡張末期圧について理解することが何になる.でもこれらをわからなければ,結局心不全のことはよくわからないのだ.
高校時代に,「微分積分やら基礎物理やらを勉強して将来役に立つのかよ」と毒づく同級生を見て,「黙ってやればいずれ役に立つんじゃないのかなあ,こういうのは……」ともくもく受験問題を解いていたときの記憶を思い出す.そうか,心不全とは社会・国語のように学ぶものではなく,数学・物理学として学ぶものであったか.
市原のオリジナル索引③
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ないけい | 内頸静脈圧は中心静脈圧とほぼ等しい | 159 | |
| にとろを | 「ニトロをのんだら30分できいたのよ」 「ほお~」 | 41 | |
| にゅうと | 乳頭筋断裂 | ――は血圧の低下や急性の肺うっ血で発症 | 98 |
| 後乳頭筋は右冠動脈の一枝のみから血流を受けるため,――はほとんどが下壁梗塞 | 98 | ||
| 弁尖はムチ状の動き(frail valve) | 99 | ||
| ――では僧帽弁閉鎖不全の程度に対して左房の拡大を認めないのが特徴 | 99 | ||
| はいうっ | 肺うっ血 | ――はなぜ起きるのか | 230 |
| ――が高度で肺の含気が減少するほどBラインの数は増加します | 325 | ||
| ――の評価はE/e'やPR-PGで評価するのが基本 | 330 | ||
| はいけっ | 肺血栓塞栓症 | ――の胸痛の特徴 | 42 |
| ――の可能性を示唆するFOCUS | 44 | ||
| ――の胸痛は末梢肺動脈の閉塞から生じた胸膜の炎症によるもので「胸膜痛」/e'やPR-PGで評価するのが基本 | 119 | ||
| 中枢肺動脈が閉塞した場合,狭心症様の前胸部痛が生じることがある | 119 | ||
| Dダイマーが正常値であれば急性の――や深部静脈血栓症の可能性は非常に低い | 122 | ||
| Dダイマーは年齢とともに検査の特異度が下がる | 122 | ||
| ショックがある場合の心エコー | 123 | ||
| 右室拡大があり血行動態が安定していない場合は心エコーの結果だけで治療を開始してよい | 123 | ||
| リスク評価(右室の収縮能低下は――の重要な予後不良因子) | 123, 134 | ||
| ――の心エコー所見 | 125 | ||
| ――が疑われた症例に血管エコーで下肢近位側に静脈血栓を認めた場合 | 129 | ||
| ――が疑われる状況での静脈圧迫テスト(4点圧迫法) | 130 | ||
| 下腿の深部静脈の存在だけでは必ずしも――を示すものではない | 132 | ||
| 救急の心エコーでの筆者のスクリーニング法 | 134 | ||
| はいけっ | 肺血管抵抗の推定 | 274 |

本書は別に心不全のためだけの教科書ではない.胸痛疾患で病院に訪れた患者にどこまで心エコーで評価するか,最低限何を計測しておくと役に立つか,という「いかにも研修医が喜びそうな」知識も豊富に掲載されている.心筋梗塞の評価法,肺うっ血や肺血栓塞栓症についても,きちんと学べてお得な本だ.
それでもやはり読後感としては「心不全をやりきった」という感覚が強い.うーんいい教科書であった.第3章はぶっちゃけ読むのに死ぬほど時間がかかった.高校3年間の数学をいちから勉強しなおして最後に偏微分を理解せよと言われているようなものだ.見てくれこの付箋の数と,そこににじんだ私の心の叫び声を.
くり返すがこの本の後半50%は「心不全」である.ずーーーーっとしんどい! 延々と素材集めが続く! そして思わず付箋に書いた「美しい」(297ページ).素材が全部集まってそれらを組み合わせて心不全の真髄が語られるこのページで私はカタルシスを覚えた.そこからさらに27ページほど読み進んだ324ページでは思わず漏れる「ここのために!」
市原のオリジナル索引④
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| せっかい | 「石灰化の偏位ね」「かっぽれ かっぽれ」 | 106 | |
| せぶんい | セブン,イレブン,LMT | 傍胸骨左縁短軸像での―― | 76 |
| ぜんふか | 前負荷・後負荷をどのように推測するか | 340 | |
| そうぼう | 僧帽弁の収縮期前方運動(SAM) | 146, 147 |
前回と同様,できればフルバージョンの「勝手に索引」も見てみてほしい.ちょいちょいヘンなフレーズが紛れ込んでいるが本書をお持ちの方であればわかるだろう.「そこを索引にしたくなるワケ」がつたわると思う.しんどくて爽快,つらく苦しく快感,まるで登山のようなドクショであった.
文 献
- 『Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 内分泌・消化器編』著/田中竜馬,羊土社,2017
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)