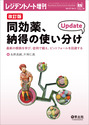こちらも御覧ください!
誌面掲載全文を見る
市原のオリジナル索引
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| 16 | 16分画でも17分画でも差はありません | 66 | |
| 17 | 17分画モデル | 66 | |
| CO | 心拍出量(CO) | ――と左室駆出率は,お互いが補い合う指標 | 190 |
| ――の計測精度は左室流出路経およびTVIの正確さで決まる | 190 | ||
| 左室が小さい場合は左室の収縮能から考える以上に――が低下している可能性がある | 327 | ||
| CTO | 慢性完全閉塞性病変(CTO) | 完全閉塞病変で良好な側副血行路があり壁運動も正常な場合,――の可能性 | 81 |
| 局所壁運動の消失した領域が周囲の収縮に引っ張られた動きを示す | 83 | ||
| Dだいま | D -ダイマー | ――が正常値であれば急性の肺血栓塞栓症や深部静脈血栓症の可能性は非常に低い | 122 |
| ――は年齢とともに検査の特異度が下がり,80歳以上では10%程度になる | 122 | ||
| EF | 左室駆出率(EF) | ――とは心臓がいかに効率よく作動しているかを示す指標 | 189 |
| 循環血漿量(前負荷)や血管抵抗(後負荷)の影響を含めた循環系の状態を把握できる | 198 | ||
| 肥大心や心アミロイドなどの左室容積の縮小を伴う心不全例では――では収縮能を過大評価してしまう | 300 | ||
| ――=心拍出量と単純に考えない | 330 | ||
| Emax | Emax | ――なんて臨床で役に立たないぞ そうだ! そうだ! そうだ! そうだ! | 284 |
| ――は負荷によらない収縮能の指標 | 307 | ||
| FOCU | FOCUS | ―― | 43 |
| 心エコーを専門としない救急医のための――では各断面から左室収縮能を三段階で評価する | 198 | ||
| Fran | Frank-Starlingの法則 | ―― | 250, 285 |
| ――の一番わかりやすい例は,利尿や輸液による循環血漿量の変化が心拍出量あるいは血圧に与える効果 | 288 | ||
| ショックの病態と―― | 291 | ||
| 傾きが心臓の収縮能によって変化する | 296 | ||
| Forrester分類を――で考える | 298 | ||
| ――の最大の限界は後負荷の効果をうまく扱えないこと | 301 | ||
| GLS | GLS | ――は長軸方向への左室収縮能の指標として,非常に注目されています | 212 |
| 各社製品での健常者における――の平均値 | 214 | ||
| ――評価の有用性が報告されている疾患の一部 | 215 | ||
| 肥大型心筋症 | 215 | ||
| 高血圧心 | 215 | ||
| 心アミロイド | 215 | ||
| 大動脈弁狭窄症 | 216 | ||
| 薬剤性心筋障害(抗がん剤など) | 216 | ||
| 虚血性心筋症 | 216 | ||
| 心毒性のある抗がん剤の使用例では,心筋障害の早期検出のために――はできるだけ計測 | 218 | ||
| Hand | Handbook of Echo-Doppler Interpretation | 31 | |
| HFpE | HFpEF | ――の頻度は過小評価されているのかもしれません | 168 |
| ――におけるFrank-Starling曲線 | 297 | ||
| 利尿による血圧低下が起きやすい | 297 | ||
| 前負荷・後負荷とも軽減するACE阻害薬やARBがHFpEFでは十分な予後改善効果が認められないわけ | 321 | ||
| ――のEDPVRは急峻である | 322 | ||
| HFrE | HFrEF | ―― | 169 |
| ――におけるFrank-Starling曲線 | 297 | ||
| ――における薬剤の血行動態への影響 | 319 | ||
| NSTE | NSTEMIでも非常にリスクの高い症例がある | 50 | |
| PCI | 冠動脈インターベンション(PCI)をどの病変に行うべきかに直結 | 81 | |
| P-V | P-Vループ | ―― | 221, 303 |
| ――は心エコーの解釈にしか役に立たないぞ!! ん? | 284 | ||
| ――でこれだけは覚えよう | 307 | ||
| 動脈エラスタンス(Ea)による――の変化 | 314 | ||
| 前負荷による――の変化 | 315 | ||
| HFrEF症例における――の変化 | 318, 323 | ||
| ――の面積拡大は心臓の外に対する仕事量の増加を意味し,病的心にとっては負担 | 318 | ||
| HFpEFにおける―― | 320, 323 | ||
| ――を使って心エコーのデータから心不全の病態を読み解く | 337 | ||
| ――のイメージが「大体」得られたら,それが前負荷・後負荷にどのように影響されているかをイメージ | 340 | ||
| 高血圧心や肥大型心筋症 | 342 | ||
| 心アミロイド | 343 | ||
| HFrEF | 344 | ||
| 僧帽弁閉鎖不全 | 359 | ||
| teth | tethering | 83, 89 | |
| UAP | UAPと局所壁運動異常 | 50 | |
| あーちふ | アーチファクト | 多重反射 | 17 |
| 有用な多重反射 | 20 | ||
| 肺エコーでのうっ血のサインであるBライン | 20 | ||
| 音響陰影 | 20 | ||
| 鏡面反射 | 21 | ||
| 屈折によるレンズアーチ―― | 21 | ||
| サイドローブ―― | 22 | ||
| ビーム幅―― | 22 | ||
| ――鑑別のポイント | 24 | ||
| ――の一覧(表) | 25 | ||
| あえてて | あえて手書きでスケッチ | 13 | |
| いちがた | 「いち型 に型 さん型 よん型」「ちがいがわかるかな~」 | 332 | |
| いっしょ | 「いっしょうけんめい書いたのに」 | 27 | |
| いんせい | 陰性T波 | 特に自覚症状のない前胸部誘導の―― | 13 |
| 心尖部型肥大型心筋症で前胸部誘導の大きな―― | 12 | ||
| うしつき | 右室機能は長軸方向への動きを評価する方がよい | 268 | |
| うしつこ | 右室梗塞でも急性期には必ずしも右室の拡大を認めません | 72 | |
| うしつし | 右室収縮能の低下 | 60/60サイン(三尖弁閉鎖不全の最大圧較差と右室流速路のacceralation time) | 127 |
| McConnell徴候 | 127 | ||
| うしつし | 右室心筋の構造と動き | 259 | |
| うしつへ | 右室への圧負荷は臨床的には左心系の疾患による場合が最も多く,循環血漿量の増加を伴うことが多い | 271 | |
| うっけつ | うっ血の所見としては起坐呼吸および頸静脈圧上昇が重視されます | 183 | |
| うぼうあ | 右房圧 | 下大静脈による――の推定 | 257 |
| 臨床では下大静脈を――の指標として,その拡大・縮小を前負荷の変化と考えることも多い | 288 | ||
| えこーぜ | エコーゼリーの代わりにイソジンゲル | 93 | |
| おおさか | 「おおさか名物 しんまくパンチ」 | 383 | |
| おお,べ | 「おお,べんだぷにあじゃ」「下を向くと苦しいの ゼエゼエ」 | 161 | |
| かいぼう | 解剖学的に説明できないような場合は虚血性心疾患ではないのかも | 83 | |
| かせいし | 仮性心室瘤 | ――では瘤の入り口(頸部)が瘤本体よりも狭い形態を示す | 101 |
| ドプラエコー | 101 | ||
| かだいじ | 下大静脈 | ――による右房圧の推定 | 257 |
| 臨床では――を右房圧の指標として,その拡大・縮小を前負荷の変化と考えることも多い | 288 | ||
| ――の視覚的な拡大および呼吸性変動の消失があれば循環血液量の過剰は確実 | 329 | ||
| ――はForrester分類の参考にはなりますが,前負荷の指標としてはかなり大雑把です | 331, 341 | ||
| かんどう | 冠動脈の解剖学 | ―― | 54 |
| 左冠動脈の解剖学的ポイント | 58 | ||
| 右冠動脈の解剖学的ポイント | 59 | ||
| かんどう | 冠動脈の走行(エコー画像上) | 傍胸骨左縁短軸像での―― | 60 |
| 心尖四腔像での―― | 62 | ||
| 心尖二腔像での―― | 63 | ||
| 長軸像での―― | 65 | ||
| かんどう | 冠動脈病変についての「ストーリー」を作る | 83 | |
| きがいし | 期外収縮で動悸を感じるのは収縮性増強にもよる | 250 | |
| きざこき | 起坐呼吸のため半坐位で心エコー | 48 | |
| きぜつし | 気絶心筋 | 82 | |
| きょうつ | 胸痛 | ――の診断では,検査時にも胸痛が持続しているかどうかが重要 | 15, 50 |
| 20代で非典型的な――なら拡張能などは詳しく見ません | 26 | ||
| ――疾患で救急外来を受診した症例のうち,循環器系疾患は50% | 37 | ||
| カナダでの――の原因疾患(表) | 38 | ||
| 島根での――の原因疾患 | 37 | ||
| まずは三大疾患から考えていくべき | 38 | ||
| 急性心筋梗塞のうち――が主訴であったのは50%強 | 39 | ||
| ――の特徴と所見の陽性尤度比 | 40 | ||
| ――の性状 | 42 | ||
| ――改善後も壁運動異常が持続する場合 | 51 | ||
| ――が続く場合の心エコー | 51 | ||
| きょけつ | 虚血カスケード | 52 | |
| きょけつ | 虚血性心疾患 | 局所壁運動の評価 | 50 |
| きんちょ | 緊張性気胸 | 肺エコーを使うことで診断 | 150 |
| 高周波のリニアプローブが適する | 150 | ||
| lung slidingの消失 | 150 | ||
| けいきょ | 経胸壁3D心エコー法 | どのような場合に「あえて」使うべきかがわからない | 205 |
| こうふか | 後負荷 | ――とは「心臓が血液を駆出するときに打ち勝たなければいけない負荷」を意味します | 313 |
| なぜ――上昇で肺うっ血が生じるのか | 315, 317 | ||
| 体血管抵抗上昇の所見としては血圧よりも末梢冷感を中心とした“cold”所見の存在が参考になる | 340 | ||
| こきゅう | 呼吸困難が心不全によるものかも初期段階では不明 | 281 | |
| こじんて | 個人的な意見ですが | 218 | |
| ざいでも | 坐位でも頸静脈の拡大・拍動がみられることがあり,この場合は中心静脈圧は20 mmHg以上 | 159 | |
| さしつか | 左室拡大 | 88 | |
| さしつか | 左室拡張能 | IVRTは他の指標で――が評価できないときの補助的な指標 | 225 |
| 左室収縮能が低下している心臓は必然的に――の低下を伴う | 227 | ||
| ――の小さな変化よりも,左室拡張障害の有無を判定することを重視 | 234 | ||
| 左室駆出率(EF)正常と収縮能低下がある場合で診断のフローチャートを分ける | 234 | ||
| 各指標の計測のしかた | 240 | ||
| 慢性的な――障害の可能性を評価 | 328 | ||
| さしつく | 左室駆出率(EF) | ――とは心臓がいかに効率よく作動しているかを示す指標 | 189 |
| 循環血漿量(前負荷)や血管抵抗(後負荷)の影響を含めた循環系の状態を把握できる | 198 | ||
| 肥大心や心アミロイドなどの左室容積の縮小を伴う心不全例では――では収縮能を過大評価してしまう | 300 | ||
| ――=心拍出量と単純に考えない | 330 | ||
| さしつし | 左室収縮能 | ――を評価する各指標 | 188 |
| FOCUSでは各断面から――を正常・軽度低下・高度低下の三段階で評価することが推奨 | 198, 327 | ||
| GLSは長軸方向の――の指標として,非常に注目されています | 212 | ||
| 日常臨床ではどの指標を用いるか | 218 | ||
| 高度の僧帽弁閉鎖不全が持続すると――は過大評価される | 290 | ||
| ――が低下した症例や局所壁運動異常を認める症例では心不全の原因が虚血によるかどうかを判定する | 327 | ||
| さしつは | 左室は心筋線維が基部から心尖へとらせんを巻くようできています | ―― | 199 |
| 右利きの人がタオルを絞るのと逆向き | 212 | ||
| さっぱり | さっぱりわからんがありがたや | 30 | |
| さぼう | 左房 | 非常に大きな――は拡張障害よりも僧帽弁疾患や慢性心房細動の結果であることが多い | 328 |
| しかんと | 弛緩とはエネルギーを必要とする能動的な過程です | 222 | |
| じゆうへ | 自由壁=対角枝領域 | 58 | |
| しょくど | 食道疾患 | ――の胸痛の特徴 | 42 |
| しょけん | 所見 | ――を書くときにはそれが次に検査をする人にとっての | 14 |
| 重要な――をその場で声に出してスタッフに伝える | 15 | ||
| を読んだ医師の多くは | 26 | ||
| ――の文中にもキーポイントあるいはサマリー | 28 | ||
| 非専門医に対しての書き方 | 29 | ||
| 面白い―― | 30 | ||
| しょっく | ショック | 急性心筋梗塞に伴う――の原因 | 90 |
| ――を伴う症例をみた場合には「機能的合併症の可能性もある」 | 91 | ||
| ――症例では心膜貯留が少なくても自由壁破裂の可能性は除外できない | 92 | ||
| 肺血栓塞栓症の診断ステップを――がある場合とない場合に分ける | 123 | ||
| ――ではまず下大静脈を観察し,よほど拡大していない限り十分な輸液を行う | 292 | ||
| しんえこ | 心エコーで大切なのは画像を撮ることではなく, | 31 | |
| しんがい | 心外膜炎 | ――の胸痛の特徴 | 42 |
| じんこう | 人工弁 | ――の評価 | 366 |
| ――ではごく小さな弁逆流の存在は正常で,むしろ血栓予防の効果がある | 374 | ||
| 生理的な弁逆流が突然消失し,新たに中心性の逆流が出現した場合は血栓形成を疑う | 374 | ||
| しんしつ | 心室中隔=中隔(前下行枝本幹由来)領域 | 58 | |
| しんしつ | 心室中隔穿孔 | ――の発症は心筋梗塞発症1日以内と3~5日目が多い | 95 |
| 下壁梗塞例では多くは左室基部の中隔と下壁の接合部に生じる | 95 | ||
| 身体所見が大切ですが,カテーテル前の心エコーによって確実に診断できます | 96 | ||
| 急性心筋梗塞で右室負荷所見が出現した場合,肺血栓塞栓症の合併とともに――も考える | 97 | ||
| しんせん | 心尖部血栓と診断するポイント | 100 | |
| しんたん | 心タンポナーデ | ――では心膜貯留とともに右心系の虚脱と下大静脈の拡大 | 293 |
| しんのう | 心嚢穿刺 | 92 | |
| しんはく | しんはく 心拍出量(CO) | ――と左室駆出率は,お互いが補い合う指標 | 190 |
| ――の計測精度は左室流出路経およびTVIの正確さで決まる | 190 | ||
| 左室が小さい場合は左室の収縮能から考える以上に――が低下している可能性がある | 327 | ||
| しんふぜ | 心不全 | 急性――において最初にプローブを当てただけでどこまで心不全がわかるか | 324 |
| 急性――の病態が2分でわかる! | 324, 329 | ||
| P-Vループで(慢性)――を読み解く | 342 | ||
| ――では症状そのものが症候群の中心的な構成要素 | 154 | ||
| ――は「心臓+血管系+神経体液性因子(交感神経系,RAAS系)」の全身疾患 | 156 | ||
| BNP,NT-proBNP値の――診断へのカットオフ値 | 158 | ||
| ――の基本病態は「うっ血」と「組織への低灌流」 | 162, 330 | ||
| 右室の機能評価は難しいが,右室の拡大の有無だけでも評価すべき | 162 | ||
| 急性――と慢性――は区別して考える | 164 | ||
| 急性――と慢性――では検査の目的が異なる | 277 | ||
| 急性非代償性――が急性――の多くを占めます | 164, 345 | ||
| EFを指標とした――分類(HFpEFとHFrEF) | 166 | ||
| HFpEFの頻度は過小評価されているのかもしれません | 168 | ||
| HFpEFの予後はHFrEFより悪くはなく,どちらかといえばやや良好といえそう | 168 | ||
| EFが40~50%の心不全(HFmrEF)はHFrEF,HFpEFと異なった特徴があり | 171 | ||
| はじめはEF≦40%であった例が治療によってEF>40%に改善した――症例 | 173 | ||
| 予後の評価について最初のEFよりも改善後のEFが関係する | 174 | ||
| ――の重症度評価の指標(表) | 176 | ||
| NYHA心機能分類(特に慢性心不全の重症度評価) | 177 | ||
| Killip分類はあくまで急性心筋梗塞の重症度指標であり,急性――に適応するときには注意 | 178 | ||
| Forrester分類が優れているのは――の評価に留まらず,治療方針の指標となる点 | 179, 298, 330, 333 | ||
| Nohria-Stevenson分類は「2分間で」――の重症度が評価できる | 181, 279, 340 | ||
| “Cold and Wet”の症例は特に予後不良 | 183 | ||
| 急性――の発症早期の病態を評価し,適切な治療を選択するためにクリニカルシナリオ | 183, 279, 333 | ||
| 最重症の――の分類にはINTERMACSプロファイル | 185 | ||
| 急性――では詳細な病因の解明より迅速な血行動態の評価が優先 | 278, 280 | ||
| 慢性――とは心臓だけの疾患ではなく全身疾患であり | 278 | ||
| 急性――の治療方針 | 282, 333 | ||
| 慢性――では必ずしも循環血漿量が過剰であるとは限りません | 288 | ||
| 急性――での右心機能の評価 | 378 | ||
| しんふぜ | 「心不全なら利尿剤打っときましょう」「脱水だよ!」 | 163, 297 | |
| しんぼう | 心房細動 | ――での心機能評価 | 250 |
| しんまく | 心膜炎 | 急性――ではV6誘導でST/T>0.25のことが多く,早期再分極と鑑別できる | 148 |
| 急性――の診断基準 | 149 | ||
| 心筋にまで炎症が拡がった心筋――では壁運動異常を認める | 150 | ||
| 慢性――炎では――貯留があっても心不全が出現しないこともある | 379 | ||
| 急性――炎では容易に拡張不全の症状が出現 | 379 | ||
| 収縮性――炎 | 380 | ||
| せっかい | 「石灰化の偏位ね」「かっぽれ かっぽれ」 | 106 | |
| せぶんい | セブン,イレブン,LMT | 傍胸骨左縁短軸像での―― | 76 |
| ぜんふか | 前負荷・後負荷をどのように推測するか | 340 | |
| そうぼう | 僧帽弁の収縮期前方運動(SAM) | 146, 147 | |
| そうぼう | 僧帽弁閉鎖不全症(MR) | 急性の―― | 358 |
| 慢性の――による心不全の場合は,手術によって改善が期待される例も多く | 359 | ||
| ――に対する手術適応のためのフローチャート | 362 | ||
| 左室拡大を伴う疾患における――は,左室拡大による弁尖の心室側への牽引が主たる原因 | 364 | ||
| 後壁梗塞症例では軽度の左室拡大でも高度の――が発生することも | 364 | ||
| 急性心不全時,――が視覚的に非常に高度,あるいはごく軽度と判定されれば急性期にはそれで十分 | 365 | ||
| そくふく | 側副血行路 | 78, 79 | |
| だいどう | 大動脈解離 | ――の胸痛の特徴 | 42 |
| ――の可能性を示唆するFOCUS | 44 | ||
| Stanford A型, DeBakey I型・II型は緊急手術の適応 | 103 | ||
| 検査のまえに――の可能性をまず考えつくことが重要 | 103 | ||
| 突然発症の激しい胸背部痛が下方へ移動する | 104 | ||
| ――ではほとんどの例で血圧上昇 | 105 | ||
| 石灰化がX線上6 mm以上内側に偏位しているような場合 | 105 | ||
| 経胸壁エコーで大動脈の観察に適した断面(表と図) | 108 | ||
| 多くの場合偽腔の方が真腔よりも大きくなっています | 117 | ||
| 偽腔は拡張期に経が大きくなり | 117 | ||
| 経胸壁心エコーでの――の診断は陰性的中率が低く | 118 | ||
| ――が強く疑われるなら心エコーよりも造影CTなどの実施を優先すべき | 118 | ||
| だいどう | 大動脈弁 | 急性心不全で高度の――変性をみたとき | 347 |
| 有症状の――狭窄症(AS)は手術適応 | 347 | ||
| ――狭窄症(AS)の重症度評価 | 348 | ||
| ――二尖弁での注意点 | 349 | ||
| 急性――閉鎖不全症(AR)では拡張期圧は上昇し急性肺水腫を呈しま | 353 | ||
| 逆流ジェットが太いほど――閉鎖不全症(AR)は重症 | 353 | ||
| たうなん | たうなんてわからなくっても困らないわ | 223 | |
| たこつぼ | たこつぼ心筋症 | ――の古典的な病像 | 135 |
| 入院中のトロポニン上昇は急性冠動脈症候群の方が高値 | 138 | ||
| 当初考えられていたよりも合併症は多い | 138 | ||
| ――では冠動脈一枝の支配領域を越える範囲に局所壁運動障害が存在する | 140 | ||
| 逆たこつぼ | 142 | ||
| ショックを伴う―― | 146 | ||
| 機能性狭窄 | 146 | ||
| 僧帽弁の収縮期前方運動(SAM) | 146 | ||
| たしびょ | 「多枝病変の可能性があること」を常に忘れず | 81 | |
| たじゅう | 「多重反射よ 多重反射よ 多重反射よ」「等間隔だなあ」 | 25 | |
| だんせい | 弾性反跳(elastic recoil)の概念を例で示す(図5) | 227 | |
| ちょうじ | 長軸方向ストレインの実際 | 理論的なことに捉われず,まずは計測してみることを強くお勧め | 213 |
| どS | 「どS’」「イタい イタい」 | 204 | |
| とうみん | 冬眠心筋 | 82 | |
| どこがほ | どこがほんとに痛いの | 16 | |
| どっちの | 「どっちのフローチャートかな」「はやくしてくれ」 | 238 | |
| ないけい | 内頸静脈圧は中心静脈圧とほぼ等しい | 159 | |
| にとろを | 「ニトロをのんだら30分できいたのよ」 「ほお~」!? | 41 | |
| にゅうと | 乳頭筋断裂 | ――は血圧の低下や急性の肺うっ血で発症 | 98 |
| 後乳頭筋は右冠動脈の一枝のみから血流を受けるため,――はほとんどが下壁梗塞 | 98 | ||
| 弁尖はムチ状の動き(frail valve) | 99 | ||
| ――では僧帽弁閉鎖不全の程度に対して左房の拡大を認めないのが特徴 | 99 | ||
| はいうっ | 肺うっ血 | ――はなぜ起きるのか | 230 |
| ――が高度で肺の含気が減少するほどBラインの数は増加します | 325 | ||
| ――の評価はE/e'やPR-PGで評価するのが基本 | 330 | ||
| はいけっ | 肺血管抵抗の推定 | 274 | |
| はいけっ | 肺血栓塞栓症 | ――の胸痛の特徴 | 42 |
| ――の可能性を示唆するFOCUS | 44 | ||
| ――の胸痛は末梢肺動脈の閉塞から生じた胸膜の炎症によるもので「胸膜痛」/e'やPR-PGで評価するのが基本 | 119 | ||
| 中枢肺動脈が閉塞した場合,狭心症様の前胸部痛が生じることがある | 119 | ||
| Dダイマーが正常値であれば急性の――や深部静脈血栓症の可能性は非常に低い | 122 | ||
| Dダイマーは年齢とともに検査の特異度が下がる | 122 | ||
| ショックがある場合の心エコー | 123 | ||
| 右室拡大があり血行動態が安定していない場合は心エコーの結果だけで治療を開始してよい | 123 | ||
| リスク評価(右室の収縮能低下は――の重要な予後不良因子) | 123, 134 | ||
| ――の心エコー所見 | 125 | ||
| ――が疑われた症例に血管エコーで下肢近位側に静脈血栓を認めた場合 | 129 | ||
| ――が疑われる状況での静脈圧迫テスト(4点圧迫法) | 130 | ||
| 下腿の深部静脈の存在だけでは必ずしも――を示すものではない | 132 | ||
| 救急の心エコーでの筆者のスクリーニング法 | 134 | ||
| はいこう | 肺高血圧症 | ――の分類 | 272 |
| ――の原因としては左室不全に伴うものが最も多く,HFrEF,HFpEF,弁膜疾患のいずれでも生じます | 378 | ||
| はいどう | 肺動脈圧の推定 | 273 | |
| はなをす | 「鼻をすするようにしてみてください」 | 257 | |
| ひだりし | 左主幹部梗塞 | ――でST上昇を認めない場合 | 50 |
| ――は左前下行枝領域から回旋部領域に連続する壁運動異常 | 76 | ||
| ――は「セブン,イレブン,LMT」 | 76 | ||
| 心室中隔の壁運動がほとんど正常に見える―― | 80 | ||
| ひっしゃ | 筆者の全くの私見 | 199 | |
| ひまんの | 肥満の患者さんの場合 | 48 | |
| ふかんぜ | 不完全閉塞 | 78 | |
| へきうん | 壁運動異常 | ――領域と推定される責任病変のまとめ(表) | 83 |
| 前壁梗塞で長軸像で中隔基部の―― | 70 | ||
| 傍胸骨左縁短軸像僧帽弁レベルで側壁領域の―― | 70 | ||
| 側壁~後壁に局所―― | 71 | ||
| 側壁のみに――,後壁は保たれる | 71 | ||
| 後壁のみに――,側壁は保たれる | 71 | ||
| 下壁梗塞で右室後壁の――があれば | 72 | ||
| ――が下壁基部から広がっていれば | 72 | ||
| 右室後壁の――は傍胸骨左縁短軸像がわかりやすい | 72 | ||
| 傍胸骨左縁短軸像で――が中隔下部領域に認められる場合 | 74 | ||
| 傍胸骨左縁短軸像で――が後側壁領域全体に広がっている場合 | 74 | ||
| 下壁領域の――が中隔下部を含んでいるかどうか | 75 | ||
| 傍胸骨左縁短軸像で後壁から3時~4時の位置にまで―― | 76 | ||
| 左前下行枝領域から回旋枝領域に連続する―― | 76 | ||
| 中隔の――が出ない(中隔の壁運動が保たれた)左主幹部梗塞 | 76 | ||
| 中隔の動きに惑わされて側壁の――を見逃す | 77 | ||
| ――を認める領域の最も近位側の壁運動が保たれている | 79 | ||
| ――を認める領域の遠位側の方により良好な局所壁運動の残存 | 79 | ||
| ――が消失している領域で壁厚の局所的低下やエコー輝度の高度な上昇 | 82 | ||
| ――異常の広がりが冠動脈の解剖とあまりに一致しない | 84 | ||
| ――の範囲が各分画内に収まっているかを考える | 84 | ||
| 前壁に――があって心尖部の壁運動が比較的保たれている場合 | 85, 86 | ||
| ――が消失するとともに壁厚が菲薄化している領域 | 89 | ||
| 急性心不全では,新たな冠動脈病変による虚血が存在しなくても――が増悪することがあります | 328 | ||
| へふへふ | へふへふぺふぺふへふぺぷぺふ♪ | 172 | |
| べんだぷ | ベンダプニアは最近になって心不全の症状として認められるようになりました | 161 | |
| べんとう | 「弁当いかがですか~」「たこつぼといえば西明石駅名物ひっぱりだこ飯〜」 | 145 | |
| むちのよ | 「ムチのような動き!」「イタい イタい」 | 99 | |
| もくしほ | 目視法の私案(EF) | 199 | |
| やせがた | やせ型では立位心になる | 48 | |
| やせがた | やせ型の患者さんの場合 | 47 | |
| りんしょ | りんしょうてきには差はないね | 233 | |
| わたした | 「わたしたちを平均しなさい!!」「それは無理だ」 | 253 |
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)
本記事の関連書籍