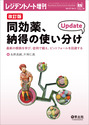- [SHARE]
- ツイート


今回のお題本は『お母さんを診よう』である.プライマリ・ケア医が,妊婦さん,授乳婦さん,そしてこれからお母さんになる(かもしれない)すべての女性,すなわち「広義のお母さん」を診るにあたって必要な知識と知恵を丹念に紡いだ名著だ.読者対象が「プライマリ・ケア医」であるということにご注目いただきたい.サブタイトルは「プライマリ・ケアのためのエビデンスと経験に基づいた女性診療」.産婦人科の研修中に使うであろう「産婦人科用マニュアル」とは趣が異なる.
一読した印象は,「おそらくこの本を必要としている人はメッタクソに多いだろう」ということ. 誰しも経験があるだろう,妊娠中・授乳中の患者が一般外来に来たときの独特の緊張感.「お母さん」がすべて産婦人科でカバーされているわけではない.学生の頃から幾度となく聞いてきた「女性を見たら妊娠を思え」はいいとして,では,思ったらその先どうするのかを,きちんとシミュレーションできているか,という話だ.
もちろん,妊婦が普通に体調を崩して普通に一般外来を訪れることはある(妊婦だって風邪くらいひくし,食あたりにもなる).HPVワクチンや風疹ワクチンなどの接種相談に来る女性もいる.他病での診療中に,月経をはじめとする女性特有のトラブルが後景から飛び出してくることも多い.妊婦における血圧のコントロールや薬剤使用時の注意点なども含めて,「言われてみれば……」系ソワソワポイントが,この領域にはとても多い.どう考えても早めに読んでおきたい本だ.
さあ,今回の「勝手に索引」を見ていただこう.いつものように,Webでは完全版を公開.本稿では,一部を抜き出して説明する.今さらだけど今回の索引はもはや「やりすぎ」感があり,我ながら誇らしい(?).スーさん(編集者・あだ名)はきっと索引作成の前後で体重減少したと思う.
市原のオリジナル索引①
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| にんしん | 妊娠・出産に対して,いろいろな感じ方や考え方がありますし | 56 | |
| にんしん | 妊娠中からパートナーに対して不満をもっていた場合 | 200 | |
| にんしん | 妊娠中に異常を指摘されていても,それが産後にまで影響してくるという説明が妊娠中になされていない場合もしばしばで | 82 | |
| にんしん | 妊娠中にどうしても解熱薬が必要な場合は,NSAIDsを避け,アセトアミノフェン(カロナール®)の使用を検討する | 236 | |
| にんしん | 妊娠中にとくに摂取を意識する必要のあるビタミンとしては,葉酸やビタミンDがある | 122 | |
| にんしん | 妊娠中に問題となりやすいコモンプロブレム | 機能性頭痛 | 88 |
| 気道・呼吸器感染症 | 88 | ||
| インフルエンザ | 88 | ||
| 感染性腸炎 | 88 | ||
| 尿路結石 | 88 | ||
| 尿路感染症 | 89 | ||
| 無症候性細菌尿 | 89 | ||
| 妊娠性貧血(鉄欠乏性貧血) | 89 | ||
| 花粉症,鼻炎 | 89 | ||
| 齲歯,歯周病 | 89 | ||
| 外傷 | 90 |
当然のように目に付くのは「にんしん」の項目.多い.幅広い.コモンプロブレムが豊富.便秘,浮腫,痔核…….
そもそも皆さんは,「妊婦の便秘」についてまとまった本を読んだことがどれだけあるだろうか.どんな医者でも経験するはずだが,どこに書いてあるのかイマイチわかりづらい項目だ.実戦,現場,外来のナラティブ.薬を1つ出すたびに,禁忌が気になってしょうがない. さらに,コモンプロブレムだけではない.
市原のオリジナル索引②
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| こわいふ | 怖い腹痛 | 妊娠後期の腹痛は超緊急疾患の除外がキモ | 93 |
| 全妊娠期間を通じて,血管解離と血栓症の頻度が上がる | 93 | ||
| カンカンカンと血圧上昇 | 93 | ||
| 破裂しソウな腹痛 | 93 | ||
| 臍詰まり | 93 | ||
| 妊娠関連の超緊急疾患は,緊急度合いの桁が違う | 94 | ||
| カンカンカンと血圧上昇 | 95 | ||
| カン(肝):HELLP症候群 | 95 | ||
| カン(肝):急性妊娠脂肪肝 | 96 | ||
| カン(癇):子源 | 96 | ||
| 血圧上昇:重症妊娠高血圧症候群 | 96 | ||
| 破裂しソウな腹痛 | 97 | ||
| 破裂:子宮破裂 | 97 | ||
| ソウ(早剥):常位胎盤早期剥離 | 97 | ||
| 臍詰まり | 97 | ||
| 臍:臍帯脱出 | 97 | ||
| 詰まり:羊水塞栓 | 98 | ||
| 妊娠後期の超緊急疾患を否定するには? | 98 | ||
| もし妊娠後期の超緊急疾患を否定できなかったら? | 99 |
「妊娠関連の超緊急疾患は,緊急度合いの桁が違う」.頭ではわかっているけれど,あらためて読むとぞわっとするフレーズだ.救急・ER系の本をどれだけ読んでも「妊婦だったら」の項目はほんのちょっとしか書かれていないことも多い.果たして何割の研修医が,「お母さん」を診ることに日常的に備えているだろう.
研修医向けの書籍紹介となると,ついこうして「すぐにでも読んで欲しい項目」ばかりをピックアップしたくなるのだけれど,それだけでは書籍の多相性は見えてこない.もっと深く潜ろう.もっと細やかに探ろう.
すると,こういう一文に目が留まる.
市原のオリジナル索引③
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ぷらいま | プライマリ・ケアのACCCA | 14 | |
| ぷらいま | プライマリ・ケアの外来はフォローアップが途切れた女性をサルベージする機会 | 153 | |
| ぷれどに | プレドニゾロン(プレドニン®)は胎盤通過性が低いため,妊娠中は使用しやすい | 238 | |
| ぷろげす | プロゲステロンやエストロゲンによるインスリン抵抗性の増加 | 80 |
このあたり,「いぶし銀」である.いい……実にいい.
と,一人で感動していてもしょうがないので,本文を引用しながら簡単に補足しておく.妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群は(出産後の)疾病発症リスクとなるため,本来は産後も継続してフォローアップが望ましい.しかし,産科医から内科に引き継いだあとの受診でいったん血糖値や血圧が安定していると,そこでフォローが途切れてしまうことが多い.だから著者は言うのだ,「プライマリ・ケアの外来はフォローアップが途切れた女性をサルベージする機会」であると.な,な,なるほどなあ……! 本書は単なる知識の羅列ではない,「熱心な指導医」の雰囲気を帯びている.医を学ぶ醍醐味がある.
記事の多彩さにも驚いて欲しい.次の索引④などはいい例だろう.性病あり,近親者からの暴力(intimate partner violence:IPV)あり,「産み方」あり,性教育あり,若年妊娠に対する社会的支援あり,調乳のコツまで…….
「お母さんを診る」ってこんなに幅広いのか……と,ため息が出る.
市原のオリジナル索引④
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| だんじょ | 男女ともに最も多い性感染症は(わかっている範囲では)性器クラミジア感染症 | 14 | |
| ちいきで | 地域で診療する以上,自分が勤務する医療機関内にも加害者と知り合いがいる可能性があり,何らかの形で情報漏洩の危険性伴うことを知っていなければならない | 217 | |
| ちいきの | 地域のプライマリ・ケア医,救急医に「妊婦は診ない」といわれてしまうと,今後日本の周産期医療は立ちゆかない | 101 | |
| ちいさく | 小さく産んで大きく育てるは今や非常識 | 127 | |
| ちしきだ | 知識だけではなく,自己効力感を高め,自己・他者を尊重する姿勢,交渉スキルなどを伝えることで,危険な性行動が抑制される | 224 | |
| ちちおや | 父親も誰かわからず,妊娠していることが判明するのが怖くて受診できなかった | 77 | |
| ちょうに | 調乳したミルクからあらかじめ大さじ1杯ほどの量を取り出して薬を溶かし,哺乳の最初に飲ませてしまう | 172 |
実践的な項目の中に敢然と光る,「地域のプライマリ・ケア医,救急医に『妊婦は診ない』といわれてしまうと,今後日本の周産期医療は立ちゆかない」の一文.うーん全くその通りだ.産婦人科にまかせてOK,と放っておける話ではない.
市原のオリジナル索引⑤
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| おっとも | 夫も仕事で忙しいので…… | 57 | |
| おなかが | お腹が痛いのが赤ちゃんに影響しないか心配で…… | 253 | |
| かいとう | 回答が真実である保証もない | 23 | |
| かいにゅ | 介入項目は多数あるが,初診時のメッセージが多くなりすぎる | 22 | |
| かくてい | 確定的影響も確率的影響も100mGy未満では影響の発生はほとんどない | 105 |
このあたりなど,項目を眺めていて,あなたは,キュンとこないだろうか.こない? くる? くる? くるでしょう.くるだろうと思ったよ.「夫も仕事で忙しいので……」「お腹が痛いので赤ちゃんに影響しないか心配で……」.これらが本書の中に出てくる意図は,別に「読者にあるあるとうなずいてほしいから」ではない.ならばどうしてこれらのセリフが文中に登場するのか,本書をお持ちの方は実際に該当ページを見ていただきたい.そうか,外来で患者と対話するにあたっては,そのような解釈が可能なのかと,「経験知」が胸を打つだろう.
* * *
本書を読んでいると,だんだん,外来のことを思い浮かべるようになる.実際に自分が「お母さん」たちを相手にしてさまざまな対話をしているシーンが脳内再生される.あるいは本書は,外来技術を磨くための本なのかもしれない,と感じる.
話がちょっとずれるけれど,昔,「それにつけてもオヤツはカール」というキャッチコピーがあった.では,「それにつけても内科は○○」の空欄に当てはまる言葉って何かなあ,と考えてみる.エビデンス,処置,手技,疫学…….いろいろ候補はあるだろうが,私なりにしっくりくるフレーズは,「それにつけても内科は外来」なのである.結局のところ,どれほど優秀な医師であろうと,患者の話を聞いて視野を共有し二人三脚を進める「外来技術」がないと,なんか,ぜんぶ,台無しだよな……と思う.
では,「外来」のノウハウを直接学べる本があるのかというと,そういうのは思った以上に少ない.というか,そもそも外来とは,「ノウハウ」だけで乗り切るものではない.ここのところはまだ私の中で言語化し切れていないのだけれど,外来がうまい医者には,医学の知識と確かな医術,そしてコミュニケーションスキルに加えて,さらに,「質の高い思索を数多くこなした経験」みたいなものが備わっているように思う.ノウハウだけではどうにもならないのだ,たぶん.
なんだよ,結局は経験なのかよ,と鼻白んでしまう人がいたら申し訳ないけれど,私は何も,経験が「勤務年数」と比例するなんて言っていない.「ベテランならうまい」というものではないと思う.横軸に「時間」を,縦軸に「経験値」を当てたとして,グラフがy=axの直線になるとは私には思えない.ここで言う経験というのは,場数や体験時間だけで決まるパラメータではなく,なんらかの衝撃や衝突が加わることによって,ドカンドカン変形・屈曲して非線形に昇り上がっていくものだと思っている.時間に物を言わせて累積した澱のような知識なんぞ,所詮は加齢と共に弱っていくシナプスのダメージと打ち消し合ってしまう.私は臨床知というのはもう少し偉大だと信じていて,要は,「ただ時間をかけりゃいいってもんじゃない,独特の経験が必要」だと考えている.
これだけ多くの医学書が世に溢れ,動画教材も長足の進歩を遂げている今,こと「外来」に関しては,センパイの仕事っぷりを1〜2年後ろで見学しただけであとは現場に放り出されて自前でやりくりしている研修医たちの,何と多いことか.そういう人たちに,「どうしたら外来でうまくやれますか」と尋ねられたとき,「情念の濃い本とちゃんと衝突してみるのは1つの手だよ」と答えている.
市原のオリジナル索引⑥
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| きかれる | 聞かれるとちょっと迷う赤ちゃんのよもやま相談 | この子おっぱい飲みすぎじゃないですか? | 169 |
| この子おっぱい足りないんじゃないですか? | 169 | ||
| 赤ちゃんのスキンケアはどうしたらよいですか? | 170 | ||
| 薬は食後じゃないとだめですか? | 171 | ||
| この子,泣きやまないんです | 172 | ||
| 夕方になるとすごく泣き出すんです | 172 | ||
| おしゃぶりはいつまで? | 173 | ||
| 便の相談 | 173 |
「ちゃんとぶつかった先達」の書いたものは,濃い!そういう濃い本ときちんと衝突しながら,ガンガン非線形に突き進んでいく.そうすれば,若かろうが,まだ時間をかけていなかろうが,医師の頭の中には確かにある種の「集合知」が形成されていくのではないかと思うのだ.
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)