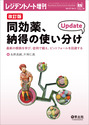論文の読み方で
勝手に索引!
(後編)
❶僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方を知らない。
後藤匡啓/著,長谷川耕平/監
■定価3,960円(本体3,600円+税10%) ■A5判 ■310頁 ■羊土社
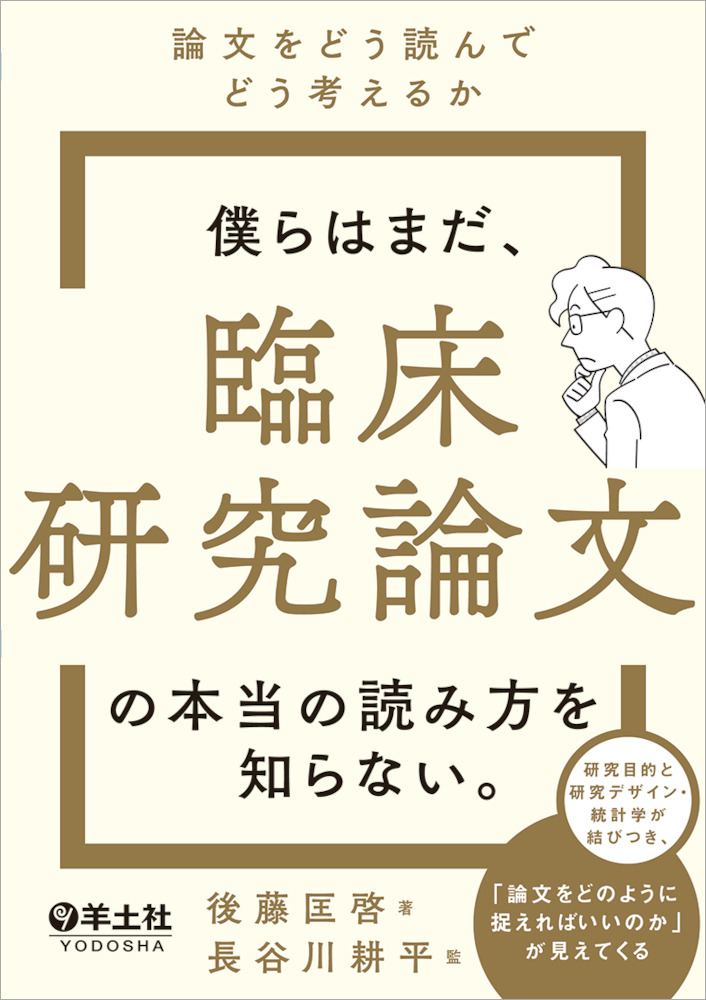
❷短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー 論文読解レベルアップ30
田中司朗,田中佐智子/著
■定価4,180円(本体3,800円+税10%) ■B5判 ■198頁 ■羊土社

- [SHARE]
- ツイート


(今回だけでも読めますが,先月号の「前編」を先に読んだほうがよいです.ウェブで読めますのでよろしければ先にご参照ください)
* * *
さあ,スーさん(担当編集)が苦労してまとめた索引を見てみよう.いつものように,本稿では索引の一部を抜き出しながら解説する.Webで索引の完全版を公開するから,QRコードからぜひアクセスしてみてほしい.今回はちゃんと2つあるぞ.スーさんありがとう.
お題本その1『僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方を知らない。』1)は,「あの花」感をにおわせる挑戦的なタイトルである.かなりよく売れている本であり,すでにご存じの方も多かろう.
その2は,『短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー 論文読解レベルアップ30』2).こちらは一見普通のタイトルだが,表紙には思い切りリアルなオオサンショウウオのモノクロ写真.イラストにすれば可愛かったろうに,あえて実物の写真.
どちらも一筋縄では行かない,個性あふれる本だというのがわかるだろう.順に紹介する.
1『僕らは』で勝手に索引!
『僕らは』1)は紙質のよい本だ.パラパラ開く楽しみがある.デザインが良く「眺めてうんざりすることがない」のがよい(※医学書においてこれはとても大事なことです).イラストに描かれている内容がよく練られていて,単なる「箸休めのカット」ではなくイラスト自体に意味があるのがよい.

さらに,項目ごとに小括として挿入される「Dr.Gotoからの一言」というコーナーが便利である.項目末尾のまとめ自体は医学書の編集手法としてよく目にするが,形式的なまとめに終始して事実上の飾りになってしまう本も多い中,本書の「一言」は本当に役に立つ.イラストと「一言」を拾い読みして,気になったところの本文を読むスタイルでかなり通用する.まとめ能力が高い書籍だ.
著者の「文体」にも特筆すべき点がある.たとえば以下の項目を見てほしい.
市原のオリジナル索引① その壱
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| かんどか | 感度解析は非常に重要 | 239 | |
| きかいが | 機械学習(深層学習含む)はブラックボックスだから…という意見を聞きますが | 226 | |
| きじゅつ | 記述研究 | 記述研究は読むのが容易であり、次にランダム化比較試験など治療・介入の研究が読みやすい | 98 |
| 記述研究というのは臨床研究の最初の第一歩 | 100 | ||
| describe(記述する)、characterize(特徴づける), clinical features(臨床における特徴)など、「記述する」「特徴づける」という単語があれば記述研究になります | 101 | ||
| 記述研究はdescriptive studyと呼ばれ、現状をただ記述するだけ | 108 | ||
| 記述統計は研究対象集団がどんな特徴(年齢や性別の分布など)をもった集団か? を表すために用いられます。 | 186 |
網かけしたフレーズは,実際には次のような一文の中に登場する.
この太字にした部分は,著者の後藤先生がレジデントだったときの視点,もしくは後藤先生の目の前で勉強しているレジデントの視点で書かれている.
「誰が誰に向けて書いた本か」はよく語られがちだが,「誰が誰に向けて,いつの体験を元に語っているか」に着目すると,その医学書が備えるパースペクティブ(視点)がよりはっきりとわかる.この読み方はあまり知られていないが,医書読みにはぜひ一度お試しいただきたい.
同じように,こちらの部分も「前後」を見てみよう.
市原のオリジナル索引① その弐
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| しんたい | 身体所見でも研修医と指導医では正確さに違いがありますよね。 | 169 | |
| しんらい | 信頼区間 | 信頼区間が基準値を跨がなければ統計学的に有意と判定 | 203 |
| でも信頼区間は広いからサンプルサイズの問題かな…… | 248 | ||
| しんりょ | 診療報酬のために記載してある診断名がどこまで正しいのか? | 141 | |
| すいそく | 推測統計 | 「確率分布とは何か?」「検定とは何か?」といった基本的な段階で挫折することが多く、肝心の推測統計までたどり着けない | 185 |
| 推測統計が何をしているか | 191 |
やはりここでも,著者がレジデント時代の記憶を振り返っている.こういうところに,通読型の医書の個性が出る.
すなわち本書は,レジデントだったときの気持ちを忘れていない指導医が,「論文を読む前に知っておきたいこと」,「論文の読み方(特に臨床研究論文の読み方)」,そして「論文の批判的吟味」や「抄読会の準備方法」などを念入りに解説する.売れるのも納得のよい本だ.
2『オオサンショウウオ』で勝手に索引!
さて,もう1冊のお題本.京都大学のschool of public health (SPH)の講義を元に書かれた『オオサンショウウオ』2)もまた,論文をしっかり読み解くための教科書である.ただしこちらは,より医療統計に関する記載がメインとなっている.
本書は,なつかしの受験問題集のように,末尾が別冊として取り外せる.へぇ,何の回答が載っているんだろうと思って,先に別冊を開くと……

なんと,本文で読み解く「課題論文」がまるまる載っているではないか! 権利の問題とかどうやって解決したんだろうと気を揉んでしまうが,すごい熱意だ.実際に,SPHの講義では論文を配付して,講師と一緒に読みながら医療統計のノウハウを学ぶのだろう.さらに,論文が単にコピペされているわけではなく,読み手を助けるためのサポートがある.特に感動したのは「講義内容」マップ(右の写真)だ.
これ,すごい.概観,やばい.俺,興奮.
思わず作りたてのAIみたいなしゃべり方になってしまったが,幅広い医療統計学のどのあたりの知識を使うとこの論文を上手に読めるかが俯瞰されており,グッとくる.
さあ,別冊ばかり見ていないで,本文も見てみよう.
市原のオリジナル索引② その壱
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| こほーと | コホート研究やケース・コントロール研究 | コホート研究やケース・コントロール研究では交絡の調整は必須 | 47 |
| コホート研究やケース・コントロール研究では,推測の基盤としてモデルベースに頼らざるを得ません | 80 | ||
| コホート研究やケース・コントロール研究などのランダム化や介入を伴わない研究 | 149 | ||
| コホート研究とケース・コントロール研究のイメージ | 152 | ||
| さがやた | 差がやたら出てくるような手段で解析をする人のほうがトンチンカンなのでして | 137 | |
| さぎょう | 作業記録を残す | 105 |
まずは,コホートとかハザード比とかサブグループ解析とか,「医療統計で出てくるとウッとなりがちな用語」に目を奪われる.当然,このあたりの用語に関する解説は綿密で丁寧だ.
ただし,本書ではお堅いはずの講義を読みやすくするワザが仕込まれている.コナン君の犯人みたいなシルエットだけの「受講者」が,講義の最中に基本的な質問をぶち込んでくるのだ.
市原のオリジナル索引② その弐
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| すべてぷ | すべてプラセボに勝てなかったのです | 81 | |
| すみませ | すみません,よくわかりません.ほかの例はありませんか? | 161 | |
| せいぞん | 生存時間解析三種の神器 | 49 |
市原のオリジナル索引② その参
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| こていこ | 固定効果モデル | 固定効果モデルと変量効果モデルのどちらを使えばいいんですか? | 116 |
| 固定効果モデルでは,推定値のバラツキを,「試験内分散」だけによるものだと考えます | 135 | ||
| このさん | この三角,何ですか? | 86 |
索引を眺めていると,「本当にこの難しそうな教科書の索引項目なの?」と目を疑うようなものが混じっている.それらはたいてい「コナン君の犯人」によるものである.さすがにΔ(デルタ)を見て「この三角,何ですか?」と質問する場面では,仮にも医者だろ,カマトトぶってんじゃねぇよとツッコみたくなるが,講師がたった今説明したばかりの内容に,受講者役が「すみません,よくわかりません」と立ちはだかる構成はエグい.
著者の田中夫妻が実際のSPHの講義で,若手に伝わりづらかったと感じた点を忘れずに書面に反映したのだろう.これが編集者のアイディアだとしたら胆力が半端ない.医学書の著者に「わかりませんと言う人を入れましょう」とはなかなか言いづらいだろう.ヒリヒリ緊迫する,いい本だ.
32冊を合わせて勝手に索引!
『僕らは』1)も,『オオサンショウウオ』2)も,全体のクオリティを底上げしているのは,著者の指導医としてのナラティブであるように思う.著者たちは「若手だったときの気持ち」を忘れず,「若手からのリアクション」をきちんと想定して医書を作っている.だから,とても読みやすい.
ただし,注意しなければいけないこともある.
今回紹介した2冊はいずれも,「優れた指導医に相当する本」として頼りがいがある本だ.しかし,だからと言って,たとえばどちらか1冊だけを買って,「たった1冊ですべてわかった!」とまでは言えないし,言ってはいけないと思う.
前回書いた「Acknowledgementの書き方,知ってるか?」に衝撃を受けた日から,私はずっと考えていた.臨床研究や医療統計のようなジャンルを勉強する際に,たった一人の指導医からすべてを学べるほど,今どきのエビデンス・ベースト学問は簡単ではないのと同様に,たった1冊の本に全責任を負い被せるような勉強をしてはいけない,と.
指導医一人じゃ足りないよ,と言われたところで,若手は困ってしまうだろう.みんながみんな,東大や京大の院に入り直す選択を取れるわけでもない.
でも,本ならば,同時に複数の本を師匠とすることが容易にできる.
たとえば,このようにして.
市原のオリジナル索引①+② その壱
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| こほーと | コホート研究は同じ特徴をもった集団を追跡して行う研究 | お題本❶ 143 | |
| こほーと | コホート研究やケース・コントロール研究 | コホート研究やケース・コントロール研究では交絡の調整は必須 | お題本❷ 47 |
| コホート研究やケース・コントロール研究では,推測の基盤としてモデルベースに頼らざるを得ません | お題本❷ 80 | ||
| コホート研究やケース・コントロール研究などのランダム化や介入を伴わない研究 | お題本❷ 149 | ||
| コホート研究とケース・コントロール研究のイメージ | お題本❷ 152 | ||
| こほーと | コホートデータは「ある研究目的のために同じ特徴をもった集団を追跡する」 | お題本❶ 136 | |
| これすぽ | コレスポンディングオーサーの重みは分野によって異なり、生物系や基礎医学系だと非常に重要視されます | お題本❶ 88 | |
| さいきん | 最近の論文はEpub ahead of printといって紙媒体より先にオンラインで公開されることが多い | お題本❶ 53 | |
| さいしゅ | 最終的にアクセプトするかどうかは編集部の一存で決まるため、実は編集者達の好みに結構左右されます | お題本❶ 40 | |
| さがやた | 差がやたら出てくるような手段で解析をする人のほうがトンチンカンなのでして | お題本❷ 137 | |
| さぎょう | 作業記録を残す | お題本❷ 105 | |
| さぶぐる | サブグループ解析 | サブグループ解析では年齢や男女など各サブグループで関連性や治療効果が異なるかどうかという異質性(heterogeneity)を評価します | お題本❶ 238 |
| サブグループ解析を行って効果修飾が見られた場合、「なぜグループごとで結果が異なるのだろう?」という理由を考える | お題本❶ 238 | ||
| さぶぐる | サブグループ解析は,全患者を対象とした解析で有意な場合とそうでない場合で,解釈が変わります | お題本❷ 120 |
これは,2冊それぞれ作った完全索引を合体させたものだ.ちゃんとQRコードで全部見られるようにしておいたから,皆さんも試しに見てみるといい.1冊の索引を見ていたときとは,だいぶ雰囲気が変わる.
たとえば,「コホート」に関しては2冊とも言及があるが,それらの説明方法は,当たり前だけれど本ごとに異なっている.全く同じ内容を説明するにあたって,指導医と若手との関係やパースペクティブが異なれば,表現方法が変わるのは当たり前のことだ.
市原のオリジナル索引①+② その弐
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| めそっど | メソッドに何が書いてあるか | お題本❶ 106 | |
| めたあな | メタアナリシスは臨床試験のある種の反復 | お題本❷ 29 | |
| めたかい | メタ解析自体は意外と簡単にできてしまうのでその質も(かなり)玉石混淆 | お題本❶ 105 |
「メタアナリシス(メタ解析)」と「モデル」も,2冊ともに解説されていて,かつ切り口が異なっている.1冊ずつ本を読んでいたときもうすうす感じてはいたけれど,こうして索引を作ると,よりはっきりと「視座が違う本」であることがわかる.
スペースの都合上,すべては提示できないが,「ランダム化」,「サブグループ解析」,「ロジスティック解析」,「打ち切り」なども見比べてみるといい.
これまでは,私自身,「優れた指導医のような本」,「頼れる先輩のような本」,という言葉を頻用してきた.しかし,本は人と違って,複数同時に師事することができる.このメリット,もっとしっかり享受したほうがいい.索引は合併させてナンボなのかもしれないと,ふと思った.
お題本
- 『僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方を知らない。』(後藤匡啓/著,長谷川耕平/監),羊土社,2021
- 『短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー 論文読解レベルアップ30』(田中司朗, 田中佐智子/著),羊土社,2016
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)