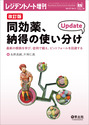- [SHARE]
- ツイート


私は今42歳,医師17年目であるが,「これまで外科系の本をなんとなく敬遠してきた自分」に対するかなり強めの後悔がある.病理医だから外科の本は解剖以外読まなくてもいいや……という気持ちでいたかつての自分,ああ,無知でオロカだった.なぜそこに宝の山があることに気づかなかったのか! 手をドラえもんのように丸くして頭をポコポコ殴ってみたい思いでいっぱいだ.リアルガチな拳はちょっときついものがあるのでウレタン製くらいでいいけれど.
ともあれ,17年前とは言わないが,せめて10年早く「研修医向けの外科系教科書」を読んでおくべきだった.今になって必死で読みまくっている.うおおなるほど,うわあなるほど,と毎日のように叫んでいる.主に脳内で,たまにツイッターで.
おせっかいかもしれないけれど,「しくじり先生」的に申し上げておこう.これから内科系に進む研修医や,いわゆるマイナー科に進む研修医のみなさん.外科系の本を見逃すな.ここは穴場だ.そしてパラダイスである.先月の「外科センス」もよかったが,今月もいいぞ.
なぜ外科系の本をそんなに推すのかって? 疾病1つ1つを掘り下げていく内容もさることながら,「疾病に関わらず,患者の状態を維持するための知恵」が満載だからだ.これだとわかりにくいだろうか? 一言でまとめると,「病棟テクニック」が手に入るのである.
今回の「勝手に索引」を見ていただこう.いつものように,Webでは完全版を公開.本項では一部を抜き出して説明する.さっそく以下の項目を見てほしい.「ぐっ」とくるぞ.
市原のオリジナル索引①
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| かいだん | 階段を上れるか | 53 | |
| かいふく | 開腹 | しっかりした診断ができなくても緊急――する | 36 |
| ―― | 71 | ||
| ――時に助手になったら,早速鑷子でガーゼをつかんで待機 | 83 | ||
| 執刀医の位置に立って「――をさせて」とアピールしよう! | 88 | ||
| かおすで | カオスです | 90 |
市原のオリジナル索引②
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| しょくし | 触診と併せてみるX線上の大腸の所見ポイント | 31 | |
| しょしん | 初診時に注意すべき点 | 53 | |
| しょっく | ショックにまでなっているのに診断がつかない!という窮地に追い込まれたときに思い出してください | 36 |
救急外来で研修医が最も気にかけているであろう「緊急手術って結局どういうケースで行うの?」や,「一刻一秒を争う病態かどうかをどう判断するの?」という,岐路に立たされたとき御用達の知恵.こういうのを読んだ経験があるかないかで,たぶん,いざというときの判断が「2分」早くなる.
ただし本書は「ERでの判断を速くする技術」ばかりが書かれているわけではない.というか,それ以外の要素に滋味がある.
序盤,まず診察についてのあれこれ,すなわち手術「前」にやることの記載がはじまる.見逃してはいけない疾患のサイン,細かな診察手技のコツ,頭から足までを系統的に探っていくときのポイント…….
これらを踏まえて,次に手術「中」にやることが分厚くカバーされる.糸結びなどの手技からオペの流れまでを網羅できる.もっとも,網羅するとはいってもそこは「通読系の教科書」なので,羅列された箇条書きをただ読み下していくのとは違い,「ストーリーが思い浮かぶような読書」が可能になっていて,読みやすい.
すなわち序盤から中盤にかけて「あー確かに外科の本だよねー」と,読む前の印象を裏切らない王道展開が続くのだ.そして本書の真のかっこよさはこの先にある.「手術前」「手術中」ときたら,次にやってくるのはご想像の通り,「手術後」.
大量の紙幅を割いて,「第4章 全身管理で勉強しよう」が展開される.……ここが秀逸! ありとあらゆる研修医にとって,第4章は必読だろう.将来進む先が皮膚科だろうが精神科だろうが関係ない.病棟を管理しない医者なんてほとんどいないからだ.病棟を直接管理しない病理医(である私)ですら,病棟で起こったトラブルに端を発する患者の変化は診断しなければいけないわけで,全医師にとって病棟における全身管理の勘所は一大テーマであろう.
そもそも,初期研修医が毎日悩む内容のほとんどは,「病棟で患者をどう診るか,病棟でスタッフのためにどう動くか」であろうと思われる.主執刀するわけでもなく,自分の責任で処方しまくるわけでもないが,患者の微細な変化に目を配り,チームの一員となって目を使い手を動かせ,それがお前が今ここにいる意味だと叱咤激励される毎日.医学部時代に教わったことと無関係とまでは言わないが,机上の論理とは似て非なる,現場の論理に摩耗する.「研修医マニュアル」に必死で目を通す.そんな研修医の日常において,本書はギラリと存在感を発する.
私は狂ったように蛍光ペンを引きまくった.これこれ! こういうのを知っておきたかった! 意外と本で読んだ記憶がない,でも,今日もどこかの病棟で展開されているであろう経験知とエビデンス.
ここであらためて索引を見てみよう.するといろいろわかることがある.
市原のオリジナル索引③
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| さっとつ | さっと強く入れると,組織がキレる前に指導医がキレる | 82 | |
| さゆう | 左右の腹直筋鞘が癒合しているところ(白線) | 71 | |
| じかく | 痔核 | 内――は通常軟らかいため,よほど経験を積まないと直腸診ではわからない | 129 |
| 肛門粘膜下には,血管,動静脈吻合,結合織,粘膜下筋でつくられるクッションがあり | 129 | ||
| 排便時に怒責をくり返すことでクッションが引き伸ばされ断裂し血管が増生し内――になる | 129 | ||
| 歯状線の外側に浮腫,炎症が波及したり血栓(外――)ができたりすると強い痛みが発生 | 129 | ||
| まず「血液は真っ赤ですか? 紙に付きますか?」と聞きます | 129 | ||
| 内――には動静脈の短絡がある | 129 | ||
| 排便時間を短く(2〜3分以内)にするよう指導 | 130 | ||
| 5分間でも長い | 130 | ||
| 残便感があっても排便努力を切り上げ,肛門を洗浄する | 130 | ||
| Goligher分類 | 130 | ||
| 肛門周囲に膿瘍がみられる場合 | 131 |
ざくざく索引を作っていくと,「外科医が得意とする疾病」が幅広く記載されていることに気づく.虫垂炎,痔核,ヘルニア,腸閉塞…….疾病のメカニズムから,対処法,そして外科手術の勘所までがまとめてあって,便利だ.「そうそう,外科の教科書っていうなら,こういう内容を書いてなくっちゃねぇ」と納得されること請け合い.
しかし,本書はそこに留まらない.たとえば以下のような項目をチェックしてほしい.
市原のオリジナル索引④
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| しゅうじゅ | 周術期の循環器合併症 | 術前術後に合併する循環器異常のなかでも,特に代表的なもの | 166 |
| Nohria分類のB,すなわちwet&warmが多い | 166 | ||
| Nohriaの分類は身体所見〔うっ血と組織低灌流(低血圧)の組合わせ〕で分けた心機能分類 | 166 | ||
| 第1病日あたりに眼球結膜に浮腫が出現することがあります | 166 | ||
| サードスペースにあった水分が急速に血管内へ戻る | 166 | ||
| 高齢者では術前に指摘されていない拡張障害が併存していることが多い | 166 | ||
| Nohria Lの低血圧はみられるがうっ血はない状態 | 167 | ||
| 下肢挙上で血圧が上昇するかを見るのもよい判定法 | 167 | ||
| Nohria Cの肺水腫の所見とともに血圧も低い場合 | 167 | ||
| 時々,ご飯をおごりましょう | 167 | ||
| 心臓に合併症のあるケース | 168 | ||
| 安定狭心症 ⇒ 階段を2階分上って大丈夫なら手術もOK | 169 | ||
| 大抵,ニトロール®をカバンにもっていたりします | 169 | ||
| 胸骨上に握りこぶしを乗せ,ぎゅっと握りしめるLevine徴候として表現されるのか | 169 | ||
| 負荷心電図で心拍数と収縮期血圧の積であるdouble productも有用で15,000ほどあると安心 | 169 | ||
| RCRIでリスクが高いとされるような患者さん | 169 | ||
| 結果的には心筋梗塞の発生を避けることができなかった | 169 | ||
| スタチンを処方しておくのは新たなACS予防の役に立ちそう | 170 | ||
| ACSの治療完了から外科手術までは最低60日空ける | 170 | ||
| 緊急手術は本当に危ないので,死亡リスクについて十分に家族に説明 | 170 | ||
| 胸痛はみられないことがあります.むしろ息切れ,冷感,低血圧などの症状が多い印象 | 171 | ||
| 80歳以上となると,腹痛,嘔気,嘔吐が主症状になります | 171 | ||
| 心電図モニターでは洞性頻脈が最も多い異常 | 171 | ||
| 虚血性心疾患であっても心電図が正常な症例は10〜21.9%もあるので,くり返し心電図をとるべきなのはER症例と一緒 | 171 | ||
| 術前に中止した方が無難な薬剤としてACE阻害薬,ARB | 171 | ||
| まず酸素投与 | 172 | ||
| 弁膜症の既往がわかっていても手術前に心エコーを依頼しますよね | 172 | ||
| 親切な循環器の先生は輸液を絞ってくださいとかコメントしてくれるのですが,どれだけ? | 172 | ||
| 閉鎖不全症 ⇒ 輸液は絞り気味,血圧を下げ頻脈にする | 173 | ||
| 狭窄症 ⇒ 輸液は十分に,徐脈にしながら血圧を上げる | 173 | ||
| 十分な歩行負荷に耐えられないような症例では死亡率が飛躍的に増加する | 174 | ||
| モニターを見てオワアという聞きなれない叫び声 | 175 | ||
| 我々外科医には見分けがつかないのである.心筋梗塞とたこつぼ心筋症 | 175 | ||
| 病名告知やギャンブルの負けのせいでたこつぼ心筋症になった報告もあります | 175 | ||
| 1年前に心筋梗塞で心臓にステントを入れました.今は健康です.…手術お願いします | 176 | ||
| ヘパリンが抗血小板薬の代わりになるガイドラインやエビデンスがあるわけではない | 177 | ||
| ペースメーカーは手術中,基本的にVVIまたはDOOとする | 178 | ||
| 術後約1%の患者さんに新たに心房細動が発生します | 179 | ||
| 5 cm以上の腹部大動脈瘤なら感度82%で触れることができます | 180 | ||
| 術後,数日で初めて歩いてトイレに行って,病室に戻る直前に突然失神するのが典型的な肺塞栓症の発症パターン | 181 | ||
| 腹部の手術後に発症した肺塞栓症で腹痛を呈したため再開腹してしまったという笑えない話 | 181 | ||
| 痰詰まりじゃないわけだ…ヤバいと思いながら | 184 | ||
| ダイナミックですよ,大変だけど. | 185 |
「周術期の循環器合併症」について体系的に書籍で読んだのははじめてかもしれない(なお,この項目はまだまだ続くのだが紙面の都合で一部だけを掲載する).手術という侵襲が体に加わることで,具体的で多彩な症状が起こり,シーンごとに異なる対処が求められる.
市原のオリジナル索引⑤
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| じゅつご | 術後呼吸状態のチェックポイント | 呼吸数の報告がない場合は必ず確認を! | 193 |
| ダウン症においては常に舌を口から出していることがあり,巨舌による換気不全を術前に予測しておく必要がある | 193 | ||
| 呼吸不全の最も多い原因は分泌物,喀痰による部分的な換気不良,すなわち“換気/血流比の低下”です | 194 | ||
| 高齢者では弾性力の低下に伴って細気管支の呼気時の閉塞部分(closing volume:CV)が多くなります | 194 | ||
| 酸素需要は発熱や術後振戦により術前の170%ほどにまで増加することがあります | 195 | ||
| 手術直後から1日目:換気不全が多い! | 195 | ||
| 手術が終わって抜管し病棟へ戻るところからのチェックポイント | 195 | ||
| 翌日以降の呼吸不全は診断に時間をかける余裕があります | 195 | ||
| まさかと思ったが硬膜穿孔による呼吸筋抑制なんてのも起きるんだという経験 | 196 | ||
| 手術直後の換気障害に対する初期治療 | 197 | ||
| ところで酸素投与はいつ中止するのか? | 198 | ||
| 術後2日目から:肺水腫/心不全が多い! | 199 | ||
| 経験豊富な優秀な看護師から「患者さんが溺れていますよ」ってコールがあります | 199 | ||
| よっぽどひどくなければピンク色の喀痰にはなりません | 199 | ||
| 基本的な身体所見で患者さんの変化を早期に把握する医師の姿勢が患者さんを救う鍵に | 199 | ||
| 門脈圧亢進症があったうえでの呼吸不全なので肝肺症候群が合併した可能性もある | 201 | ||
| 血液ガス分析は腹膜炎術後などでアシドーシス評価をくり返す場合には採血の簡単な静脈血でOK | 201 | ||
| SpO2とPaO2の関係を知っておくと結構便利 | 202 |
うーん,シブい!「経験豊富な看護師から『患者さんが溺れていますよ』ってコールがあります」なんて,考えたくないけれどしょっちゅう遭遇しそうなシーンではないか.本書はとにかくこの「現場での多彩さをカバーし,全身をきちんと管理するための知恵」が満載なのだ.
とかく,医学部時代には,初診の患者,救急の患者を中心に,シンプルな診断カスケードに乗っかった「一本道の因果」を学びがちだ.しかし,いざ医療現場で働き始めた途端に遭遇するのは,「複数の問題点を抱えた患者」や,「院内の処置によってリスクが倍増した患者」ばかり.臨床試験に登録できる患者のような,65歳未満,命に関わる既往歴なし,多重服薬歴なし,PS良好な固形癌患者に出会うことのほうが稀だし,ガイドラインを見ながら「Aという薬がBという薬よりもちょっとだけ良く効きます」,なんて単純なシチュエーションにも意外とお目にかからない.世はまさに,マルチモビディティ診療全盛時代.「習ったとおりにいかない毎日」を乗り越えるためには,歴戦の外科医の言が頼りになる.
市原のオリジナル索引⑥
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| じゅつご | 術後乏尿と急性腎不全 | 乏尿(0.5 mL/kg/時)が6時間以上続いたり,Cr 0.3 mg/dL 以上の上昇をみたら急性腎不全を疑う | 223 |
| 術後によくみられる乏尿の多くは生理的な反応です | 223 | ||
| 乏尿,無尿という報告を看護師から受けたら,筆者は患者さんの頸静脈を診て,腋窩を触り,下腹部を触診しています | 223 | ||
| せん妄になった男性患者が導尿カテーテルを引っ張って尿道の途中に留まっていることがあります | 223 | ||
| 腎前性腎障害のリスクは循環血漿量が少ない時期でのNSAIDsの使用が代表的 | 224 | ||
| 急性尿細管壊死は虚血と薬剤が原因となることが多い | 224 | ||
| 腎後性として単純にフォーレカテーテルの血栓などによる詰まりがみられることがあります | 224 | ||
| 術後乏尿の主な原因である循環血漿量の低下をどうやって見分けますか | 224 | ||
| 術後の生理的な乏尿であればレニン-アンギオテンシン-アルドステロン系の作用によりNaと水分は再吸収され,尿中Naは低下します | 225 | ||
| 結膜の浮腫がサードスペースへの水分貯留を示すことがある | 225 | ||
| じゅつぜ | 術前からの透析患者への対応 | 透析患者に対する意識は周術期の点滴量を減らすことにのみ向きがちだがそこが1番ではない | 221 |
| 透析から心筋梗塞に至る一本道があると考えよう | 221 | ||
| 周術期に輸液された水分は血管内や細胞外液とは平衡関係のないサードスペースに取り込まれてしまいます | 221 | ||
| 術後疼痛ではアセトアミンフェンとフェンタニルが使いやすい | 222 |
「透析患者に対する意識は周術期の点滴量を減らすことにのみ向きがちだがそこが1番ではない」とか,「乏尿,無尿という報告を看護師から受けたら,筆者は患者さんの頸静脈を診て,腋窩を触り,下腹部を触診しています」とか,「透析から心筋梗塞に至る一本道があると考えよう」とか.このナラティブ,良いでしょう.こういうのどんどん読みたいと思うでしょう.そうでもない? まあ人それぞれかもしれない,けど,私はこういうものこそ,本で読んでおきたいと思うほうである.
外科医の病棟管理に必要なのは,誤解をおそれずに言えば「外科学」じゃない.そこにあるのは診断と治療のくり返し,さらに言えば,術前・術後に患者の体調をベターにキープするための「維持管理学」であろう.すなわち本書は外科の本というだけではなくて(まあ外科の入門書としても優れているのだけれど),維持管理学を学ぶための本なのだ.
通常,医療においては診断と治療と維持とが三位一体になって進んでいくが(これを私は医療の三角形と名付けた),病院内外で維持管理というと,患者とのコミュニケーションを元に患者の日常を手伝う看護師や介護士,ケアマネージャーやソーシャルワーカー,栄養士や言語聴覚士など,医師以外の職種による働きが大きいように感じる.しかし医師だって維持はする.術後の患者に何が起こるかをじっくり勉強することは,まさに,医者っぽい.じっくり通読したらいいと思う.
◆ ◆ ◆
以上,絶賛しまくった本書であるが……スーさん(担当編集者)に1つだけ,愚痴ったことがある.この本の後半部,全身管理の第4章は,通読型というよりは網羅型,辞書型に構成されている.だから「オリジナルの索引」を作るのはすごく大変だった.項目だけを抽出すると「ふつうの索引」になってしまうのだ! ……ふつうの索引を作って何がいけないのか,みたいなツッコミは甘んじて引き受ける(スーさんもとばっちりだ).でも,普通に勉強しても,つまんないでしょう?
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)