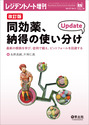腹痛の「なぜ?」で
勝手に索引!
腹痛の「なぜ?」がわかる本
腹痛を「考える」会/著
■定価(本体 4,000円+税) ■A5判 ■266頁 ■医学書院

- [SHARE]
- ツイート


千鳥のノブの持ちネタに,「クセがすごい」というツッコミがある.ノブはいつでもこの業物を帯刀し,鯉口を斬った状態で大悟と対峙して,ここぞというタイミングで一閃して爆笑を生み出す.CMにまで用いられる鉄板ネタであり,聞いたものをみな納得させてしまう強度のあるツッコミだ.
実際のところ,私たちはみな,クセやアクが強いものを心のどこかでひそかに探して愛でているのだと思う.少しの後ろめたさと,背徳の快感と共に.そうでなければ「クセがすごい」という極めて短いツッコミが,これほど多彩なニュアンスを持って私たちの心に飛び込んでくることはないだろう.
ここで,「いや,ちょっと待って,私は某病理医とは違って,クセとかアクみたいな気持ち悪いものを愛でる趣味はないよ」と反論する人もいるかもしれない.でも,そのセリフがすでに,私とあなたの違いを認識して区別しようと試みている.彼我の輪郭を重ねて,差異の部分に色を塗って指摘することは,互いの「クセ」を探すことと同じだ.クセと言って伝わらないのであれば,逸脱,違和,あるいは差延と呼んでもいい.
私たちはクセが気になってしょうがない.
さて,今月のお題本.前置きでピンときた人もいるだろうけれども「クセがすごい」.最近SNSで流行っているような,日記に毛の生えた程度のペラッペラなネット記事ばかり読んでいると,本書の刺激は強烈だ.目が覚める.背筋が伸びる.これが知性だよなあってため息が出る.こだわり,個性,こってり高カロリー.鋭利なアイスピックで氷を砕いていたら全部溶けちゃいました,っていうくらいの念入りな掘り返し.私はこういう本が死ぬほど好きだ.ただし本当にしんどい読書であった.完読したことでシナプスが5,000個くらい死んだと思う.それくらい脳に負荷がかかる楽しい読書体験.仮に,医学部の4年目くらいに本書を読了しておけば,その後確実に「東大王」みたいな医者になれるだろう,すなわち若干のキモさと潤沢な若さで周りのおじさんを魅了するタイプの医者に.
今回の「勝手に索引」を見ていただこう.いつものように,Webでは完全版を公開.前回も長かったが今回も長いぞ.本項では,一部を抜き出して説明する.
市原のオリジナル索引①
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| たいよう | 太陽神経叢 | ―― | 16 |
| エコーで腹腔動脈を同定し,そのまま動脈周囲の――をプローべで圧迫 | 168 | ||
| だしんつ | 打診痛は左手をゆっくりと腹腔内に押し込んでから左手の指先を右手指で叩くと陽性所見が出やすくなる | 46 | |
| たんせき | 胆石症 | 「――に特有の圧痛点は第12胸椎体の右縁から外側2〜3横指の位置にある」 | 160 |
| ――で多彩な圧痛点を生じるのはなぜか | 164 | ||
| ――では例外的に関連痛を右側に自覚することが多い | 164 | ||
| たんせき | 胆石症の右肩への放散痛を考える | 157 | |
| たんせき | 胆石発作では「右肩への放散痛」が有名であるが,なぜこれが生じるのかを考えてみたい | 157 |
本書は痛みのメカニズムを妥協せずに追い求める本だ.タイトルに「腹痛」とあるから,たいていの読者は「まあ腹部疾患の症候論を語るんだろうな」と予想して読み始めると思うが,それだと推測の「方向」は合っているのだけれど「程度」が期待をはるかに超えてくるのでびっくりすることになる.数多の類書と比べても,1つの命題に対する思索が長くてしつこい.往年の名作『スラムダンク』で河田弟がダブルクラッチを決める際に,ブロックに飛んだ桜木花道の滞空時間を見て「あれ……まだいる」とつぶやいたシーンを思い出してほしい.今のはすばらしい例えだった,読者は全員よくわかったと思う.
市原のオリジナル索引②
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| かんれん | 関連痛 | 内臓の痛みを皮膚(体表面)の痛みとして感じている | 10 |
| 性状は一般に鋭く,比較的限局している | 10 | ||
| 腹部以外に感じられる――を放散痛と呼ぶ | 10 | ||
| 消化管の腹痛を感じる部位(個人的には「――」だと思う) | 21 | ||
| 「片側の――は消化管以外から」と考えると嵌まる | 102 | ||
| 泌尿器・生殖器の――を考えるうえで,この論文に出会えたのは天佑だ | 126 | ||
| 腹腔動脈および上腸間膜動脈が支配する臓器の――は全て「心窩部痛」になりうる | 181 | ||
| 痛みのある場所の皮膚と皮下組織を優しくつまんで痛みが強くなれば――,変わらなければ体性痛 | 188 | ||
| ――の中枢説と末梢説 | 200 | ||
| ――は,「1つだけの臓器は正中,左右2つある臓器は片側に現れる」 | 212 | ||
| 男女ともに生殖器と泌尿器は神経を共有していると考えると――を理解しやすくなる | 216 |
胆石の痛みがなぜ右肩に放散するか? 知ってるヨ,要は関連痛だろ,なんて甘っちょろい気持ちで本文を読んでいると,ドカンとぶつかる.なにせ,「関連痛」だけでこれだけのサブ項目を抱える教科書だ.
痛みをどうパターンに分けて診断するか,痛みにどう対処して「手当て」するか.そういった「研修医が基本的になんらかのかたちで必ず勉強する内容」を網羅的に書かれた本ではない.それ以前の部分,もっとプリミティブな命題.「なぜこういう痛みが成立するのか?」という,症候学や疾病学のコアの部分を突き詰めた議論.正直,盲点である.だから,じっくり読む.
「うっ,なるほど,そこはあんまり考えたコトなかったなあ」
ほとんど毎ページのように,口の中でこのような言い訳をブツブツ呟くことになる.
本書のネットリとした思索のうねりを支えるのは,序盤の「準備運動」の部分だ.見たことはあるけれど覚える気がしなかった神経配置,デルマトーム,関連痛について,武器だという事は知っていたけれど,「ここまで研がないと斬れない刃物だったのか(これだけ錬磨すれば使えるよなあ)」という感想がおのずと出てくる.神経解剖学と痛みの伝わるメカニズムにまっすぐ向き合おう.骨太でけっこう大変だ.学生時代に神経生理を寝て過ごした方(例:私)にとっては正直苦痛かもしれない.しかし,ここでふんばれ! 本書のルールを体に取り入れろ,そうすると本書の中盤以降は楽しくてしょうがない.
市原のオリジナル索引③
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| たんのう | 胆嚢炎の腹痛を考える | 154 | |
| ちゅうい | 注意をそらすような痛みのある損傷 | 28 | |
| ちゅうす | 虫垂炎 | ――の疼痛刺激伝導路 | 8 |
| ――は管腔の閉塞から始まる | 14 | ||
| ――は「心窩部痛」か「臍周囲痛」か | 15 | ||
| ――で痛む場所は患者によって心窩部と臍周囲に分かれ ることに気づいた | 16 | ||
| ――の疼痛刺激伝導路 | 19 | ||
| 虫垂の内腔が拡張していないため関連痛に乏しく,体性痛が初発症状となった―― | 66 | ||
| 一般に腸間膜リンパ節炎は――と似ているといわれるが | 70 | ||
| ――の典型例は本当に教科書の記述どおりだが,非典型例はどこまでも非典型な経過を辿る印象がある | 72 | ||
| ――の初期に「漠然とした不快感」として内臓痛を感じるのに似ている | 182 | ||
| ちゅうす | 虫垂炎と憩室炎の腹痛を考える | 62 | |
| ちゅうす | 虫垂炎の関連痛を考える | 14 | |
| ちゅうす | 虫垂炎の体性痛を考える | 20 |
印象深いのは本書の随所に認められる「○○を考える」というサブ項目タイトルの数々だ.虫垂炎の「こと」,胆嚢炎の「こと」,腹部診察の「こと」を覚えるのではなく,あくまで「虫垂炎を考える」,「胆嚢炎を考える」,「腸間膜リンパ節炎の腹痛を考える」というアイキャッチ.えっ,腸間膜リンパ節炎の腹痛を考えるって!? ギョギョッ,そんな思考をしたことがない…….
市原のオリジナル索引④
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| さくじょ | 削除されている(なぜだ) | 83 | |
| さゆうか | 左右片側の間欠痛や断続痛は消化管以外から考えるのが地雷回避法 | 35 | |
| さゆうさ | 左右差のある非持続痛は消化管疾患以外から考える | 212 | |
| しあつと | 指圧という治療のオプション | 132 | |
| しあつは | 指圧はナゼ効くのか | 136 | |
| しきゅう | 子宮留膿腫の腹痛を考える | 239 | |
| じぞくつ | 持続痛 | 膵臓は実質臓器なので疼痛は関連痛・体性痛ともに――が原則 | 184 |
| 管腔臓器由来の腹痛が――であれば体性痛を意味する | 192 | ||
| じぞくつ | 持続痛とは痛みの強さに「波がない」ものを指す | 4 | |
| しどうい | 指導医モドキ | 190 |
筆者は救急現場で働いていた時代が長いそうだ.執筆のベースにあるのは豊富な臨床経験.血の通った臨床の筋道.クリニカルクエスチョンの深度.なのに,これまでの救急医の本とはどこか違う雰囲気が感じられる.
特筆すべきは,文章の端々に垣間見える,今や古典と称されるような「旧仮名遣い時代の文献」を引用した考察の数々だ.「温故知新」という額装された四字熟語が脳に攻め込んでくる.いったい誰なんだこの著者は.調べてもわからなかった.それもそのはず,本書は「匿名」で書かれているのだ.そ,そ,そんな医学書,ありえる? クセがすごい! 自然と笑みがこぼれる.
福井大学名誉教授の寺澤秀一先生が,帯だけではなく本文にも「顔写真つき」で掲載されている理由を考える.邪推に過ぎないが,「著者をマスクした医学書」をどう編集したらいいものか,医学書院も迷ったのではないか.まったく楽しいことをする.唯一無二の本だ.
「軽度の内臓痛は痛みではなく膨満感や消化不良に似た症状として自覚される」
「左右片側の間欠痛や断続痛は消化管以外から考えるのが地雷回避法」
「指圧はなぜ効くのか?」
これらを“tips”ととらえてしまってはダメであろう.日常のルーティンで「なぜかは知らんけどそういうものなんだよ」と通り過ぎてしまいがちな,メカニズムに関する疑問や発見を,素通りせずにきちんと文章にするということ.それを,匿名でやるということ(笑).
市原のオリジナル索引⑤
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ひだりて | 左手は添えるだけ | 45 | |
| ひっしゃ | 筆者 | すべての管腔臓器は閉塞→拡張により最初に腹痛を生じ,のちに嘔気嘔吐を生じるというのが――の持論である | 22 |
| はたして――は正確に診断できたのだろうか? | 114 | ||
| ――は膝を痛めて走れない | 178 | ||
| ひにょう | 泌尿器科領域の神経分布を考える | 122 |
知 ら ん が な お 前 は 誰 だ (笑)
思わず紙面にツッコんでしまう.でも,スナップを利かせた右手がそのまま宙を舞う.「この問いかけができる本ってやっぱり強いよなあ……」.
◆ ◆ ◆
今月は以上.至高の名著だ,ぜひ心して読んで欲しい.よかったら索引の完全版も見て欲しい.担当編集者のスーさん(あだ名)は,だいぶがんばって項目のチェックをしてくださった,ぼくがあまりに長文の項目を蛍光ペンで塗りまくるのでデザインも大変だったろう.力作.
最後に,私が今回本書を連載に取り上げるにあたって,1つだけ懸念していたことを付記しておく.それはほかでもない,本書の前書きにあるこの一言だ.
うっ,これ,レジデントノートの連載なんだけどな……まあいいか…….
詳細は前書きを読んでいただきたいのだが,匿名著者の言いたいことはよくわかる,それでも,「レジデントノートの隅々にまで目を通すような初期研修医」はどのみちタダモノではないから大丈夫だと思う.かまうもんか,読んで味わえ.
そうだ,言い忘れていた.著者は現在病理医だそうだ.心の叫びを止められない.「クセ……!」
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)