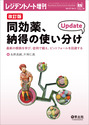- [SHARE]
- ツイート


私は病理医であり,放射線診断医に対してはひとかたならぬ思いがある.画像診断医たちが診て推しはかる「カタチ」を,直接見て語ってフィードバックするのが我々の大事な仕事だからだ.画像と病理は,単純な先攻・後攻の関係ではない.肩を組んで二人三脚をするイメージというのも何か少し,違う.私たちはもうちょっと向かい合っている.
ファイティングポーズをとり,ストロングスタイルで,がっちりと組み合う.お互いが長所を魅せあいながら,その都度,相手の短所を指摘し,補いあう.それはあたかもプロレスのように.病理医にとっての放射線科医は,「毎日対戦する宿敵レスラー」のような存在である.双方が順番にきれいに技をかけ,それを互いが抵抗せずにきれいに受けることをくり返すと,いい試合(診断)が完成し,観客(主治医)は熱狂する.
だから私は,今回のお題本を読むのをとても楽しみにしていた.「好敵手」が書いた本だからだ.ただし,正直に言えば1つだけ,懸念事項もあった.
それは本書が「研修医向け」だということだ.いくらなんでも,形態を専門にしている私にとっては,簡単すぎるのではないか.ほとんど知っている内容ばかり記載された本を知らん顔して読んで「わあすごいいい本だ,さあオリジナルの索引を作っちゃうぜ」といつものテンションで語り尽くせるものだろうか.あまりに得るものが少なければ記事を書くのもしんどいなあ……なんて.
読み終えた今,思う.完ッ全に杞憂であった.
本書は確かに研修医に向けて書かれた本なのだが,私に読まれるのを待っていたような本でもあった.自信を持って人にお勧めできるし,自分のために楽しく再読できる.
さあ,「勝手に索引」を見ていただこう.いつものように,Webで完全版を公開.QRコードからアクセスしてほしい.担当編集者スーさん(あだ名)の索引構成はもはや職人芸である.私が本に蛍光ペンを引いただけのものを,よくもまあこれだけ見事に索引にできるものだ.
市原のオリジナル索引①
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ひかそし | 皮下組織は脂肪の信号を反映してT1強調像,T2強調像,FLAIRのいずれでも高信号 | 34 | |
| びこんぶ | 鼻根部と橋-延髄移行部はどこになるんでしょう? | 26 | |
| ひしつ | 皮質−白質境界・島皮質の不明瞭化 | 29 | |
| びじょう | 尾状葉(caudate lobe)の血流は特殊 | 116 | |
| ひだりは | 左はフォロースルーで振り切ったラケットが最後にクッと上に上がる癖がある(左S3c) | 78 | |
| びまんせ | びまん性軸索損傷(DAI) | 55 | |
| ふくぶだ | 腹部大動脈の解離はその27%に臓器虚血を合併するとの報告もあり | 107 |
「えっ,何,テニス!?」と驚いた.これは何かというと,気管支の走行の覚え方なのである.チキショウ,これを研修の時に知っていたらラクだったろうなあ.
テニスに限らず,全編を通して表現が多彩で,読んでいて楽しい本.わりとデキる研修医と,若手のエースクラスの放射線科医,そしてベテラン指導医が語り合う形式で進んでいく.
会話形式の教科書のリーダビリティはとても高いので,あるいは読者諸氏も「そのうち専門医になったら,会話形式の本,ちょっと書いてみよっかな」的な気分になったりして.しかしこれ,実際にやってみるとドチャクソ難しいんだよな.私クラスの書き手だと,登場人物の脳みそが「全員自分」になってしまって,うまく話を膨らませられない.
その点,本書の対話は見事だ.若手の気分もベテランの気分もきちんと描き出されており「ガチ感」がある.執筆を担当しているのが「若手のエース格」である堀田・土井下両先生であり,レジデントの気持ちもオーベンの気持ちもわかるポイントに立っているからこそ,登場人物たちに絶妙のリアリティが生まれるのだろう.若すぎてもベテラン過ぎてもこうは書けない.経歴の違う三者が,画像診断という素材を真ん中に置いて,それぞれの視座から語り合う構図は,本書にとても大きな効果をもたらしている.
市原のオリジナル索引②
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| にじしょ | 二次小葉のシェーマ | 87 | |
| ねんまく | 粘膜下層が浮腫に陥ると | 153 | |
| のうこう | 脳梗塞 | あっ.――ですか | 14 |
| 前頭葉に生じた――では症状や神経学的所見が不明瞭なこともあり | 14 | ||
| 超急性期――を見逃すな! | 28 | ||
| のうこう | 脳溝の消失・脳実質の低信号化 | 29 | |
| のうざし | 脳挫傷ですね | 51 | |
| のうじょ | 嚢状動脈瘤は動脈の分岐部で発生することが多い | 61 | |
| のうひょ | 脳表に沿うような異常増強効果,すなわちPS型 | 36 |
たとえばここでハイライトした「あっ,脳梗塞ですか」は,研修医のセリフだ.何気なく読み飛ばしてはもったいない.「あっ」と声を出す,すなわち会話の中でそれまで気づかなかったことに到達しているということだからだ.実際,このシーンでは,研修医は「あっ」の直前まで「画像を見て脳梗塞かどうかわからなかった」.急性期脳梗塞と脳膿瘍を鑑別しきれていなかったのである.しかし,対話の中で指導医と若手放射線科医とがアシストをすることで,研修医は「あっ」と気づくのである.そして読者はこの全ての視座を取り込むことができる.これこそ,対話型・通読型教科書の要点であり本質だ.
ちなみに「脳挫傷ですね」は若手放射線科医のセリフ.これを研修医が言えていないというのが妙にリアルである.
市原のオリジナル索引③
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| さいきか | 細気管支を中心として小葉間隔壁によって囲まれる領域をMillerは“二次小葉”として定義している | 87 | |
| さいきん | 細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別項目と鑑別基準 | 86 | |
| さいごは | 最後はお尻の方へクッと… | 82 | |
| さゆうた | 左右対称でびまん性なのがやや気になりますね | 40 | |
| しきゅう | 子宮外妊娠 | ――(ectopic pregnancy) | 170 |
| 腹腔内出血が多い場合には卵管妊娠の破裂を考えるべき | 170 | ||
| ―― vs 卵巣出血 | 170 | ||
| 妊娠早期の卵巣出血(妊娠黄体からの出血)の場合には妊娠反応が陽性になることがあり | 170 |
ここも象徴的だ.研修医が,自分の担当した症例について「くも膜下出血の見逃し」をしたのではないかと怯えているシーン.そこに若手放射線科医が登場して相談に乗る中で,「左右対称でびまん性なのがやや気になりますね」のセリフが出てくる.会話の中で思い込みが論理的に覆されていく場面なのである.網羅型・辞書的教科書ではニュアンスを伝えきるのが難しい,通読型教科書ならではの,面目躍如とも言える見事な流れ.
市原のオリジナル索引④
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| そくのう | 側脳室がなくなったくらいのスライスで緑色の側頭葉もなくなる | 21 | |
| そのいき | その意気だよ! | 89 | |
| そもそも | そもそも“挫傷”とは | 51 | |
| そんなに | そんなに細かく分類する必要はあるのでしょうか…? | 94 | |
| だいどう | 大動脈解離 | ――では石灰化が大動脈壁から離れ,内腔に浮いたように存在する | 104 |
| ――の分類 | 105 |
「そんなに細かく分類する必要はあるのでしょうか…?」にしびれる.
「その意気だよ!」にほっとする.
「対話型にしておけば読みやすいからレジデントノートにぴったりだろ」みたいな安直なつくりではない.そこに「三者」がいることが必然なのである.異なる視座が交錯する点に「医の学問」がハイライトされている.私はこのような,教育目標を達成するために緻密に構成された座組みが大好きだ.
* * *
さて,「異なる視座」でいえば,もう1つ.ぜひ,「虫垂炎」にも着目してほしい.
市原のオリジナル索引⑤
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ちゅうす | 虫垂 | ――自体をしっかりと同定する | 143 |
| ――の起始部は変異が少なく,通常は回盲弁(バウヒン弁)より約3cm尾側の盲腸の後内側壁から起始する | 143 | ||
| ――を先端部までしっかりと追わないと病変を見逃してしまいます. | 145 | ||
| ちゅうす | 虫垂炎 | ――を疑ったときには冠状断や矢状断の再構成画像を積極的に依頼しよう | 145 |
| 中高年者の――の原因としては重要な位置 | 146 | ||
| 急性――のCT所見 | 146 | ||
| 虫垂内腔の液体貯留が増加している場合は,――の可能性が高くなるね | 147 |
本連載ではこれまで,いろいろな本の索引を作ってきた.その中には「虫垂炎」がくり返し登場する.外科でも内科でも,虫垂炎は常に腹痛鑑別の上位だから,当然といえば当然だ.しかし,同じ虫垂炎と言っても,教科書が変われば執筆者たちの視座がまるで違い,記載内容も大きく変わる.観測地点が異なると富士山のカタチが違って見えるけれど全部同じ富士山だ,みたいなイメージ.
本書は画像診断の教科書なので,虫垂炎の症状や治療についての記載は少なく,画像オーダーの仕方や虫垂の探し方などが他より細かく書かれている.「放射線診断医ゆえの視座」によって,虫垂炎という表象が描写されている.ではここで,連載第5回で取り上げた『腹痛の「なぜ?」がわかる本』1)の完全索引から,同じ「虫垂炎」の項目を眺めてみよう.
プレイバック! 市原のオリジナル索引(連載第5回)
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ちゅうす | 虫垂炎 | ――の疼痛刺激伝導路 | 8 |
| ――は管腔の閉塞から始まる | 14 | ||
| ――は「心窩部痛」か「臍周囲痛」か | 15 | ||
| ――で痛む場所は患者によって心窩部と臍周囲に分かれ ることに気づいた | 16 | ||
| ――の疼痛刺激伝導路 | 19 | ||
| 虫垂の内腔が拡張していないため関連痛に乏しく,体性痛が初発症状となった―― | 66 | ||
| 一般に腸間膜リンパ節炎は――と似ているといわれるが | 70 | ||
| ――の典型例は本当に教科書の記述どおりだが,非典型例はどこまでも非典型な経過を辿る印象がある | 72 | ||
| ――の初期に「漠然とした不快感」として内臓痛を感じるのに似ている | 182 |
こちらはもっぱら,痛みのメカニズム,症候学,といった切り口なのがおわかりだろう.『画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン』の索引とはまるでかぶっていない.
おもしろくなってきた.もう1冊見てみよう.連載第4回「外科の診かた」2)の索引で,「虫垂炎」を引いてみる.
プレイバック! 市原のオリジナル索引(連載第4回)
| 読み | 項目 | サブ項目 | ページ |
|---|---|---|---|
| ちゅうす | 虫垂炎 | 翌日できる医者と言ってもらえるかも(^.^) | 102 |
| 夜間原因のわからない腸炎症状で来た患者さん | 102 | ||
| ベテラン外科医の頭のなかの診断項目もこんなものです | 103 | ||
| 糞石の嵌頓がきつい症例の場合 | 103 | ||
| この見事なエコー写真 | 103 | ||
| これが上行結腸でその下端(ガスエコーが途切れるところ)に虫垂根部があるはず | 104 | ||
| 関連痛について | 105 | ||
| もともと虫垂のあった場所,すなわち臍周囲の鈍い痛み | 105 | ||
| 関連痛について | 105 | ||
| 虫垂切除術 | 107 | ||
| 外科医にならなくても,一生使える技術 | 107 |
また違う! 外科の術前検討における項目が並ぶ.内科と外科でここまで違うというのもあらためて眺めてみると興味深い.外科だって画像で診断しているはずなのに,放射線科の本とは異なるニュアンスを感じられるのもワクワクする.
* * *
本稿の冒頭で私はこう述べた.
しかし,自分が業務の中でよく知っているはずの「虫垂炎」1つとっても,教科書が変われば書き方のバリエーションが変わる.病理医としてよく見ていたはずの「虫垂炎」が,他の専門家の目からは似て非なるものとして認識されているのだということを,しみじみ味わう.
私は気づいた.少しだけ鳥肌が立つ.
「クラミジア」についての記載を,連載第6回「お母さんを診よう」3)と見比べてみる.
「大動脈解離」の項目を,連載第2回「心エコー塾」4)と見比べてみる.
これ……今までに作ってきた索引を,ためしに全部統合してみたら,どうなっちゃうんだろう? 年次の違い,専門科の違い,複数のカメラが眺めたスナップ写真を統合して,医療界を立体視するような試みが,できるのではないか……?
* * *
……あ,『画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン』,いい本ですね.しかも,今もレジデントノートで連載中か.第3シーズン? 確固たる実績だ.まあ,人気が出るのもわかるなあ.
参考文献
- 『腹痛の「なぜ?」がわかる本』(腹痛を「考える」会/著),医学書院,2020
- 『研修医のための外科の診かた、動きかた』(山岸文範/著),羊土社,2019
- 『お母さんを診よう』(中山明子,西村真紀/編),南山堂,2015
- 『Dr.岩倉の心エコー塾』(岩倉克臣/著),羊土社,2019
著者プロフィール
- 市原 真(Shin Ichihara)
- JA北海道厚生連 札幌厚生病院病理診断科 主任部長
- twitter:
- @Dr_yandel
- 略 歴:
- 2003年 北海道大学医学部卒業,2007年3月 北海道大学大学院医学研究科 分子細胞病理学博士課程修了・医学博士
- 所属学会:
- 日本病理学会(病理専門医,病理専門医研修指導医,学術評議員・社会への情報発信委員会委員),日本臨床細胞学会(細胞診専門医),日本臨床検査医学会(臨床検査管理医),日本超音波医学会(キャリア支援・ダイバーシティ推進委員会WG),日本デジタルパソロジー研究会(広報委員長)